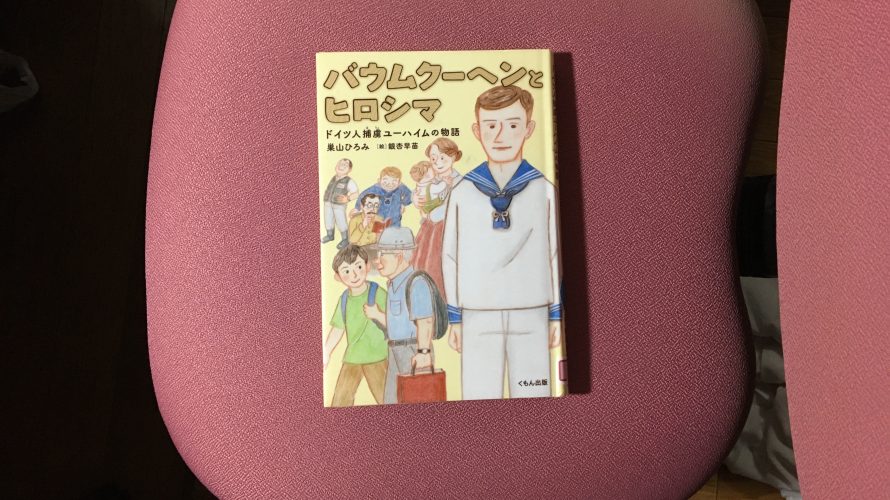ドイツの雑誌に習志野ドイツ人捕虜収容所の記事
市内在住の小畠(こばたけ)さん(詩人・小説家として有名なシュトルムなどドイツ文学研究家、故 小畠 泰さんのご夫人)から「ドイツ兵士の見たニッポン」の執筆者Hさんに「ドイツの雑誌に習志野ドイツ人捕虜収容所の記事が載っている」というご連絡があったそうです。(下の画像は小畠 泰さんが訳されたシュトルムの小説です)

Frieden(平和)に載った習志野収容所の記事
習志野ドイツ人捕虜収容所のことが載っている雑誌の名は「Frieden(平和)」



記事の内容は2019年に習志野市を訪問された
メルバー・琢磨博士(ハイデルベルク大学)へのインタビューでした。
記事の内容をご紹介します。(「ドイツ兵士の見たニッポン」の執筆者Hさんに翻訳していただきました)
ドイツ人捕虜収容所跡にある「ドイツ捕虜オーケストラの碑」(東習志野4丁目)の写真が掲載され、習志野ソーセージについても触れられています。
日本研究
ベートーヴェンの第九と収容所病
日本におけるドイツ捕虜は、第一次世界大戦史の知られざる一章である
ハラルト・ヨーン
中国・チンタオのドイツ植民地が失われた後、何千人ものドイツ兵が日本の捕虜収容所に送られた。その日常生活はどのようなものだったか?
そして、第一次世界大戦のこのあまり知られていない一章について、日本の見解はどうなのか?
研究者のメルバー琢磨(たくま)博士にインタビューしてみた。
背景: 第二次世界大戦はドイツにとっては1945年5月8日に国防軍が降伏して終ったが、戦闘は夏の終わりまでアジア太平洋地域で続いた。
1945年9月2日、アメリカによる広島・長崎への原爆投下後になってやっと、日本は降伏文書に署名した。
1945年のこの終戦のイメージは、日本が第一次世界大戦で果たした役割を忘却に追いやってしまう。
すでに19世紀から20世紀にかけて、日本は新しい大国として世界の舞台に加わった。
早くもこの帝国は、その拡張主義者の努力で中国やロシアと対立した。
1904-05年の日露戦争では、日本の海軍がロシア艦隊を沈めた。
初めて、西洋以外の大国が白人勢力に対して軍事的に勝利したのだ。
日本は今や、国際社会の主要な大国の地位に上っていた。
また、中国におけるドイツ植民地の夢を一撃で終わらせたのも、太平洋における日本の軍事力であった。
1914年11月7日、ドイツ皇帝の部隊は中国の港町・チンタオ(今日のQingdao)で降伏した。
約2ヶ月間の包囲の後、中国におけるドイツの植民地化の歴史は数百人の死者を出して終った。
その歴史は、1897年に2人のドイツ人宣教師が殺害された事件から始まったものだった。
その結果、ドイツ軍は黄海に面した膠州湾を占領した。
ベルリンは中国に、山東半島の地域とその主要都市チンタオを99年間、皇帝ヴィルヘルム2世に貸し与えるよう強要した。
ドイツ帝国海軍は東アジアに駐留する兵士を黄河の下流に移し、その結果、貿易業者と行政スタッフがチンタオに定住した。
しかし、大都市の台頭は、第一次世界大戦の勃発直後に終った。
イギリスと、それに同盟していた日本帝国は、皇帝ヴィルヘルム2世に、チンタオを日本帝国に引き渡すよう要求したが、皇帝はこれを拒否した。
こうして、1914年8月23日、日本はドイツ帝国に宣戦布告した。
その後、1週間の包囲の末、ついにチンタオの町は占領された。
11月7日午前6時20分、ドイツ軍は最後の砦であった信号山に白旗を掲げたのだ。
その結果、何千人ものドイツ兵が日本によって捕虜とされた。
彼らの歴史と日本の捕虜収容所の役割を、若き学者であるメルバー琢磨博士は、彼のプロジェクト、チンタオ・デジタルアーカイブで調査している。
彼の目標は、日本で捕虜となったかつてのドイツ兵が残した個人の遺品から、手記や写真を体系的にコレクションすることだ。
メルバー博士、なぜ日本にいたドイツ捕虜の足跡をたどり始めたのですか?
第一次世界大戦から100年という国際的にも記念すべき時期を迎え、有名な歴史家たちは、読む価値がある第一次世界大戦の歴史の総括的な著作をいくつも出版市場に持ち込みました。
それらを読んだとき、私はアジアの戦争局面はせいぜい端役の役割しか与えられていないことに気づきました。
ドイツ帝国によって、またはチンタオの最後の総督アルフレート・マイヤー・ヴァルデックの名によって租借されたドイツの保護地域チンタオについては一言も触れられていないのです。
日本が第一次世界大戦で連合国の側にいたこと、また地中海の制海権をめぐってさえも戦争に参加していたという事実は、この国ではほとんど知られていないのです。
これは、第一次世界大戦中の日本におけるドイツ兵の歴史に、さらに当てはまります。
日本の捕虜収容所の中に何人のドイツ兵がいたのですか? そして、彼らはどのように扱われたのですか?
数字は情報源によって異なりますが、ドイツとオーストリア・ハンガリーの戦闘員を合わせて4,500人以上が捕虜になったことは確かです。
日本軍の捕虜については、第二次世界大戦の時の連合軍兵士への扱い、あるいはよく言われる虐待のイメージが、常に思い浮かびます。
それに比べると、第一次世界大戦では待遇が良かった。例えば、第二次世界大戦とは対照的に、日本では強制労働者として捕虜を組織的に搾取することはなかったのです。
日本におけるドイツの捕虜の話になると、今日に至るまで板東収容所の話が一番取り上げられます。
この収容所は1917年4月に稼働し、それからしばらくしか使われなかったが、日本にとっては一種の模範収容所でした。ドイツ人は、日常の収容所生活の中で創造的な自由を享受し、多くのスポーツや文化活動を自由に追求することができ、ドイツの囚人と日本人の警備兵、そして地元の人々との間で本当の交流がありました。
それはどこでもそうでしたか?
日本には12以上の収容所がありました。
他の収容所からは苦情の報告があります。すなわち郵便のやり取りは一部機能せず、兵士は食べ物について不平を言い、収容所病に苦しみ、うつ病もありました。
また、ドイツ兵の残した文書には、時には日本人に関する軽蔑的な発言も見られます。
だから、日本での捕虜暮らしは、板東が私たちに信じさせているほどバラ色で牧歌的ではなかったようです。
私の懸念の一つは、全体像をまるで大幅に灰色で描いてしまうことです。
これらの収容所をどのように想像することができますか? ドイツ人はどのような条件の下でそこに住んでいたのですか? そして、この時期はいつ終ったのでしたか?
かなり長い間、兵士たちは兵舎の収容所に収容されました。
兵員や将校のための宿泊施設に加えて、後期には住居はもう少し豪華になり、キッチンやダイニングルームが、少なくとも多少のプライバシーを与えていました。
動物を飼ってすることができ、収容所印刷室、図書館、それに広場があって、そこでは例えばテニス、体操、綱引き、競技、フィールドホッケー、そしてもちろんサッカーなど、スポーツを実践することができました。
兵士たちは文化活動を追求し、オーケストラ、合唱団、劇団、あらゆる種類の学習とワーキンググループを設立しました。
こう言うとまるで非常に牧歌的に聞こえるかもしれませんが、兵士が何よりも一つのことを望んでいたという事実を隠してはいけません。それは収容所の中から、彼らの愛する人の家へと思いを寄せていたということです。
しかし、兵士たちは翌年のパリ講和会議の後にやっと送還されることになり、第一次世界大戦が終った1918年にはまだまだ収容所の中でした。
勝者と敗者の間には文化的な関わりもありましたか?
実際のところ、日本人とドイツ人の間には、勝者と敗者、囚人と警備員との関係を超えた接触があったのです。
すなわち、収容所はどこも日本の商人によって支えられており、ドイツ捕虜も日本の工場で働くことが許されていました。
ドイツ人から何かを学ぶことは、大いに興味を引くことでした。例えば、今でもドイツ風に作られた「習志野ソーセージ」は、東京に近い千葉県習志野市の名物です。そこには、最大の収容所が存在しました。
また、収容所の中で展示会が開催され、地元の人々がそこを訪れました。
これらの中で、ドイツの兵士は絵画、技術機器や職人技を示しました。
ドイツ人も日本文化を知りました。収容所を訪れる力士の写真があります。
また、ドイツ人と日本人の間でスポーツの出会いもありました。
例えば、日本サッカーのルーツの一つは、これらの収容所にあります。
また、日本の観客の前で演劇やオーケストラを結成し、演奏を行いました。
ベートーヴェンの第九は、ドイツの収容所オーケストラによって日本で初演されました。
日本はこの歴史をどのように扱ってきたのか。その問題に関する博物館や展覧会はありますか?
第一次世界大戦は、日本では歴史の授業でもほんの端役しか演じられていません。
その他のテーマは、明治維新、大国としての日本の台頭、日露戦争(1904/05)、アジア太平洋戦争/第二次世界大戦、原爆などです。
特に、今日の日本の大都市やその近くにあった収容所の話はほとんど知られておらず、日本では忘れ去られています。
具体的な研究はどのようなものでしょうか?
私の研究の良いところは、子孫からの手紙が私に届くということです, 特に元チンタオ人の孫の世代から,私が彼らの遺品を吟味したりデジタル化したりできるよう、貸し出してくれるのです。メール送信や、持参してくれる人もいます。
日本の専門家との意見交換や、アーカイブや図書館の研究など、日本への旅行も私の研究に役立ちました
一方で私は、その場で手がかりを探し、もしそうなら、収容所の何かが今日でも見ることができるかどうか、収容所の物語が地元で何がどのように提示されているのかを調べるのです。
第一次世界大戦は今や100年前です。あなたの研究の話題になる理由は何ですか?
私の視点から見ると、グローバリゼーションは政治、メディア、社会における私たちの時代の流行語です。
グローバルな相互依存性がはるかに早くから存在し、例えば知識と知識の特定の交換プロセスが行われたことを、私の研究が非常によく示していると思います。
ちなみに、今年75年前の第二次世界大戦の終結を記念しているという事実そのものが私のテーマとして残っています。
私たちの中には、世界大戦を経験し、それについて話すことができる人々がまだいます。
第一次世界大戦は第二次世界大戦とは全く違い、話すことができるのはドイツ兵の子孫であり、ドイツ兵は彼らにとって、個人的で、感情を持って思い出される自分のおじいさんです。
しかし、この世代の孫たちは、自分の死に近づいています。
次の世代はもはやこの遺産をどうするか分からないでしょうし、ドイツ兵だった先祖との個人的で感情的なつながりもないので、個人の思い出も消されてしまうでしょう。
歴史家としての私にとって、これは今、ほぼ最後のチャンスです: 私は21世紀の技術的方法、すなわちデジタル化によって、第二次世界大戦の歴史家の後世と将来の世代のために保存したいと思います。
研究を背景に、太平洋の現在の緊張をどのように評価しますか? 新たな武力紛争の脅威はありますか?
日本と隣国のロシア、中国、南・北朝鮮との間の太平洋の緊張は数十年前から続いています。
今のところ日本にとって深刻な戦争の危険は見当たらないが、第一次世界大戦を見れば、長年にて蓄積する緊張と、ちょっとした出来事と政治的意思決定者による無謀なアプローチで山火事が起きてしまう、ということが良くわかります。
紛争当事者の側で、賢明かつ慎重に行動し、日本が今後も戦争を免れることを切に願っています。(了)
○メルバー琢磨博士の紹介
日独関係史の歴史家。ハイデルベルク大学の異文化交流研究センターで教え、研究を行っている。takuma.melber@hcts.uni-heidelberg.de
○フリーデン(平和)誌、2020年2月号
同誌はVolksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.(ドイツ戦争墓地維持国民同盟)の発行。
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. | Gemeinsam für den Frieden
Der Volksbund ist eine humanitäre Organisation. Er widmet sich im Auft...
この団体は第一次世界大戦直後の1919年12月に設立され、ドイツ国外に残るドイツ人戦没者墓地の維持管理を行っている。維持管理する墓地は26か国832か所に及ぶという。事業費はほとんどが会費、寄付金、募金で賄われており、その他は連邦と州からの交付金である(Wikipedia)。
(編集部より)
メルバー琢磨博士が2019年に習志野市を訪問された時の「住みたい習志野」の記事です。
第一次世界大戦と習志野―大正8年の青きドナウ― - 住みたい習志野
習志野市役所ホームページに掲載されました。以下市HPよりhttps://www.city.narashino.lg.jp/citysales...
第一次世界大戦と習志野―大正8年の青きドナウ― - 住みたい習志野
今回ブログにこの雑誌記事を載せるにあたっては、メルバー琢磨博士のご協力のもと、インタビュアーのハラルト・ヨーンさん、Frieden編集部の皆さんの特別のご配慮をいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。
コメントをお寄せください。
<パソコンの場合>
このブログの右下「コメント」をクリック⇒「コメントを投稿する」をクリック⇒名前(ニックネームでも可)、タイトル、コメントを入力し、下に表示された4桁の数字を下の枠に入力⇒「コメントを投稿する」をクリック
<スマホの場合>
このブログの下の方「コメントする」を押す⇒名前(ニックネームでも可)、コメントを入力⇒「私はロボットではありません」の左の四角を押す⇒表示された項目に該当する画像を選択し、右下の「確認」を押す⇒「投稿する」を押す