習志野市でのボトルシップ発見から四半世紀
きょう8月28日は、習志野俘虜収容所にいたドイツ兵が残したボトルシップが発見されて25年になるということで、「ドイツ兵士の見たニッポン」の著者Hさんにインタビューしてみました(編集部)。
――ボトルシップが発見されて25年になるそうですね。
H: そうですね。平成9年(1997)8月28日のことでした。当時私は社会教育課の事務員だったのですが、ちょうど社会教育課の市史編さん室では市内の高齢者を訪ねて、昔の風習などにつき「民俗調査」というのを行っていました。その中でこの日、津田沼にお住まいの歌田實さんにお越しいただいてお話をうかがっていたところ、話が一段落した頃、歌田さんが、民俗調査とは関係ないけれど、わが家に昔から、こういうものがある、ということでボトルシップを見せてくださった。それで「お前も、ちょっと来てみろ」と私も編さん室に呼ばれて行ったのが最初でしたね。
――歌田家にはどうしてボトルシップが伝わったのでしょう?
H: ドイツ捕虜が習志野にいた大正の頃、歌田さんのお母さんは長作小学校の先生をなさっていたそうです。そこである日、収容所を見学に行こうということになり、子供らを連れて収容所に行った。ドイツ兵も子供らを見て喜び、言葉は通じないものの遊んでくれた。そして帰る段になったら、ドイツ兵がおいで、おいでをして、ボトルシップを一本くれた。それが先生の家に伝わった、ということなんですね。びんの中にどうやって船の模型を入れたのだろうと、子供らは大喜びだったそうです。

――作ったドイツ兵の名前などは伝わっていないのですか?
H: 残念ながら作者の名前は書かれていません。ただ、3本マストの外洋船なのに、後ろにはドイツの湖水やアルプス、お城の塔が見えるんですね。こういう船に乗って、早く故郷に帰りたいなぁというメッセージなんでしょう。
とにかく、これで初めて、習志野のドイツ兵が残した具体的な遺品が見えてきたわけです。なにしろ『習志野市史』は、通史編というのがその2年前、平成7年に出たばかりだったのですが、ドイツ兵については“昔のことで、今となってはよくわからない”と匙を投げています。しかし、こうしてボトルシップが出てきた以上、よくわからないでは済まなくなってしまいました。
歌田さんと入れ替わるように8月31日には、福岡県久留米市の教育委員会から職員の方が来訪されました。久留米にもドイツ兵がいたのですが、その史料展を企画しており調査のために東京まで来た。ついでに習志野収容所の状況を聞きに来た、というお話でした。そして、よくわからないどころか、ドイツ側にはかなりの記録が残っているよと、久留米さんからいろいろ情報を教えてもらったわけです。そして、私がちょっとドイツ語が出来たもので、ドイツにいる数人のコレクターに連絡を取って史料を取り寄せてみたところ、実にいろいろなことがわかってきた。捕虜オーケストラなども、有名な板東収容所(徳島県鳴門市)では許されたものの、習志野あたりでは許されなかったのではないか、と思われたのですが、どうして、どうして。立派な「習志野捕虜オーケストラ」があったことがわかってきました。これは大変だ、ということで調査を始めて、史料展として世に示せたのは平成12年でしたかね。
――ということは、歌田さんがボトルシップを持ち込まれなかったら、この歴史は「よくわからない」で消えてしまったかも知れないわけですね。
H: そうですね。実際、その後25年経って、今ではドイツ側の子孫だとかコレクターもだいぶ亡くなってしまいましたから、あの時調べなかったら、もうわからなくなっていたでしょうね。
――いちばん苦労されたところは何でしょう?
H: 調査をする予算をもらうにも、まず取り寄せた史料を解読して、こんなことが書いてあるから本格調査が必要だと上司に訴えなければならないわけですね。ところが、当時の手紙とか日記などは、ドイツ語はドイツ語ですが、文字が違うのです。
――ローマ字ではないんですか?
H: ドイツ文字というのがあるんですね。

これがドイツ文字なんですが、通称亀の子文字とかひげ文字といって、今でもよくワインのラベルとかお菓子の箱なんかで見かけると思います。当時のドイツ語は、新聞でも小説本でも、みんなこれで印刷されていました。
そして、このドイツ文字の筆記体というのがあるんですね。これはドイチュラント、ドイツ国と書いてあるのですが、上からローマ字、ドイツ文字、そしてドイツ文字の筆記体です。

手紙や日記といった手書きの史料は、みんなこれで書いてある。ローマ字とはだいぶ様子が違いますね。ドイツでもヒトラーの時代には、このドイツ文字をやめてローマ字を使うようになったそうですから、それより若い世代は読めません。ちょうど我々が、江戸時代のくずし字の手紙を読もうというようなものですね。
年配のドイツ人女性に教えてもらいながら、何とかこれを読んで活字体にして、それを日本語に翻訳する。そして、こんな面白いことが書いてあるから、ぜひ本格調査をやらせてくれ、史料展をやらせてくれと役所の上司を説得しなければならない。お金が付かなければ、誰かに何かを頼むもなにも、まるで始まらないわけですから。
――これはかなり特殊技術ですねぇ。
H: 今ではドイツでも、AIで解読する技術など開発されているようですが、25年前にはそんなものありませんからね。書き順を覚えて、こんな言葉があるのかなと独和辞典を見比べながら、なんとか書き起こしていくわけですね。個人の書きぐせも出てきます。

これなんか、何て書いてあるかわかりますか?
――いや、まるで読めませんね。
H: ミリエスの楽譜です。Schließe mir die Augen beide(シュリーセ ミア ディー アウゲン バイデ)と書いてあるんですね。「閉じておくれ、僕の眼を」という曲のタイトルです。
「閉じておくれ僕の眼を」は習志野ドイツ人俘虜収容所で作曲された - 住みたい習志野
習志野収容所で作られた曲「閉じておくれ…」を県立津田沼高オケが演奏。「習志野の宝に」 - 住みたい習志野
こんな仕事に追われた結果、平成12年に資料展を開き、その図録を基に「ドイツ兵士の見たニッポン」という本も公刊したのですが、今でも、習志野にドイツ兵がいたなんて初めて聞いたとか、日本がドイツと戦争したなんてウソだろう、学校で習わなかったという方がたくさんおられるようです。特に、先祖代々習志野に暮らしてきたという方は、死んだ親父もじいさんも、こんな話はしていなかった。本当なのか、という疑いが強いようです。大切な郷土の歴史、ドイツとの国際交流、大事にする習志野市の姿勢が求められますね。本も2千部あまりで絶版にされてしまいましたので、今、古本でネット検索すると、とんでもない値段がついていますよ(笑)。
(定価1800円のこの本、今amazonでは一番安値で5270円になっています)

――ところで、ボトルシップは現在、どこで見られるのでしょう?
ボトルシップは市役所5階の市史編さん室に保管しているので、見たかったら社会教育課(047-453-9382)に申請を出さなければいけないようです。ドイツ兵は、習志野の子どもらに、と言って残していってくれたはずなのに…
他の市にはある「郷土資料館」が習志野市にはないので、市民が郷土の歴史に接する機会が限られています。ボトルシップもそうですが、せめて子どもたちや市民の方たちがいつでも見られるように、どこかに展示してもらえれば、市民の方たちにも喜ばれるでしょうね。
――このドイツ人捕虜収容所の歴史、とても面白いのに、習志野市の学校では教えていないようです。貴重な歴史なのに、もったいないですね。ありがとうございました。(了)
瓶詰細工(びんづめざいく)=ボトルシップの由来。妻の手紙で一念発起、技術みがいたドイツ魂 - 住みたい習志野
習志野歴史散歩(番外編):習志野市に郷土資料館はないけれど… - 住みたい習志野
永久保存版?郷土の歴史はこんなに面白い。「住みたい習志野」の歴史記事アーカイブ - 住みたい習志野
習志野「ドイツ人捕虜オーケストラの碑」秘話:オクセンドルフ夫人の大活躍 - 住みたい習志野
(ボトルシップなどの展示が行われたときの東京新聞の記事)
京成津田沼駅前クレストホテルで行われた「ドイツ兵士の見たNARASHINO」特別資料展図録

特別資料展に寄せられたドイツ大使館からのメッセージ
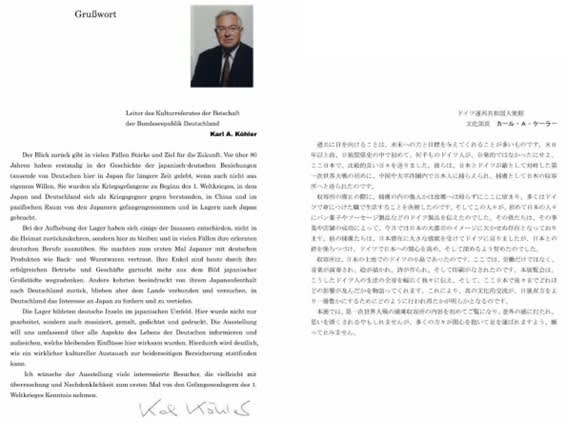
習志野ドイツ人捕虜たちのオーケストラ

当時のコンサートのパンフレット

習志野ドイツ人捕虜収容所にいた著名な指揮者・演奏家、ハンス・ミリエスさん。彼が習志野で作曲した「閉じておくれ、僕の眼を」という曲、今も習志野市で歌い継がれています。

収容所には軽音楽バンドもありました。

コメントをお寄せください。
<パソコンの場合>
このブログの右下「コメント」をクリック⇒「コメントを投稿する」をクリック⇒名前(ニックネームでも可)、タイトル、コメントを入力し、下に表示された4桁の数字を下の枠に入力⇒「コメントを投稿する」をクリック
<スマホの場合>
このブログの下の方「コメントする」を押す⇒名前(ニックネームでも可)、コメントを入力⇒「私はロボットではありません」の左の四角を押す⇒表示された項目に該当する画像を選択し、右下の「確認」を押す⇒「投稿する」を押す






































