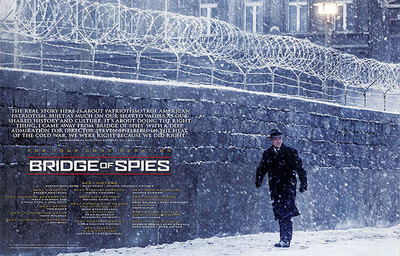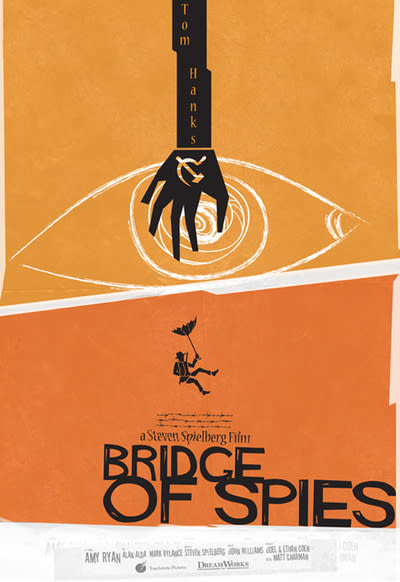いい買物ができました。
Start-rite/スタートライトという子供の靴をセールで見つけたのです。
わが家の娘はもう私と同じ足のサイズですので、姪のために。
このブランドはイギリスの老舗子供靴で、特に女の子のストラップシューズが人気です。ロンドンのおしゃれなセレクトショップや百貨店でもまずこのブランドを扱っていて、靴屋さんではシューフィッターのいる店で扱ったりもしています。
当然お値段もそれなりなのです。が、イギリスにはチャリティショップという素晴らしい文化があり、子供のものはサイズがすぐ変わるためコンディションのよいものも多く見つかるためよく買っていました。
日本でも人気のイギリスのブランドはたくさんありますが、こんなにかわいい子供の靴がなぜかどうしてもほとんど入手できません。
これを語り出すと、相当大勢の人を敵にまわしてしまうのですが、まあブログは日記だ、許してくださいませませ・・・
日本の子供は革靴(フェイクも含む)を履かない。
というか大人が履かせない文化が深く根付いている。
ここ20年くらいで、欧米のファストファッションも日本に定着し、庶民でも日本の企画以外の子供服を買うチャンスは整いました。ですので、服装はほぼ欧米と差がなくなって来たのですが、どういうわけか、靴だけは「子供の靴はいつでもどんな時でも運動靴」という習慣は残っています。
運動靴がダメだとはちっとも思っていませんよ!私もスニーカーはいて通勤もします。
でも、学校や幼稚園の制服ってある意味フォーマル服なのに、なぜアニメキャラやキラキラ付属物が過剰についているスニーカーをあわせるのがもっともメジャーなんでしょうか?
子供はキラキラどころか音や光が出るとかおもちゃのような靴が好きなのは当たり前です。でもおもちゃはおもちゃで、服は服、それは大人が教えるものでしょ?
大人ならリクルートスーツには普通の革靴を合わせるのはそれが正式だからで、子供の学校の制服もそうであるべきなんです。中高生になるとローファーが主流になりますけれど、もっと小さくても制服にはそういう靴しか合わないでしょ?
まあ、浴衣や着物でも洋服風というのもある時代ですから崩しにルールを破るのはいいですけれど、まだルールを学ぶ段階の若い時期に、ルールを学べないで、美意識も形成されません。
その掟破りの服装が一般化しているために、娘が1年生の時制服に革靴を合わせて(と言ってもゴム底)登校させていたら先生に「しましまさんはオシャレすぎる」と言われたんですね。適正なコーディネイトはおしゃれですけれども、ちっとも過ぎてないのに。その靴が赤とかゴールドだったら過ぎてますけど、マットな黒なんだから紺と白とグレーの制服には最も普通の組み合わせで、黄色やピンクのキラキラがついたスニーカーの方がよっぽどおしゃれすぎです。
という胸の痛い経験があるので、日本の子供靴事情の話になるとつい感情的になってしまうのですが、どうしても制服にスニーカーを履かせたいのならば、白、紺、黒などの無地にすればいいのに。きっと選ぶ大人の美意識も子供時代に養われなかったから無法地帯なんだわ。
ところで、Start-rite、ロンドンのお店ではほとんどストラップの靴しか見たことなかったんですが、200年以上の歴史を持つこのブランドも、今世紀になって経営を改革したんですね。そのせいなのか(?)公式サイトには、ありとあらゆるデザインが展開されています。はい、イギリスの子供だって制服脱いだらカラフルな子供らしいかわいい服を着てカラフルな靴を履いてます。要するにTPOですよね。
うん、でも昼間のカジュアルな服と夜のドレスの区別がハッキリしているイギリスに比べてその線引きがゆるい日本の洋服。やはり歴史の浅い文化ってルールがゆるいのかもね・・・詳しくないけど、着物なら組み合わせやTPOの基礎ってしっかり決まっててそれを破るのはあえて、みたいな崩しの上級技ですものね・・・
姪は大学まである幼稚園に入園するから、服装もお嬢さんにふさわしいルールを教わってこの靴の出番がありますように。