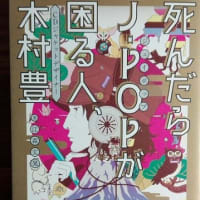エイベック研究所社長の武田さんと宮台真司さんの対談の後編。
もし「心ある (私の主観だが) 」マーケティング業務従事者だったら、このタイトルだけでピンとくるものがあるはずだ。
宮台真司の言葉は、いつでも私を魅了して止まない (以下黒字部分は引用)。
■マーケターとしては早すぎた?宮台真司
宮台:そう。第三が〈脱偶発化〉です。出会い系サイトや婚活サイトは、年収・身長・学歴・趣味などのスペックへのニーズを元にマッチングされます。自分が最も嫌うタイプの相手を好きになるアクシデントがありえません。すべてが枠の内側で起こります。
〈完全情報化〉も〈脱タブー化〉も〈脱偶発化〉も、ニーズに応じたものです。前回お話ししたように、「ニーズに応じたマーケット・イン」は人々の幸福値や尊厳値を下げます。人の幸福や尊厳は必ず〈未規定性〉とともに与えられるのです。
アップルの製品が我々に驚きと感動をもたらしたのは、宮台が言うところの〈未規定性〉によることは言うまでもないだろう。
それにしても、既に80年代(バブルで浮かれてた時代)に、すでに「マーケット・イン」が、人々の幸福値や尊厳値を下げることを押さえていたなんて早すぎだよな(笑)、流石!
先日私は、Facebookでこう書いた。
「新しいものを創るのは、いつの時代でも、どこでも、マジョリティ(多数派)ではなくマイノリティ(少数派)だ」
「マジョリティがいつも正しいとは限らない。いつの間にか50基の原発で経済・生活の土台が築かれる世の中になってしまったのは、マジョリティが間違ってたからじゃないのか?」
と書いたけど、当時の(そして私も身を置いていた)マーケティング業界において、宮台は確実にマイノリティだったはずだ。
そして宮台は「新しくて」「正しかった」わけだ(新しすぎた・・・けど)。
■社会学的、歴史的視座はマーケティングにも不可欠だ
武田:宮台さんは、モノが輝かなくなったのは、モノのせいではなくて、私たち消費者側の心の問題だと断言されていますよね。
宮台:そう。ただし〈個人的な心理の問題〉でなく、〈社会的な意味論の問題〉です。その中で、新たに開発されたモノも、随所に残った都市の光と闇の対照も、独特の意味加工を経て体験されました。新技術も貧困も、いまとはまったく異なる仕方で体験されたのです。
73年の石油ショックで「低成長時代」になります。石油ショックの直前、「3C」を含めた耐久消費財の普及曲線がプラトーに達し、新規需要より買替え需要が専らになりました。そして、77年からオタクの萌芽が現れ、83年には誰の目にも「見える化」します。
消費者心理と商品・サービス、という視点のみの「コンシューマ・マーケティング」は不全である。
社会学が必要だ。
Cultural Marketing もしかり。
表層的なトレンドに振り回されない「歴史観」というものも必要だ。
Cultural Marketing Lab INOUE. の得意とするところだけどね(宣伝・・・笑)。
■「ジラールの欲望の三角形」の崩壊?(わからない人は拙著 PDF版78ページ参照のこと)
宮台:(中略)ところが、島宇宙がバラけ、所属が不透明かつ流動的になり、そのぶん人間関係がその場のノリを維持するだけの希薄なものになると、「他者の欲望を自分の欲望とする」メカニズムが働かなくなります。その結果、驚くべきことに、欲しいものがなくなるのです。
これが、マス・マーケティングが威力を発揮した時代の終焉、の正体だ。
「記号消費」の終焉と表現する人もいる。
私の場合は、「記号消費」が終焉したわけでなく、ヴェブレンの「顕示的消費」が終焉しただけだ、と拙著 PDF版138ページで定義しているが。
宮台が指摘する「コモディティ化の段階説」は重要だ。
<第1段階=耐久消費財飽和>
<第2段階=島宇宙拡散>
宮台:なるほど。僕は先日まで東京都民投票条例の制定を求める直接請求の請求代表者でした。住民投票の本質は、ポピュリズム的な衆愚政治の恐れを批判される「世論調査による政治決定」でなく、住民投票に先立つ数カ月間の公開討論会の活動にあります。
この宮台の指摘をみるにつけ、「政治」も「マーケティング」にも相通じることがあると感じざるを得ない。
消費者心理をつかむことは大切だが、それが表層的である限り、「ポピュリズム的な衆愚政治」という「世論調査による政治決定」と同じ愚を犯すことになるわけだ (「n=1」の大切さにも通じるけど)。
■エイベック研究所の企業コミュニティサービス
この対談シリーズでは、宮台真司の発言を大幅に引用してきたが、ホスト役の武田さんの発言も貴重だ (そもそも、ホスト役として宮台真司とコミュニケートできるだけの社会学の知識・知見をお持ちなのが武田さんだ)。
今回の対談のタイトル 「生活のリアリティ」が「社会のコモディティ化」を打破するのキモとなる箇所だ。
一般的には、企業とユーザーの密な結びつきは、ハーレーやマッキントッシュなど高関与で商品の特徴が差別化されたもの、と限定されがちだが、低関与商品でもそれは可能であり、事実、武田さんが実務で実証しているのだ。
武田:商品はフルーツなので、それを持っているからといって仲間から注目されたりするものでもなければ、オーダーメイドで私だけのものになるわけでもありません。しかし、フルーツを自宅に持ち帰って消費するプロセスは千差万別です。それら多様な生活のリアリティがソーシャルメディアを通して噴水のように表出されています。
たとえば、そのフルーツを食材にしたレシピ大会や子どもと一緒に撮る写真大会などです。そういう活動に参加していると、スーパーマーケットで買い物をしている際、彼女らの目にはそのフルーツが輝いて見えるのだそうです。
これは、彼女らが主体的に参加しているコミュニティの履歴が、そのフルーツと、またそのフルーツを通したほかの参加者たちとの関係を特別なものにしているからだと分析しています。つまり、自分がその商品に関与しているという実感が、商品を輝かせているのだと思います。
***************************************
▼記事へのご意見、Cultural Marketing Lab INOUE.へのお問い合わせは下記メールにてお願いいたします。
sinoue0212@goo.jp
***************************************
▼『コンテンツを求める私たちの「欲望」』
電子書籍(無料)、閲覧数8,300突破しました!
私の思想=文化マーケティングの視座が凝縮されています。
http://p.booklog.jp/book/43959
***************************************
▼パートナー企業様
*詳細につきましては担当者とご説明に参ります。
【ソーシャルリスニング】につきましては、
GMOリサーチ株式会社 「GMOグローバル・ソーシャル・リサーチ」
http://www.gmo-research.jp/service/gsr.html#tabContents01
【激変するメディアライフ! 感性と消費の新常識】
アスキー総合研究所「MCS2012」
http://research.ascii.jp/consumer/contentsconsumer/
***************************************
お読み頂き有難うございます。
(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。

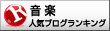 音楽 ブログランキングへ
音楽 ブログランキングへ
 マーケティング・経営 ブログランキングへ
マーケティング・経営 ブログランキングへ
もし「心ある (私の主観だが) 」マーケティング業務従事者だったら、このタイトルだけでピンとくるものがあるはずだ。
宮台真司の言葉は、いつでも私を魅了して止まない (以下黒字部分は引用)。
■マーケターとしては早すぎた?宮台真司
宮台:そう。第三が〈脱偶発化〉です。出会い系サイトや婚活サイトは、年収・身長・学歴・趣味などのスペックへのニーズを元にマッチングされます。自分が最も嫌うタイプの相手を好きになるアクシデントがありえません。すべてが枠の内側で起こります。
〈完全情報化〉も〈脱タブー化〉も〈脱偶発化〉も、ニーズに応じたものです。前回お話ししたように、「ニーズに応じたマーケット・イン」は人々の幸福値や尊厳値を下げます。人の幸福や尊厳は必ず〈未規定性〉とともに与えられるのです。
アップルの製品が我々に驚きと感動をもたらしたのは、宮台が言うところの〈未規定性〉によることは言うまでもないだろう。
それにしても、既に80年代(バブルで浮かれてた時代)に、すでに「マーケット・イン」が、人々の幸福値や尊厳値を下げることを押さえていたなんて早すぎだよな(笑)、流石!
先日私は、Facebookでこう書いた。
「新しいものを創るのは、いつの時代でも、どこでも、マジョリティ(多数派)ではなくマイノリティ(少数派)だ」
「マジョリティがいつも正しいとは限らない。いつの間にか50基の原発で経済・生活の土台が築かれる世の中になってしまったのは、マジョリティが間違ってたからじゃないのか?」
と書いたけど、当時の(そして私も身を置いていた)マーケティング業界において、宮台は確実にマイノリティだったはずだ。
そして宮台は「新しくて」「正しかった」わけだ(新しすぎた・・・けど)。
■社会学的、歴史的視座はマーケティングにも不可欠だ
武田:宮台さんは、モノが輝かなくなったのは、モノのせいではなくて、私たち消費者側の心の問題だと断言されていますよね。
宮台:そう。ただし〈個人的な心理の問題〉でなく、〈社会的な意味論の問題〉です。その中で、新たに開発されたモノも、随所に残った都市の光と闇の対照も、独特の意味加工を経て体験されました。新技術も貧困も、いまとはまったく異なる仕方で体験されたのです。
73年の石油ショックで「低成長時代」になります。石油ショックの直前、「3C」を含めた耐久消費財の普及曲線がプラトーに達し、新規需要より買替え需要が専らになりました。そして、77年からオタクの萌芽が現れ、83年には誰の目にも「見える化」します。
消費者心理と商品・サービス、という視点のみの「コンシューマ・マーケティング」は不全である。
社会学が必要だ。
Cultural Marketing もしかり。
表層的なトレンドに振り回されない「歴史観」というものも必要だ。
Cultural Marketing Lab INOUE. の得意とするところだけどね(宣伝・・・笑)。
■「ジラールの欲望の三角形」の崩壊?(わからない人は拙著 PDF版78ページ参照のこと)
宮台:(中略)ところが、島宇宙がバラけ、所属が不透明かつ流動的になり、そのぶん人間関係がその場のノリを維持するだけの希薄なものになると、「他者の欲望を自分の欲望とする」メカニズムが働かなくなります。その結果、驚くべきことに、欲しいものがなくなるのです。
これが、マス・マーケティングが威力を発揮した時代の終焉、の正体だ。
「記号消費」の終焉と表現する人もいる。
私の場合は、「記号消費」が終焉したわけでなく、ヴェブレンの「顕示的消費」が終焉しただけだ、と拙著 PDF版138ページで定義しているが。
宮台が指摘する「コモディティ化の段階説」は重要だ。
<第1段階=耐久消費財飽和>
<第2段階=島宇宙拡散>
宮台:なるほど。僕は先日まで東京都民投票条例の制定を求める直接請求の請求代表者でした。住民投票の本質は、ポピュリズム的な衆愚政治の恐れを批判される「世論調査による政治決定」でなく、住民投票に先立つ数カ月間の公開討論会の活動にあります。
この宮台の指摘をみるにつけ、「政治」も「マーケティング」にも相通じることがあると感じざるを得ない。
消費者心理をつかむことは大切だが、それが表層的である限り、「ポピュリズム的な衆愚政治」という「世論調査による政治決定」と同じ愚を犯すことになるわけだ (「n=1」の大切さにも通じるけど)。
■エイベック研究所の企業コミュニティサービス
この対談シリーズでは、宮台真司の発言を大幅に引用してきたが、ホスト役の武田さんの発言も貴重だ (そもそも、ホスト役として宮台真司とコミュニケートできるだけの社会学の知識・知見をお持ちなのが武田さんだ)。
今回の対談のタイトル 「生活のリアリティ」が「社会のコモディティ化」を打破するのキモとなる箇所だ。
一般的には、企業とユーザーの密な結びつきは、ハーレーやマッキントッシュなど高関与で商品の特徴が差別化されたもの、と限定されがちだが、低関与商品でもそれは可能であり、事実、武田さんが実務で実証しているのだ。
武田:商品はフルーツなので、それを持っているからといって仲間から注目されたりするものでもなければ、オーダーメイドで私だけのものになるわけでもありません。しかし、フルーツを自宅に持ち帰って消費するプロセスは千差万別です。それら多様な生活のリアリティがソーシャルメディアを通して噴水のように表出されています。
たとえば、そのフルーツを食材にしたレシピ大会や子どもと一緒に撮る写真大会などです。そういう活動に参加していると、スーパーマーケットで買い物をしている際、彼女らの目にはそのフルーツが輝いて見えるのだそうです。
これは、彼女らが主体的に参加しているコミュニティの履歴が、そのフルーツと、またそのフルーツを通したほかの参加者たちとの関係を特別なものにしているからだと分析しています。つまり、自分がその商品に関与しているという実感が、商品を輝かせているのだと思います。
***************************************
▼記事へのご意見、Cultural Marketing Lab INOUE.へのお問い合わせは下記メールにてお願いいたします。
sinoue0212@goo.jp
***************************************
▼『コンテンツを求める私たちの「欲望」』
電子書籍(無料)、閲覧数8,300突破しました!
私の思想=文化マーケティングの視座が凝縮されています。
http://p.booklog.jp/book/43959
***************************************
▼パートナー企業様
*詳細につきましては担当者とご説明に参ります。
【ソーシャルリスニング】につきましては、
GMOリサーチ株式会社 「GMOグローバル・ソーシャル・リサーチ」
http://www.gmo-research.jp/service/gsr.html#tabContents01
【激変するメディアライフ! 感性と消費の新常識】
アスキー総合研究所「MCS2012」
http://research.ascii.jp/consumer/contentsconsumer/
***************************************
お読み頂き有難うございます。
(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。