清水昶は二〇一一年五月三〇日に、七〇歳で病没した。今年の五月で没後四年を迎える、早いものだ。私はいまもなお、背中を丸くして暗い目を燃やしながら日本酒を仰いでいる彼の姿が生々しく生きているのを感じる。私はこれからの生涯、いくどか彼、清水昶を追いかけ続けてゆくだろう。それほどに、私にとって詩人らしい詩人は清水昶しか存在し得ず、彼の死で私はこの人は本物の詩人だと思わせる詩人が皆無になってしまった。好きな詩人、どころではない。好きな、という生ぬるい連帯は好きではないのだ。私に深い傷を負わせた、仇のように追慕する詩人なのであって、それ以外の詩人は名を挙げることが私にはできかねる。
実存で詩人、どこからどう見ても詩人、言葉に刃を秘め、抜き身で酒を仰ぐ彼の詩は黄金のように眩しかった。洗練されたレトリック、詩が求めんとする営みに近づくことなく遠望し、自己のパスワードの解析のみに耽る詩の氾濫のなかで、これほどストイックで死を凝視しながら、直喩で荒々しく詩の実(さね)を鷲掴みにし、擲ちながら、権威とは無縁で、だれにも省みられず、なにも望まずにひっそりとこの世から退場した清水昶。私はまだ彼が死んでしまったことを認めるわけにはいかない思いがある。
彼の詩の殆どは「ぼくらは」「おれたちは」「きみは」と必ず複数形か二人称代名詞で語られる。
「おれたちは深い比喩なのだ」
「京は洛北/きみにとっての夢地獄」
「ねえ ぼくらは/どんな深い闇に親しんでいるのだろう」
「ときにおれたちは/劣悪な家系の鎖をひきずる」
「われわれはすでに/星めぐる領土を失い」
言葉を疑い、読者を疑い、安易な連帯を心地よく拒絶する断固たる二人称。そして叫ぶ。「ついに一語の/凶弾となれ!」と。
清水昶はもちろん全共闘時代に若かりし青春を過ごしている。しかし彼の言葉はそういった政治的闘争には無縁の、もっとも深い人類の内部から発せられた生き魂のような二人称なのである。それを終生貫いた。人類という得体の知れない怪物に向かって自らの退路を断ちながら呼びかけているように思えてならない。そしてその呼びかけに応える対象が不在なのである。しかし、私は全身が震えるような清水昶の呼びかけにいつか、自らの詩作をもって応えることができるかもしれないという希望的観測を捨てたくはない。
思うに彼の詩でいう「私」は「私のなかにいるある化け物」なのであって、その男が徘徊するのを俯瞰している「私」が語る。そこに剥き出しの何者かが正体を晒しているのである。そして詩の中でしかいない私の影を彼は追いかけて私に追いつけない私を憎み、蔑み、叱咤しているのだ。その姿勢を現代はあまりにも欠いているように思える。人はだれしも、胸の奥底に化け物の一部を飼っていて、人類とは、その化け物の総体であって、果てしなく目の前のものを手当たりしだい喰らい続ける、その顕れとして戦争、紛争、テロの仇花が咲く。せめて化け物の一部くらいは引き受けていたい。
「わたしはいつまで/はぐれたわたしを探し続ける?」
私は清水昶の「音楽」という詩を心が干からびるたびに、命の水としてきた。全篇挙げる。
音楽
きみは知っているか
空は虚無のように晴れわたり
もうだれの頭上にも
小さなハリケーンさえ来なくなって久しいが
きみの背後で
歳月ははるか遠くまで透けていて
たとえば竹馬にのる子供のように
想いもかけぬ新鮮な高さが目撃されていたりする
ふいに皿を落としたり
ゆびを切ったりの
すこしずつ死にゆくくらしのはしっこを
ネギのように切り棄てているきみの背後で
きみは知っているか
人が死ぬとき
ぼくは涙をながさない
それはぼくが
楽器のように鳴ることばかり
考えているせいでもあるのだが
故郷を失った音楽には
赤い月がのぼってゆく
世界中に廃墟をひろげて……
それでも
花を捧げ
接吻を投げ
たましいを投影しようとする者がいる
たとえばその人は
めくらの国家の片隅で
燃える手足を持っている
はげしい情動に堪えて小刻みに
真夜中のピアノを弾いてゆく
生きいきとくるしみはねる黒鍵に
やがて大波も来るだろう
ひいてゆく激怒のような波のような波の後には
すみきった悲しみが
塔のように
その人の姿勢を証明するだろう
きみは知っているか
暗然と退路を探がして
頭をふって歩く人でも
ときには
涙を忘れ年齢を忘れ
ボクサーのように後退したり
後退しながらジャブを繰り出し
棄て身の一撃を考えていることを
無差別に
差別されつつ
全身で鳴りはじめるピアニストが
闇で燃える音楽のなかに
一点のひかりを追うかのように
『新しい記憶の果実』より
七、八年前、ある歌人の出版記念会に、私は初めて清水昶と出会った。日本酒をふるえる手でぼたぼた零しながらぐい呑みで一人仰いでいた。私は彼のお住いの吉祥寺までタクシーで送ったことがある。その際、私が家を出て「新しき村」というところで農業をしたこと、病の中で深夜バイトを一〇も二〇も転々とし、幾度も夜逃げ同然に転居を重ね、詩に専念するまでずいぶん遠回りしてきたことを述懐した。そのとき、とつぜん清水昶は私の手を驚くほど強く両手で握りしめ、
「あなたは詩にとって近道をしてきた。嬉しいことだ」と言った。その瞬間だけは酔いどれの目ではなかった。「ここでけっこう、ありがとう」と足取りしっかりに暗闇に消えていったのだ。呆然と見送ったあと、タクシー代を貰うのを忘れてしまい、今では微笑ましい思い出となってしまった。
清水昶は正確に言うと、今でも死んではいない。何人も入るべからずの「われら」「おれたち」の周辺を、私は術なくこれからも歩くだろう。ただ教えられるのは、自分自身を撃たずして、他者の心を撃つ詩など在り得ないという詩の発露の型、武人のような儀礼の精神を愚直なまでに崩さなかった詩人の魂を見るのみである。彼の言葉の意を汲み取るならば、詩人は言葉のテロリストなのである。得体のしれない塊りを撃ち崩す、言葉で世界をひっくり返す、集団のはらわたを抉り、割れた柘榴の赤い血を恐れず、詩人という口に糊することのできない職業を持つことの孤立を引き受ける覚悟を、彼は示してくれるのである。栄光の孤立を。彼の設問は抜き差しならず、いつかまた語る時を持たねばならない。
──清水昶さん、あなたの詩は永遠の命を持っています。金波銀波に打ち寄せる言葉の波打ちぎわを歩くことの喜びを与えてくれたのです。










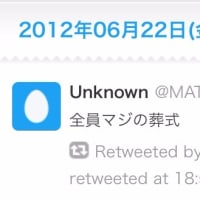
人の持つ二面性に苦しみながら,優しい顔の裏に隠されている冷たい顔に,人に見せならない貌の本性に薄ら寂しくあざける。
だが,汚い面だから,影に隠れているから,そのことが真実(本心)とは限らない。
詩の叫びを聴きながら思うのは,人の持つ両極の心に振り回されながら生きるのが人であるということ。
心が引きちぎれるくらいの思いがあっても,
大声で叫びながら,
涙を流しながら,
それでも,生きて行かなければならないということ。
それが,人の使命だから…。