
青森県西目屋村で、目屋ダム建設のために湖底に沈んだ砂子瀬集落の生活や伝承を聞き取り調査してまとめられた『砂子瀬物語』(森山泰太郎著)は、昭和20年代から30年代にかけての山村の生活を伝える第一級の資料です。
民俗学関係の本を読んでいると何度も引用として出てくるので、なんとなく親近感の湧く書籍でした。
「書かれている半分はうそだ」と書かれた当時から言われていたとは言うものの、初めて通して読んでみるとそれほど違和感は感じず、タブーに踏み込んでいる部分が関係者の不評を買ったとも感じます。
しかし現在から見ればタブーもまた貴重な資料ですが、聞き取り調査をした人の感覚から見て記録すべきものを取捨しているのだから、この調査をした昭和20~30年代の時代の感覚は抜け落ちているものと思われます。
書籍はその内容が書かれた年代を確認して、当時と今の時代感覚に補正をかけることが読書を楽しむコツだと思っています。
小説であっても、書かれた時代を頭に入れておくと、なぜそう考えるのかの理解は深まります。
たとえば戦争であったり恐慌であったり、その前なのか後なのかで登場人物の台詞の意味が分かったり。
科学関係の図書は年代によって内容が変わってきますし、一時期風靡してその後廃れていった考え方の影響もあります。
本に書いてあることがすべて正しいわけではない、必ず時代の影響を受けていると思って読むことは正しい情報に近づくために必要な事だと思います。
年末に片付けていた本の中に古い図鑑があって、小学校へ寄付するために内容を確認していたところ、最新の研究からは大きく内容の違うものが出てきました。
大昔の生き物の図鑑では恐竜の想像図が大変な事になっています。
恐竜の生態の研究は80年代から大きく進展して、それ以前の理解とは全く違ったものになっています。
研究の変遷を見る資料としては使えるものの、小学生に読ませるには少々問題があり、この本は寄付用の図書に入れなかったのですが当時はこれが間違いではなかったのです。
古い本を読む機会が増えて、なんとなくそんな事を考えていました。
 竜脚下目(カミナリ竜)は、その大きさから水生動物と考えられていた。その後の研究から現在は乾燥した森林・草原で生活していたとされている。
竜脚下目(カミナリ竜)は、その大きさから水生動物と考えられていた。その後の研究から現在は乾燥した森林・草原で生活していたとされている。
 主竜類。尾を支えに立ち上がった姿で描かれている。現在では後肢を支柱にして尾と上半身でバランスをとった状態で歩くとされている。尾は地面を引きずらない。
主竜類。尾を支えに立ち上がった姿で描かれている。現在では後肢を支柱にして尾と上半身でバランスをとった状態で歩くとされている。尾は地面を引きずらない。
引用 プログラム式こどもカラー図鑑 5大むかしのいきもの
昭和45年第一刷発行 講談社
民俗学関係の本を読んでいると何度も引用として出てくるので、なんとなく親近感の湧く書籍でした。
「書かれている半分はうそだ」と書かれた当時から言われていたとは言うものの、初めて通して読んでみるとそれほど違和感は感じず、タブーに踏み込んでいる部分が関係者の不評を買ったとも感じます。
しかし現在から見ればタブーもまた貴重な資料ですが、聞き取り調査をした人の感覚から見て記録すべきものを取捨しているのだから、この調査をした昭和20~30年代の時代の感覚は抜け落ちているものと思われます。
書籍はその内容が書かれた年代を確認して、当時と今の時代感覚に補正をかけることが読書を楽しむコツだと思っています。
小説であっても、書かれた時代を頭に入れておくと、なぜそう考えるのかの理解は深まります。
たとえば戦争であったり恐慌であったり、その前なのか後なのかで登場人物の台詞の意味が分かったり。
科学関係の図書は年代によって内容が変わってきますし、一時期風靡してその後廃れていった考え方の影響もあります。
本に書いてあることがすべて正しいわけではない、必ず時代の影響を受けていると思って読むことは正しい情報に近づくために必要な事だと思います。
年末に片付けていた本の中に古い図鑑があって、小学校へ寄付するために内容を確認していたところ、最新の研究からは大きく内容の違うものが出てきました。
大昔の生き物の図鑑では恐竜の想像図が大変な事になっています。
恐竜の生態の研究は80年代から大きく進展して、それ以前の理解とは全く違ったものになっています。
研究の変遷を見る資料としては使えるものの、小学生に読ませるには少々問題があり、この本は寄付用の図書に入れなかったのですが当時はこれが間違いではなかったのです。
古い本を読む機会が増えて、なんとなくそんな事を考えていました。
 竜脚下目(カミナリ竜)は、その大きさから水生動物と考えられていた。その後の研究から現在は乾燥した森林・草原で生活していたとされている。
竜脚下目(カミナリ竜)は、その大きさから水生動物と考えられていた。その後の研究から現在は乾燥した森林・草原で生活していたとされている。 主竜類。尾を支えに立ち上がった姿で描かれている。現在では後肢を支柱にして尾と上半身でバランスをとった状態で歩くとされている。尾は地面を引きずらない。
主竜類。尾を支えに立ち上がった姿で描かれている。現在では後肢を支柱にして尾と上半身でバランスをとった状態で歩くとされている。尾は地面を引きずらない。引用 プログラム式こどもカラー図鑑 5大むかしのいきもの
昭和45年第一刷発行 講談社
















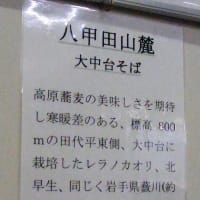



絵を見るだけでわくわくしましたね。
こいつと学研の不思議シリーズが愛読書でした。
学術的には価値がありませんが、人の考え方、歴史を知るためには貴重な資料と思います。
我々はゴジラの様な恐竜を学びましたが、わが子たちは全く違う内容を学んでいる。この違いを知り、理解しない限り果てしないジェネレーションギャップを埋める事は出来ないでしょう。
それに、江戸時代の家計簿が映画のネタに成る事を考えれば、もう少し寝かせるともっといい値がつく可能性も…(笑
今の価格に換算すると20万円でしょうか。
ある意味ステイタスでもあったのでしょうが、子供の教育にはそれなりの対価を受け入れていた時代なんでしょうね。
まだ持ってますけど差し上げましょうか? (笑)