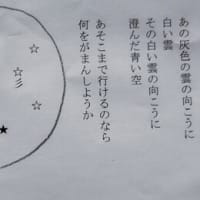時里二郎「「《漂流物ノート》による《仮剥製辞譜》の試み」緒言」(「ロッジア」7、2010年01月31日発行)
時里二郎「「《漂流物ノート》による《仮剥製辞譜》の試み」緒言」は、《わたし》が引き寄せた(わたしに漂ってきた?)ことばの「標本」に、「註解」をつけて詩を書くという試み--そのための「まえがき」のようなものである。ていねいにも、その「まえがき」に「註解」がついている。
時里が愛用する「入れ子構造」である。
「入れ子」によって、ことばは外へ出ていかない。ひたすら内部へと反射しながら、その構造複雑にしていく。そうすると、そこには「ことば」があるのか「構造」があるのか、ちょっとわからなくなる。あるいは、「ことば」そのものが「構造」になってしまうのかもしれない。逆に、「構造」が「ことば」そのものになる、ということもあるかもしれない。「構造」とは「ことば」によって書かれた「まだ存在しないことば」の全体(宇宙)なのである。いや、そうではなくて、ひとつの「ことば」そのもののなかに、いくつもの「ことば」が組み合わさっていて、ひとつにみえるもののなかに「宇宙」(全体)があるということを証明するために、時里は「入れ子」を利用しているのかもしれない。
時里は、「仮剥製」という「ことば」から出発する。剥製が、たとえば鳥なら鳥の形をして木にとまっているのに、「仮剥製」は自然界にみる鳥の形をしていない。死体のまま、紡錘形にととのえられて、「モノ」になっている。
その目撃から、時里は、次のような考えを思いつく。
脚色のない、しかしそのことによって完璧な脚色となっている仮剥製という思想。野鳥の仮剥製を眺めながら、そふ頭をよぎったのは《ことばの仮剥製》というイメージだった。とりわけ詩というのは、鳥の仮剥製のようなかたちで差し出すべきものではないだろうかと。とまり木にとまらせたり、羽を広げてみせたりするのは詩人の仕事ではない。詩のことばは、日常のことばの死をいったん見とどけることにおいて、息を始めるものでなければならない。仮剥製の鳥が、《鳥》とは別の時空に滑り込むように、仮剥製のことばもまた、日常とは別の世界を切り開く。それは詩人にとっても、詩の読み手にとっても、未知の経験を含んでいるに違いない。
「脚色」と呼ばれているのは、鳥を「とまり木にとまらせたり」することである。それは一見自然のとりに見えるけれど、そういうものよりも時里は不自然な形で死んでいるままの鳥の姿に興味を惹かれた。
なぜなら、それはふつう考えられている鳥の時空とは「別の時空に滑り込む」からである。この「別の時空」を時里は「日常とは別の世界」と言いなおしている。脚色されていない剥製、死んだままの剥製は、「日常とは別の世界」を引き寄せる。想像させる。ことばも、脚色(日常的な、流通している使い方)から切り離して「モノ」のように独立させる(脚色の反対語が、独立、孤立である--何にもつながっていない、つながっているとしたら死とのみつながっている)と、そのことばは、「日常とは別の世界」、つまり「別の時空に滑り込む」、「別の時空(次元?)」で動きはじめる。
そういうことが起きるのではないか。
--こういう動き、この運動を、時里は、「完璧」と考えている。
剥製の鳥をとまり木にとまらせるのが「完璧な脚色」であるなら、それをとまり木から遠ざけ死体そのものとして標本化するのは、「完璧な」別の時空へ誘うための出発点である。
時里のキーワードは「入れ子」よりも、「完璧」かもしれない。
時里が求めているのは、ことばの「完璧」なのである。「日常の世界」にしばられていることばは「完璧」ではない。それは「日常」の世界に「流通」しているだけである。それは「日常」の世界から出て行くことはできない。
そういう運動が、なぜ、「完璧」なのか。
これを説明するのは、少し、めんどうくさいが、「詩のことばは、日常のことばの死をいったん見とどけることにおいて、息を始めるものでなければならない。」が、その説明の手がかりになるだろう。死と再生。いったん死んで、息をふきかえす。甦る。それは、別のことばで言いなおせば、復活できる力、再生できることばをもっている、ということでもある。そんな力をくぐり抜けてきたもの--それが「完璧」である。
これはまた別のことばで言いなおせば、そうやって死をくぐり抜け、再生したことばは、何度でも死に直面し、そのつど死を乗り越えて(切り開いて)復活できるということでもあるだろう。
ことば→死→再生→死→再生→死→再生→→→→完璧なことば。
そんなふうに「図式」にしてみると、あらら、不思議。死と再生が「入れ子」になっている。「完璧なことば」は、ことばの死と再生という運動(ことばの動きの構造)が「入れ子」になっている。
時里にとって「入れ子」とは「完璧」と同義である。時里が「入れ子」の詩を書くのは、それが「完璧」をめざした運動だからである。
時里二郎「「《漂流物ノート》による《仮剥製辞譜》の試み」緒言」は、《わたし》が引き寄せた(わたしに漂ってきた?)ことばの「標本」に、「註解」をつけて詩を書くという試み--そのための「まえがき」のようなものである。ていねいにも、その「まえがき」に「註解」がついている。
時里が愛用する「入れ子構造」である。
「入れ子」によって、ことばは外へ出ていかない。ひたすら内部へと反射しながら、その構造複雑にしていく。そうすると、そこには「ことば」があるのか「構造」があるのか、ちょっとわからなくなる。あるいは、「ことば」そのものが「構造」になってしまうのかもしれない。逆に、「構造」が「ことば」そのものになる、ということもあるかもしれない。「構造」とは「ことば」によって書かれた「まだ存在しないことば」の全体(宇宙)なのである。いや、そうではなくて、ひとつの「ことば」そのもののなかに、いくつもの「ことば」が組み合わさっていて、ひとつにみえるもののなかに「宇宙」(全体)があるということを証明するために、時里は「入れ子」を利用しているのかもしれない。
時里は、「仮剥製」という「ことば」から出発する。剥製が、たとえば鳥なら鳥の形をして木にとまっているのに、「仮剥製」は自然界にみる鳥の形をしていない。死体のまま、紡錘形にととのえられて、「モノ」になっている。
その目撃から、時里は、次のような考えを思いつく。
脚色のない、しかしそのことによって完璧な脚色となっている仮剥製という思想。野鳥の仮剥製を眺めながら、そふ頭をよぎったのは《ことばの仮剥製》というイメージだった。とりわけ詩というのは、鳥の仮剥製のようなかたちで差し出すべきものではないだろうかと。とまり木にとまらせたり、羽を広げてみせたりするのは詩人の仕事ではない。詩のことばは、日常のことばの死をいったん見とどけることにおいて、息を始めるものでなければならない。仮剥製の鳥が、《鳥》とは別の時空に滑り込むように、仮剥製のことばもまた、日常とは別の世界を切り開く。それは詩人にとっても、詩の読み手にとっても、未知の経験を含んでいるに違いない。
「脚色」と呼ばれているのは、鳥を「とまり木にとまらせたり」することである。それは一見自然のとりに見えるけれど、そういうものよりも時里は不自然な形で死んでいるままの鳥の姿に興味を惹かれた。
なぜなら、それはふつう考えられている鳥の時空とは「別の時空に滑り込む」からである。この「別の時空」を時里は「日常とは別の世界」と言いなおしている。脚色されていない剥製、死んだままの剥製は、「日常とは別の世界」を引き寄せる。想像させる。ことばも、脚色(日常的な、流通している使い方)から切り離して「モノ」のように独立させる(脚色の反対語が、独立、孤立である--何にもつながっていない、つながっているとしたら死とのみつながっている)と、そのことばは、「日常とは別の世界」、つまり「別の時空に滑り込む」、「別の時空(次元?)」で動きはじめる。
そういうことが起きるのではないか。
--こういう動き、この運動を、時里は、「完璧」と考えている。
剥製の鳥をとまり木にとまらせるのが「完璧な脚色」であるなら、それをとまり木から遠ざけ死体そのものとして標本化するのは、「完璧な」別の時空へ誘うための出発点である。
時里のキーワードは「入れ子」よりも、「完璧」かもしれない。
時里が求めているのは、ことばの「完璧」なのである。「日常の世界」にしばられていることばは「完璧」ではない。それは「日常」の世界に「流通」しているだけである。それは「日常」の世界から出て行くことはできない。
そういう運動が、なぜ、「完璧」なのか。
これを説明するのは、少し、めんどうくさいが、「詩のことばは、日常のことばの死をいったん見とどけることにおいて、息を始めるものでなければならない。」が、その説明の手がかりになるだろう。死と再生。いったん死んで、息をふきかえす。甦る。それは、別のことばで言いなおせば、復活できる力、再生できることばをもっている、ということでもある。そんな力をくぐり抜けてきたもの--それが「完璧」である。
これはまた別のことばで言いなおせば、そうやって死をくぐり抜け、再生したことばは、何度でも死に直面し、そのつど死を乗り越えて(切り開いて)復活できるということでもあるだろう。
ことば→死→再生→死→再生→死→再生→→→→完璧なことば。
そんなふうに「図式」にしてみると、あらら、不思議。死と再生が「入れ子」になっている。「完璧なことば」は、ことばの死と再生という運動(ことばの動きの構造)が「入れ子」になっている。
時里にとって「入れ子」とは「完璧」と同義である。時里が「入れ子」の詩を書くのは、それが「完璧」をめざした運動だからである。
| 翅の伝記時里 二郎書肆山田このアイテムの詳細を見る |