純子ちゃんの出てくる「不適切にもほどがある」を観ながら、母校の校歌を思い出していた。
♪ 男の命強さなり 女の道は優しさよ 力を合わせ この郷(さと)に文化の華を咲かせなむ
父の出た旧制中学が戦後男女共学になった時に生まれたこの校歌を、その頃違和感無しで歌っていた私は、昭和の人である。男女の役割固定を促すこの歌詞は明らかに不適切である。この校歌3番は平成の時代に消えた。
しかし、学校のHPを開けて、驚いた。昭和が続いていた。平成の制服リニューアルブームは、田舎には届いてなかった。令和の制服は昭和と全く同じセーラー服だった。当然男子も黒い学生服のままだ。(さすがに学帽は無くなっていた)
セーラー服のスカートのプリーツ、今は形状記憶になっているのだろうか。私は裁縫好きで過保護な母が毎晩しつけ糸をしたのを布団の下で寝押していた。修学旅行の時は、どうしよう、しつけ糸持って行こうか、と悩んだのは覚えているが、実際どうしたのかは覚えていない。夏服もジャンパースカートのままである。50年前に比べたら、猛暑日も増えているのに、大丈夫?

~昨年入院中に旧友が送ってくれた学校近くの風景。とても癒された。
ついでに中学校、小学校はとホームページを覗いてみた。幸いなことに今も同じ場所に存在していた。
小学校校庭の欅の木は、更に大きく枝を伸ばして百年大木になっていた。この木の木陰で誰かを待っている夢を見たことがある。
そういえば、毎年この季節、入浴中に、天から舞い降りてくるフレーズがある。
♪うら~ら~かに~春のひかり~がふってくる~
そしてこの後10分は続くオペレッタ🎶
♩(全員)うららかに〜春の光が降ってくる 良い日よ〜良い日よ〜良い日今日は
桜よ薫れ鳥も歌え〜 良い日よ 良い日よ 良い日今日は
(123年)仲良く遊んで下さった6年生のお兄さん 優しく世話して下さった6年生のお姉さん
おめでとうおめでとう ご卒業おめでとう
(卒業生)ありがとう君たち ありがとう
(45年生)良い日この日あなた方は この学校をご卒業
雨の日もまた風の日も 通い励んだ6年の 学業終えて 今巣立つ
おめでとう おめでとう おめでとう
(卒業生)ありがとう君たち ありがとう
(45年生)朝に夕にあなた方と 遊び学んだ年月よ
運動場にあの窓に数々残る思い出が まぶたに胸に 今浮かぶ
さよなら さよなら さよおなら (←練習時ここだけ大声で歌う男子がいた)
(卒業生)さようなら君たち さようなら
(先生)君たちよ 光は空に~満ちている 翼をそろえて胸張って 翔け巣立つ~君たちよ
たとえ嵐が吹こうとも はばたけ翔け 行く~手には 明るい未来が開けてる
君たちよ 先生はいつも~見つめてる はぐくみ育てた君たちの 駆け行く姿を 君たちよ
たとえ荒波高くとも 翔け翔け 行く手には明るい希望が開けてる 君たちよ
(卒業生)ありがとう先生 ありがとう
(卒業生)育て賢く丈夫にと 今日のこの日を待っていた 父さん母さん ありがとう
今度はいよいよ中学生 しっかりやります 励みます 父さん母さん ありがとう
(全員)美しく 春の光が降ってくる 良い日よ 良い日よ 良い日今日は〜
良い日よ〜良い日よ〜良い日今日は~
起立着席のザザーっという音まで思い出した。天井の高い講堂は寒かった。
6年間ただ聞くだけだった先生の歌に憧れ、先生になれば歌えると思っていたのに、高校卒業以来、この「卒業式の歌」(小林純一作詞、西崎嘉一郎作曲)を歌ったことのある人に出会ったことがないのである。
春の光は、うら~ら~か~に~♪ 降ってくるのにな~
♪ 男の命強さなり 女の道は優しさよ 力を合わせ この郷(さと)に文化の華を咲かせなむ
父の出た旧制中学が戦後男女共学になった時に生まれたこの校歌を、その頃違和感無しで歌っていた私は、昭和の人である。男女の役割固定を促すこの歌詞は明らかに不適切である。この校歌3番は平成の時代に消えた。
しかし、学校のHPを開けて、驚いた。昭和が続いていた。平成の制服リニューアルブームは、田舎には届いてなかった。令和の制服は昭和と全く同じセーラー服だった。当然男子も黒い学生服のままだ。(さすがに学帽は無くなっていた)
セーラー服のスカートのプリーツ、今は形状記憶になっているのだろうか。私は裁縫好きで過保護な母が毎晩しつけ糸をしたのを布団の下で寝押していた。修学旅行の時は、どうしよう、しつけ糸持って行こうか、と悩んだのは覚えているが、実際どうしたのかは覚えていない。夏服もジャンパースカートのままである。50年前に比べたら、猛暑日も増えているのに、大丈夫?

~昨年入院中に旧友が送ってくれた学校近くの風景。とても癒された。
ついでに中学校、小学校はとホームページを覗いてみた。幸いなことに今も同じ場所に存在していた。
小学校校庭の欅の木は、更に大きく枝を伸ばして百年大木になっていた。この木の木陰で誰かを待っている夢を見たことがある。
そういえば、毎年この季節、入浴中に、天から舞い降りてくるフレーズがある。
♪うら~ら~かに~春のひかり~がふってくる~
そしてこの後10分は続くオペレッタ🎶
♩(全員)うららかに〜春の光が降ってくる 良い日よ〜良い日よ〜良い日今日は
桜よ薫れ鳥も歌え〜 良い日よ 良い日よ 良い日今日は
(123年)仲良く遊んで下さった6年生のお兄さん 優しく世話して下さった6年生のお姉さん
おめでとうおめでとう ご卒業おめでとう
(卒業生)ありがとう君たち ありがとう
(45年生)良い日この日あなた方は この学校をご卒業
雨の日もまた風の日も 通い励んだ6年の 学業終えて 今巣立つ
おめでとう おめでとう おめでとう
(卒業生)ありがとう君たち ありがとう
(45年生)朝に夕にあなた方と 遊び学んだ年月よ
運動場にあの窓に数々残る思い出が まぶたに胸に 今浮かぶ
さよなら さよなら さよおなら (←練習時ここだけ大声で歌う男子がいた)
(卒業生)さようなら君たち さようなら
(先生)君たちよ 光は空に~満ちている 翼をそろえて胸張って 翔け巣立つ~君たちよ
たとえ嵐が吹こうとも はばたけ翔け 行く~手には 明るい未来が開けてる
君たちよ 先生はいつも~見つめてる はぐくみ育てた君たちの 駆け行く姿を 君たちよ
たとえ荒波高くとも 翔け翔け 行く手には明るい希望が開けてる 君たちよ
(卒業生)ありがとう先生 ありがとう
(卒業生)育て賢く丈夫にと 今日のこの日を待っていた 父さん母さん ありがとう
今度はいよいよ中学生 しっかりやります 励みます 父さん母さん ありがとう
(全員)美しく 春の光が降ってくる 良い日よ 良い日よ 良い日今日は〜
良い日よ〜良い日よ〜良い日今日は~
起立着席のザザーっという音まで思い出した。天井の高い講堂は寒かった。
6年間ただ聞くだけだった先生の歌に憧れ、先生になれば歌えると思っていたのに、高校卒業以来、この「卒業式の歌」(小林純一作詞、西崎嘉一郎作曲)を歌ったことのある人に出会ったことがないのである。
春の光は、うら~ら~か~に~♪ 降ってくるのにな~



















 (~どこにあるでしょう?)
(~どこにあるでしょう?)



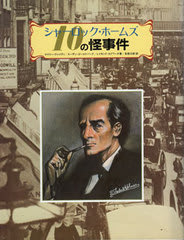
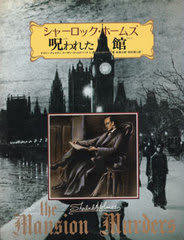

 オレンジルーム、前売2000円。
オレンジルーム、前売2000円。 エイトスタジオ、当日4000円
エイトスタジオ、当日4000円 「八月の太陽を」(作:乙骨淑子、理論社1966刊)
「八月の太陽を」(作:乙骨淑子、理論社1966刊)





 (~写真は地中美術館パンフレットより)
(~写真は地中美術館パンフレットより)

 井上ひさし作、蜷川幸雄演出の舞台「ムサシ」
井上ひさし作、蜷川幸雄演出の舞台「ムサシ」













