先日の芦屋市立美術博物館の「芦屋の画塾 芦屋のアトリエ」展で、谷崎潤一郎(42才)が小出楢重(41才)に宛てた書簡が出品されていた。1928年(昭和3)年11月4日付
「…新聞の方は御大典記事が済んだ後、十六日から載るそうです。
それで急ぐにも及びませんが、兎に角三回だけ御届けいたします。
…此の中の男の歳は三十七八歳、女の方は二十八九歳に願います。
室内装飾を出す必要があれば多少文化住宅式ハイカラの方がいひと思ひ升
しかし必ずしも拘泥されるには及びません。
貴下の感じで結構です。」
こうして、小出楢重の挿絵とともに谷崎の「蓼喰う虫」という新聞連載小説が生まれた。
岩波文庫「蓼喰う虫」には、この挿絵がそのまま載っている。


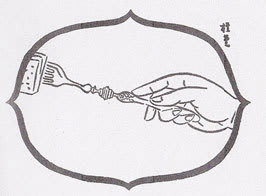

離婚寸前の夫婦の有り様が視線によく現れている。挿絵には家族が飼っているリンディというグレーハウンド犬や、神戸の居留地の金髪娼婦なども登場して、昭和初期阪神間モダニズムの様子が伺える。当時、田舎に住むこの新聞の読者は、小出の挿絵でイメージをふくらましたことだろう。
挿絵目当てに開いた小説だけど、読んでいるうちに、「摘み草」という新鮮な言葉に出会った。
主人公要が、人形浄瑠璃にはまっている妻の父と、父の世話をする若い女お久と一緒に、淡路島の芝居小屋を訪ねる旅をしたシーンである。
「ほんまに今日はええ天気どすな。」
と、要と一緒にそろりそろり先へ行きながら、お久は晴れわたった空を仰いで、
「こういう日には摘み草がしとうて、……」
と、不平らしく口のうちで言った。
「全く、芝居よりは摘み草に持って来いという日だ。」
「どこぞここら辺に蕨やつくしのはえてるとこおすやろか。」
今、兵庫県立美術館のコレクション展「いのちの色」に、小坂象堂(1870〜1899)の「草摘み」(1897年作)が出ている。夭折した画家27才の作品。

~「兵庫県立美術館アートランブルvol17」より
「あっ!」草を摘む少女の手が止まった。
「あの人だわ。」視線の先には、少女の心を摘んだ誰かが…。
地面から立ち上る青い草の香り。なんだか胸いっぱいになる春の野辺。
116年前の日本の春、野辺での出来事。
放射能という言葉さえなかった時代の幸せ感。
(キューリー夫人が放射能を名付けたのが1898年)
「今日は摘み草がしたいなぁ」とそんなことを、暢気にいえる時代はもう終わったのかもしれない。3・11後、もはや画家はこんな幸せな風景は描けない。大気には放射能に加え、PM2・5まで加わった。
それでも、それでも、ぽかぽか晴れた春の陽気に誘われて、少女の心はつぶやく。
「こんな日は、摘み草がしたいなぁ。」
あの地でもいつか摘み草 祈る2年目
「…新聞の方は御大典記事が済んだ後、十六日から載るそうです。
それで急ぐにも及びませんが、兎に角三回だけ御届けいたします。
…此の中の男の歳は三十七八歳、女の方は二十八九歳に願います。
室内装飾を出す必要があれば多少文化住宅式ハイカラの方がいひと思ひ升
しかし必ずしも拘泥されるには及びません。
貴下の感じで結構です。」
こうして、小出楢重の挿絵とともに谷崎の「蓼喰う虫」という新聞連載小説が生まれた。
岩波文庫「蓼喰う虫」には、この挿絵がそのまま載っている。


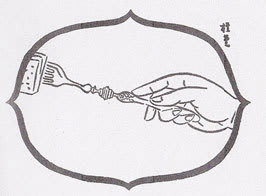

離婚寸前の夫婦の有り様が視線によく現れている。挿絵には家族が飼っているリンディというグレーハウンド犬や、神戸の居留地の金髪娼婦なども登場して、昭和初期阪神間モダニズムの様子が伺える。当時、田舎に住むこの新聞の読者は、小出の挿絵でイメージをふくらましたことだろう。
挿絵目当てに開いた小説だけど、読んでいるうちに、「摘み草」という新鮮な言葉に出会った。
主人公要が、人形浄瑠璃にはまっている妻の父と、父の世話をする若い女お久と一緒に、淡路島の芝居小屋を訪ねる旅をしたシーンである。
「ほんまに今日はええ天気どすな。」
と、要と一緒にそろりそろり先へ行きながら、お久は晴れわたった空を仰いで、
「こういう日には摘み草がしとうて、……」
と、不平らしく口のうちで言った。
「全く、芝居よりは摘み草に持って来いという日だ。」
「どこぞここら辺に蕨やつくしのはえてるとこおすやろか。」
今、兵庫県立美術館のコレクション展「いのちの色」に、小坂象堂(1870〜1899)の「草摘み」(1897年作)が出ている。夭折した画家27才の作品。

~「兵庫県立美術館アートランブルvol17」より
「あっ!」草を摘む少女の手が止まった。
「あの人だわ。」視線の先には、少女の心を摘んだ誰かが…。
地面から立ち上る青い草の香り。なんだか胸いっぱいになる春の野辺。
116年前の日本の春、野辺での出来事。
放射能という言葉さえなかった時代の幸せ感。
(キューリー夫人が放射能を名付けたのが1898年)
「今日は摘み草がしたいなぁ」とそんなことを、暢気にいえる時代はもう終わったのかもしれない。3・11後、もはや画家はこんな幸せな風景は描けない。大気には放射能に加え、PM2・5まで加わった。
それでも、それでも、ぽかぽか晴れた春の陽気に誘われて、少女の心はつぶやく。
「こんな日は、摘み草がしたいなぁ。」
あの地でもいつか摘み草 祈る2年目

















