この冬の芦屋市立美術博物館の「戦後のボーダレス~前衛陶芸の貌」展。
戦後、関西の陶芸界にも新しい流れが起こった。1947年に四耕会、1948年に走泥社結成、若者たちは、新しい時代の新しい焼き物を作った。クレイ・ワークの出発。
まず、第一室には「われわれが活けられないような花器を」と前衛華道家に求められた花器が並ぶ。
器(うつわ)とは、「ウツ」なる空洞なるものがその中に何かの到来を待ちうけているものらしい。オブジェのようだが、そこに花が加わって完成する世界。どんな花を生けようかと、想像しながら見ていく。体用留は考えない。
三浦省吾の「作品」1951は、動きのある男児のように可愛い。まるで映画「スターウォーズ~フォースの覚醒」に出てきた、BB8。
八木一夫の「春の海」1947はお正月に飾りたい。花咲き、蝶が飛んでる季節、春の海では、まあるい幸せそうなフグが泳いでいる。


三浦省吾「作品」 八木一夫「春の海」 ~写真は展覧会図録より
持ち帰りに選んだこの2点には、お花は必要ないかな。それでも丸く空いた空間は、何かを待っているみたいなので、私の気配でもしのばせてみよう。
第二室はいよいよオブジェ。
林康夫の1948の作品には「雲」という題がついているけど、私にはおでことおでこをこっつんこしている母子像に見える。真ん中の空間の形が美しい。バレンタインチョコの形にしてもいいわ。
重量感あふれる熊倉順吉の「作品」1956は、洞窟の風景みたい。コップのフチコさんになって坐りたくなる。どこにしようかな。
陶製ではなく、鉄製のオブジェも出ている。現代美術懇談会つながりで登場した、堀内正和の「うらがえる円筒a」1960。確かに途中で裏返っているのに、ある角度から見ると上から下まで一直線を辿れる。本当に格好いい作品。



林康夫「雲」 熊倉順吉「作品」 堀内正和「うらがえる円筒a」
そして八木一夫の「ザムザ氏の散歩」1954である。

このザムザ氏は、おそらく回転しながら歩むのだろう。次々に小さな足を地につけて、自分がまわりながら進むのだ。(そういえば、SMAPがデビューしたての頃、新春かくし芸大会で、グルグル回る鉄の環(ラート)を全身で回して鮮やかに技を決めていた。ドイツ生まれのスポーツを彼ら一生懸命練習したんだろうなぁ。あれから24年)
ザムザ氏とは、フランツ・カフカ(1883~1924)が1912年に書いた小説「変身」の主人公である。二度と読みたくないと思った小説である。
~ある朝、グレゴール・ザムザが不安な夢からふと覚めてみると、ベッドのなかで自分の姿が一匹の、
とてつもない大きな毒虫に変わってしまっているのに気がついた。(訳:中井正文、角川書店1968)
~ある朝、グレーゴル・ザムザが不安な夢から醒めると、ベッドのなかで、
ものすごい虫に変わっていた。(訳:城山良彦、集英社1989)
~ある朝、グレーゴル・ザムザが不安な夢から目を覚ましたところ、ベッドのなかで、自分が
途方もない虫に変わっているのに気がついた。(訳:池内紀、白水社2001)
~ある朝、不安な夢から目を覚ますと、グレーゴル・ザムザは、自分がベッドのなかで
馬鹿でかい虫に変わっているのに気がついた。(訳:丘沢静也、光文社2007)
カフカは、挿絵として虫の姿を決して載せないように指示した。遠方の姿でさえ駄目だとした。虫の姿形を読者の想像にゆだねたのだ。そのことが、この短編を一度読んだら忘れられない感触をのこす作品にしている。私は巨大なゴキブリのような形の単純なイメージしかなかった。
同じ短編を読んで、この虫の形をつくり出した八木一夫の想像力に驚く。(正直、ザムザに「氏」をつけたところから驚いている。小説では氏がつくのは、父親の方だ。まさか?)
壊れそうな足で立っている。実際に何本かは欠けている。それさえ小説の中味と連動した八木の創作の一部かもしれない。いやきっとそうだ。リンゴを投げつけられてボロボロになった身体だ。長い時間見つめていると、表面の無数の穴からは嫌な虫の匂いも漂ってきそうな質感である。でも、カフカの作品にはない、ユーモラスな要素がこの作品にはある。歩き方だ。
このザムザ氏は、どんな風に歩くのだろうと、作品を見ながら考えているうちに、気がついた。回転するのだ。ゆっくりと次々に横の足を地につけながら。足の方向がてんでバラバラに見えるけど、全身でリズムとらないと、ザムザ氏は歩けない。
あー、カフカに見てほしい。
「春の海」のような作品を作った同じ人が、「ザムザ氏の散歩」を作った。
八木一夫(1918-1979)自身も、この作品によって、伝統ある京都五条坂の陶芸家から、オブジェ焼きという新しい造形作家に「変身」したのだ。









 ジャコメッティ「石碑Ⅰ」1958
ジャコメッティ「石碑Ⅰ」1958
 クロチェッティ「マグダラのマリア」1955
クロチェッティ「マグダラのマリア」1955




 ~展覧会図録より
~展覧会図録より








 ~現代美術二等兵「KoiのRock'n Roller」
~現代美術二等兵「KoiのRock'n Roller」 ~伊藤彩「こんなんどうですか」
~伊藤彩「こんなんどうですか」



 ~楢木野淑子「あるべきような」
~楢木野淑子「あるべきような」

 三沢厚彦「Animal2016-03-B1」
三沢厚彦「Animal2016-03-B1」


 岡本光博「未確認墜落物体」
岡本光博「未確認墜落物体」 靴郎堂本店「SHOE LODGE」
靴郎堂本店「SHOE LODGE」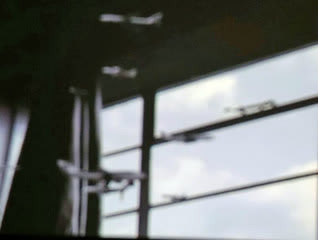 さわひらき「dwelling」
さわひらき「dwelling」


 山本桂輔「夢の山(眠る私)」
山本桂輔「夢の山(眠る私)」 君平「プランクトン」
君平「プランクトン」
 君平「ヒゴタイ」
君平「ヒゴタイ」

 近藤正嗣「晴天のアメ」
近藤正嗣「晴天のアメ」
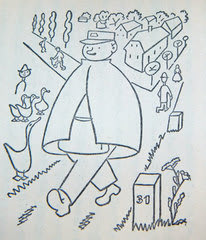


 『子どものカラー・オペラ』
『子どものカラー・オペラ』 『赤い雨』
『赤い雨』










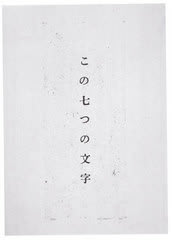 (高松次郎「日本語の文字」1970)
(高松次郎「日本語の文字」1970)
 ~高松次郎「女の影」のクリアファイル
~高松次郎「女の影」のクリアファイル