廃ペット:価格暴落のリサイクル混乱、市場原理のツケ

廃ペットの価格暴落は、リサイクルの一端を事実上、中国に頼ってきた日本に打撃を与えた。国内では、価格が高騰した際、廃ペットが中国に流れたため経営難に陥ったリサイクル業者も出ており、廃ペットのリサイクルは見直しを迫られている。業者らは「海外をあてにしたリサイクルを反省し、国内での市場拡大を目指すべきだ」と訴える。
「日本容器包装リサイクル協会」(容リ協)は処理業者を国内に限っている。しかし容リ協が扱う廃ペットは全体の半分以下にとどまり、かなりの量が独自処理で中国に流れたとみられる。
リサイクルの仕組みは「容器包装リサイクル法」に基づいている。消費者には分別、市町村には回収、製造者には再商品化を義務付けているが、収集した廃ペットをどう処理するかは市町村の判断に任され、容リ協を通す義務はない。
市町村が独自処理を選ぶ背景には財政難がある。「少しでも高く売れるところに売る」という市場原理で動いた結果、今回の混乱が起きた。
価格暴落という“教訓”から、来年度は容リ協を通して処理する市町村が97年度の導入以来最高になる見通しだ。しかし、廃ペットの需要が世界的に冷え込んでいる現状では、再商品化しても割高になるため、リサイクル業者が大量の廃ペットを抱える事態を招く恐れがある。【足立旬子】
毎日新聞 2009年2月8日 2時30分
ソース元:http://mainichi.jp/life/ecology/news/20090208k0000m040139000c.html?inb=yt
まあ予測できた事態で、以前に書いた記事:
ペットボトルのリサイクルは環境にやさしいか - 生産量・再商品化見込までの流れ -
を見てもらうと、生産量に対する各機関発表の再利用率は変わってないもしくは低下してる、というか、まあゴミは増えているという表現が適切でしょうかね。
各市町村のWEBサイト、GoogleEarth、投棄現場なんか見てみると、ベールの束がポーンと放置していたりするわけで、そこに市町村が自腹で監視カメラとか、監視体制とかで税金を使っちゃったり、もういたちごっこでしょうね。
>業者らは「海外をあてにしたリサイクルを反省し、国内での市場拡大を目指すべきだ」と訴える。
そりゃあ、業者さんとしてはリスクを犯して海外輸出(心象面も含む)より、政府の予算投入による特定産業として、安定した経営したいですよね。
真面目にやられてる多くの業者さんなんかは、必死でやっておられると思います。
でも、やっぱりそこには“環境配慮”という思想はスッポリ抜けていたり…
基本的に容リ法ってのは、容器を使用した業者の商品流通を活性化させるコトに重点が置かれているわけで、環境問題ではなくて特定事業者の経済対策だったりするんだろうなあ。
リユース瓶は、確かにコスト面、回収の労力、エネルギー面でもPETリサイクルに押されてしまってるかもしれないですが、長期的な目線で考えると良いと思うんですけどね。
むかーしは、三河屋のさぶちゃんなんかが“ふつう”に回収してくれてたりしたわけで。
まあ、地域間コミュニケーションってのがあったからこそでしょうけど。
どちらにしても“容リ協を通す義務はない”改正容リ法っつう中途半端な制度で、容リ協を通した流通が増えたところで、不法投棄問題も、海外輸出問題も、地球環境問題も、地球温暖化問題も・・・なーんも解決してないけど、 容リ協っていう財団法人には商工会議所から異動してきた方々が働いており、給料が支払われ、何をしてるって、入札の仕切と統計資料作成ですからね。 <言い過ぎました>
日本商工会議所は、特定認可法人としてスタートし、2002年民間法人化。
ちなみに認可法人の法律上の定義はなく、特別の法律に基づいて数を限定して作られる法人だそうです。
もうさー、食料品・飲料品はマイ器持参で全て量り売り。
とか、ビール業界の缶製品製造禁止令とか出しちゃえば。
ま、いろんなこわーいトコから圧力かかるんでしょうけど。
UNIQLOが自社でPET回収から再生繊維製品までやっちゃいマス。
とかやりそうなんだけどなー(独自の再生工場と契約しちゃったりなんかして)
まあ、せめて自動販売機で堂々とPETボトル商品を売ってる業者さんは、自販機の横にPETキャップ回収ボックスくらいは設置して下さい。
ポリオワクチンで助かる命もあるかもしれませんが、ポリオワクチンを本当に欲しているヒトには渡らないシステムであったり、本当はもっと根本的な支援が必要だったり、そういう説明もなく「キャップ何個で助かる命」というキャッチコピーより、出来れば子ども達に現地の映像を見てもらうとか、ネット繋げるんなら生の現地レポートをするとか、肌で感じるコトができるといいなあ、と個人的には思います。
(今のシステムを構築する(再資源用PETボトルの取引)だけで102兆円使ってますが・・・またもや連呼)。
読んで下さった方、ありがとうございます。













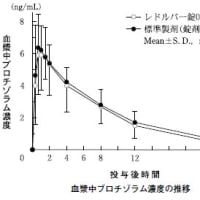

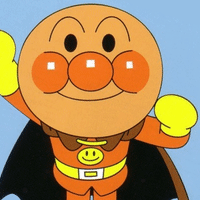
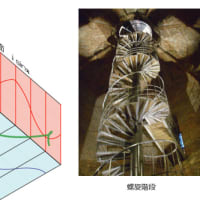

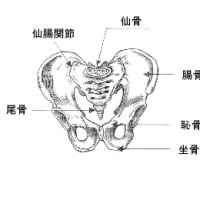
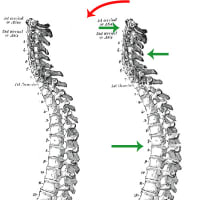
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます