日本の予算の流れ方は、下図を見て頂くとなんとなくお解り頂けるかと思います。

経済産業省によって今後5年間の事業計画における各計画値が、提示されます(○-黒波線「再商品化見込量」)。
それに沿って環境省が年度の収集量(回収量)を決め、自治体と事業所の合計が経済産業省の計画値に近づくように(厳密には事業所回収量を如何に目標値に向けるかを思案している)折衝しているのでしょう。
再商品化能力として提示されているので、その能力分のゴミ(PETボトル)が必要となる。
各市町村は、経済産業省の「分別収集量計画(赤○-赤実線)」が目標値となり、その数値に概ね近似するように収集計画を立てます。
各市町村が収集したPETボトルは、特定団体、特定企業へほぼ引き渡すことで回収-再利用率100%になるように設定。
以前は改正容器包装リサイクル法における特定財団である『財団法人 日本容器包装リサイクル協会』へ殆どを有償引き渡し(現物は各自治体で保管し、協会の入札制度によって落札した企業へ直接引き渡す)。残りは焼却処分。
国の法令(改正容器包装リサイクル法[2006])に沿って、特定財団である『財団法人 日本容器包装リサイクル協会』の入札制度で落札した業者にベールという束状にした形で有償引き渡し(現物は各自治体で保管し、協会の入札制度によって落札した企業へ直接引き渡す)。残りは焼却処分。。
2005年からは中国の樹脂需要も相まって、樹脂再原料価格(資源化前のPETボトル)が大幅に下落し、財団法人経由の業者引き渡しより、リサイクル業者(プラスα輸出業者)との独自ルート開拓のほうが高価格(もともと入札でお金を払うところが、買取してくれるのだから当然のことである)であり、中国に流出する可能性はちょっとどこかに置いておいて、一応特定業者に引き渡し。
これで自治体の目標達成率は100%(黄緑棒グラフ-水色棒グラフ)。
財団は何をやっているかというと、入札制度の取り纏め。
基本的に○○商工会議所から転属になった方などが業務にあたられているので、名目的には「非営利」。
Yahoo!辞書「財団法人」
一定の目的のために提供された財産を運用するため、その財産を基礎として設立される法人。現行法上、公益を目的とする公益法人に限って認められる。
そこでも取引量全てをさばくことが出来ず、2008年度集計で25%は入札による特定業者の手に渡らず処分。
結果的にPETボトル販売量の約20%を特定業者に引き渡す、という作業が行われているというのが、『PETボトルリサイクル』だ思います。
回収した量は39.5万トン。
財団が特定業者に引き渡した量が11.8万トン。
回収量の約1/3。
確かに一般庶民が頑張り、自治体がPETボトル用の仮置き場を確保し、分別収集の手間を惜しまず努力して、PETボトル販売量の67%は回収できました。
素晴らしい事だと思います。
PETボトルからPETボトルは残念ながら生まれることは日本ではないでしょう。
以前に帝人ファイバーさんが、山口でなさっておられたと記憶していますが、採算が合わず2005年に工場を畳んだかと。
PETはラベルにも記載されているとおり、PETボトル識別表示マーク「1」なので(1以外を見たことありません)、マテリアルリサイクルにはかなりの熱量を必要とします。
ケミカルリサイクルもそれなりに熱量が必要ですね。
ペットボトルを包装に使用している企業の環境貢献活動を見てみますと、使用原料の軽量化。
確かに原料を少なくすることは、それだけ資源を使わなくてすむということですが、それは企業としての利潤に繋がることですから当然やるでしょう。
「我がコ○・コーラ社は、自社製品からでたゴミを全て収集します」
などどいう声は挙がりませんものね。
使い勝手が良くなり、益々売れるPETボトル。
Reuseの点では、水筒代わりに使っています。
Recycleの点では、分別しています。
それではいつまで経っても変わらない。
どうすればいいか?
それはまた別の機会にでも書いてみます。
きちんと処分先まで公表している自治体もあり、努力が報われるシステムになることを願います。
埼玉県和光市さんWEBサイトより
「今まで10年あまりの出血でケミカルリサイクルシステムが機能し始めた」という点は評価できる所だと思います(再資源用PETボトルの取引だけで102兆円使ってますが・・・)。













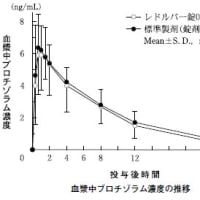

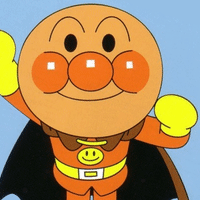
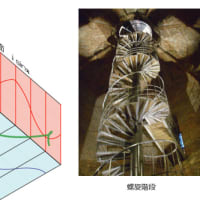

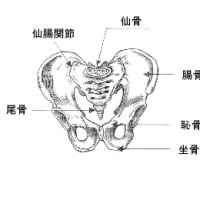
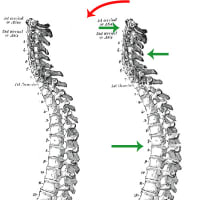
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます