たまにこういうの入れますので、適当に流して下さい。
土というのはうまくできている。
地表に露出した岩盤が、風により、雨により、あらゆる力により岩となり、水に流され石となり、砂となり、粘土となり、時には河川が氾濫して、後背湿地に堆積する。
火山から噴出した火山灰も、あるものはそのまま地表に降灰し、あるところでは削剥され、またあるところでは別の土が堆積し、その姿を留める。
自然に形成された土には、その環境に応じた土圧、含水量、間隙比が存在し、可塑性に富む比較的柔軟な状態だったりする。
そこに人為(artificial)というものが入ってしまうと、絶妙な形で保たれていた調和が乱れるコトがある。
一般的によく知られているもので、関東平野全域に分布する関東ローム層は、武蔵野面、立川面などの分類を厳密に問わず、木造2階建て住宅程度の構造物の基礎地盤としては十分な強度を持っていたりする。
構造物を建てる時、地べたに箱物を直接置くわけにはいかない。
構造物の自重を分散させる剛体(基礎)が必要となってくる。
基礎を固める前に地面を削剥整地することになるわけだが、実質的に現場でやる作業としては、ユンボ(バックホー)で自然地盤をこねくり回すことになる。
地下水位が低く、作業中晴天の日が続くならばそれに超したことはないが、含水比が増加した上にこね返しされた粘性土というものは著しく強度が低下する。
これは、その後ローラーやランマーなどで転圧を施そうが、元の強度にははるかに及ばないまったくの別物となってしまっている。
とある業界ではこのことを“鋭敏比”と呼んでいる。
自然地盤における強度と、コネ返しにより低下した強度の比のことであり、
慣用句表現としては“覆水盆に返らず”に意味合いは近い。
現場作業のアルバイトのオニイチャンとして自分が入ったとする。
どうやらそこは盛土造成した宅地造成地らしい。
これから住宅メーカーが一戸建て住宅を建設し、マイホームを夢見る家族が生活をおくる場になるのだろう。
基礎工事期間は都合上2日。その間に捨てコン打って防水シート、墨だしまでするそうだ。養生期間などあったものではない。
アルバイトのオニイチャンに課された使命は、いかに手早く“さも整地したかのようにみせかけるワザ”だったりする。
なんせ基礎工事期間2日というのは、何も時間的制限を課せられているだけではなく、工事費用としてもその程度しか支払われないコトを意味する。
現場作業というのは、人工(にんく)計算である場合が多い。
オヤカタは1時間で整地しておけと、ランマー一機を渡し、タバコを吸いながら携帯で誰かと話している。
30坪のこの区画を、ランマー転圧していこうとすると打撃板寸法から算出して約1200箇所転圧移動していくことになる。一地点3秒である。
アルバイトのオニイチャン的には、稲刈りのコンバインのように順繰りに進んでいけば仕上げられる計算にはなる。
だが、そこには調査屋が、構造屋が、計算した土質強度は見込めない。
そんなことは関係なく、オニイチャンは作業をする。
オニイチャンはアルバイトであり、オヤカタはオヤカタである。
ヒトは社会の中で暮らしているが、それ以前に自然の中に暮らしている。
ヒトの為(イ)は、時としてヒトの為にはならなかったりする。
“鋭敏比”という言葉の中には人為というスパイスも含まれている。













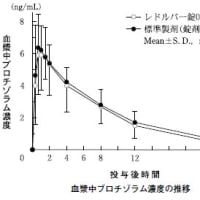

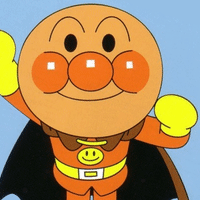
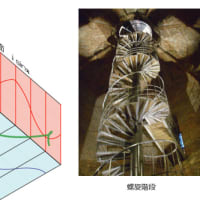

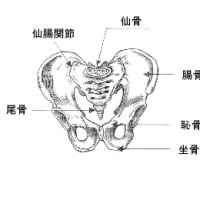
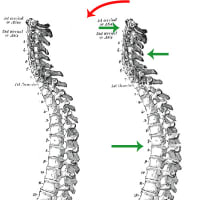
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます