自らの死というものについて、それに畏れ、或いは悲しみ、を覚える時、
そういった感情は、恐らく、有限性や喪失に向けられたものなのではないかと思う。
この世に如何なる関与もできなくなるかもしれないこと、何も知ることができなくなるかもしれないこと、そして、今まで得てきた全てを失うかもしれないこと。
そういった有限性や喪失への畏れ・悲しみというのが、死を生前に実感することなのではあるまいか。
やり残した仕事、残された家族、経験してみたかったこと、知りたかったこと、そういったことができなくなる。こういった身近な規模でも未練は残り、死を畏ろしく感じる。
そればかりでなく、(時間が無限に直線的に進むという前提の下であるが)自分の死後、自分が消滅したまま、何億年も何十億年も何百億年も時が流れる。何年経っても何年経っても、自分はそこにいない。何も見えないし何も考えない。そのような無が、未来永劫続く。このようなことを考えると、気が遠くなるような寂しさに、悲しみを感じる。
もちろん、いざ死んで絶対的な無の状態になれば、未練も寂しさも無くなるのだから、何も辛いことは無いだろう。
それでも、無限の時間の中に、何故、有限なる自己が存在しているのか。存在できるのは限られた時間で、それ以前、それ以後には、それと比較にならないほどの永い永い無が続く。それを思うと、自分は何のために存在しているのかを考えざるを得ず、更には、自分は本当に存在しているのかとすら思われて来る。
では、死後も個人の人格が保たれ、永遠に続くとしたらどうであろうか。
しかし、それも最終的には同じことなのかもしれない。
何億年・何十億年という期間存在し続けると、始めの十万年くらいで知りたいこともやりたいことも(知ることのできる、やることのできる範囲内では)全て尽くしてしまい、もはや何もかもが以前の体験の繰り返しとなり、やはり気が遠くなるような時間を無意味に過ごすことになるのではないだろうか。
全く変化が無い、というのは、存在しているという一点を除けば、結局は無と本質的には変わらないようにも思われる。
繰り返し、と言えば、仏教には「劫」という時間を単位とする循環世界観がある。
一つの世界は有限で、「成(じょう)・住(じゅう)・壊(え)・空(くう)」という成立・安定・破壊・消滅のプロセスを経て完結するという。しかし、消滅の後もまた新たに世界が「成住壊空」する。今我々の生きている世界は有限だが、その有限の世界が、前にも後にも無限個存在する。
それぞれの世界同士の関係がどのようになっているのかは勉強不足にして知らないが、世界が無限個あるならば、その中で今の我々の世界が再現されることもあるだろう。すなわち、今の自己が死によって消滅しても、気の遠くなるほど未来ではあるが、後の世界で再び同じ自己が繰り返されるのではあるまいか。
つまり、(恐らく、この世界観自体が本来意図することではないのだろうが)、有限の世界の無限回の繰り返しの中で、自己は無限性を得るのではなかろうか。
もっとも、この無限性というのも、単に無限に繰り返すというだけである。100歳で死んだ人間が、別の世界で再現されても、同じ100歳を繰り返すだけであろう。この100年間は無限の繰り返しによって永遠に保たれるが、内容量は永久に増えない。
言ってみれば、その人にとって、世界の長さは100年間なのである。つまり、有限であることに変わりはない。
こうなってくると、「時間が流れる」という観念も問題にしなければならなくなる。以前の日記でも少しだけ触れたが、「時間が流れる」というのは、実感を表現する語として優れているが、しかし、真理であるかは分からない。
上の「永久に繰り返す100年間」ということを思うと、むしろ、時間は流れ行くのではなく、ここに在るもの、としても考えられる。現在(という言い方が適切かはさておき)、自分の肉体は、空間上で、ある決まった分量の体積を持つ。それと同様に、また、時間上でも「自己」は決まった分量の幅を有する。つまり、「今、自分がここにいる」という自己は、時間の推移によって消滅するのではなく、無限(或いは有限ながら膨大)に伸びる座標上の一点に、確かに存在する。
このように認識すると、喪失という問題は、最早なくなってくる。
しかし、有限性という問題は残される。というよりも、強められるのである。自分の一生が確固として存在していようと、いくら繰り返されようと、期間・体験が限られることは変わらない。
更に言えば、この時間観では、「昨日の自分」と「今日の自分」の同一性、「ついさっきの自分」と「今の自分」の同一性はなくなる。一つの「自分」が時の流れの上を進んで行くのではなく、時間軸上に範囲として存在するのだから、その一点一点は別々のものと考えるべきかもしれない。謂わば、パラパラマンガのようなもので、始まりから終わりへ至る範囲の中で連続性(に見えるもの)を有するために、それを順番にめくれば一体のキャラクターが動いているかのように見えるが、一枚一枚は別々の紙である。
「今この瞬間の自分」は確かに存在し、それは永遠に続くが、その一点のみの存在で、前後の自己もまた別個の「今この瞬間の自分」であり、分割され得る。記憶や痕跡というものによって「自分」が続いているかのように思われるが、それは茶碗の中の米粒を「一杯のご飯」と認識するようなことに過ぎない。その形・色・質感・位置から「一杯のご飯」として世界の他の存在から区分して認識するが、それは傾向から連続性を判断しているに過ぎず、一粒一粒は別の個体である。
すると、自他の区別というのも曖昧なのではないか。
今この瞬間では間違いなく「今この瞬間の自分」であるが、「さっきの瞬間の自分」とは同一ではない。それは、「今この瞬間の自分」と「今この瞬間の他人」とが同一でないことと、本質的に異なることはない。同じ茶碗の中の米粒同士というのが、異なる茶碗の中の米粒より近しいとは断言できないだろう。
かつ、「今この瞬間」というのを如何に考えるべきか。座標上に於ける点の如く、限りなく最小の時間幅と考えた時、それに「自己」を見出す意味こそ怪しくなって来る。
ゼノンのパラドクスは、小麦粉の一粒一粒は落としても音の出ないのに、大量に一緒に落とすと音が出ることについて疑問を投げかけた。それに対して原子論者は「小麦粉一粒を落とした時にも小さな音が出る」と答えて罠に嵌った。
「今この瞬間」の一枚一枚が重なって、一つの「自己」を生むことについて、如何に回答すべきか。
荘子は言う。
全ては斉しく、かつ無である、と。
彼にかかっては、そもそも「自己」は存在しないのである。失うものも無ければ、限られるものも無い。故に、畏れも無ければ悲しみも無い。
では、何故、我思う、のであろうか。
回答はこうである。
それも幻に過ぎない、と。
思うに、世界というのは、幻の「自己」の巨大な集合体なのかもしれない。
このように言うと、「では、その“幻の自己”を見ている主体は何者なのか」と問いたくなる。
それについて、「神(God)」と答えるのも良いであろう。極端な汎神論。
或いは、「無限の可能性(無にして為さざる無し)」と言うのもアリかもしれない。時空を問わないあらゆる可能性が同時多発的に表現されている幻の中の一つ一つに、「自己」が有ったり無かったりする。実現するかもしれないし実現しないかもしれないという無限の枝分かれの末に、幻としての「自己」が、あたかも連続した存在かのように、出現して来るのかもしれない。
そういった感情は、恐らく、有限性や喪失に向けられたものなのではないかと思う。
この世に如何なる関与もできなくなるかもしれないこと、何も知ることができなくなるかもしれないこと、そして、今まで得てきた全てを失うかもしれないこと。
そういった有限性や喪失への畏れ・悲しみというのが、死を生前に実感することなのではあるまいか。
やり残した仕事、残された家族、経験してみたかったこと、知りたかったこと、そういったことができなくなる。こういった身近な規模でも未練は残り、死を畏ろしく感じる。
そればかりでなく、(時間が無限に直線的に進むという前提の下であるが)自分の死後、自分が消滅したまま、何億年も何十億年も何百億年も時が流れる。何年経っても何年経っても、自分はそこにいない。何も見えないし何も考えない。そのような無が、未来永劫続く。このようなことを考えると、気が遠くなるような寂しさに、悲しみを感じる。
もちろん、いざ死んで絶対的な無の状態になれば、未練も寂しさも無くなるのだから、何も辛いことは無いだろう。
それでも、無限の時間の中に、何故、有限なる自己が存在しているのか。存在できるのは限られた時間で、それ以前、それ以後には、それと比較にならないほどの永い永い無が続く。それを思うと、自分は何のために存在しているのかを考えざるを得ず、更には、自分は本当に存在しているのかとすら思われて来る。
では、死後も個人の人格が保たれ、永遠に続くとしたらどうであろうか。
しかし、それも最終的には同じことなのかもしれない。
何億年・何十億年という期間存在し続けると、始めの十万年くらいで知りたいこともやりたいことも(知ることのできる、やることのできる範囲内では)全て尽くしてしまい、もはや何もかもが以前の体験の繰り返しとなり、やはり気が遠くなるような時間を無意味に過ごすことになるのではないだろうか。
全く変化が無い、というのは、存在しているという一点を除けば、結局は無と本質的には変わらないようにも思われる。
繰り返し、と言えば、仏教には「劫」という時間を単位とする循環世界観がある。
一つの世界は有限で、「成(じょう)・住(じゅう)・壊(え)・空(くう)」という成立・安定・破壊・消滅のプロセスを経て完結するという。しかし、消滅の後もまた新たに世界が「成住壊空」する。今我々の生きている世界は有限だが、その有限の世界が、前にも後にも無限個存在する。
それぞれの世界同士の関係がどのようになっているのかは勉強不足にして知らないが、世界が無限個あるならば、その中で今の我々の世界が再現されることもあるだろう。すなわち、今の自己が死によって消滅しても、気の遠くなるほど未来ではあるが、後の世界で再び同じ自己が繰り返されるのではあるまいか。
つまり、(恐らく、この世界観自体が本来意図することではないのだろうが)、有限の世界の無限回の繰り返しの中で、自己は無限性を得るのではなかろうか。
もっとも、この無限性というのも、単に無限に繰り返すというだけである。100歳で死んだ人間が、別の世界で再現されても、同じ100歳を繰り返すだけであろう。この100年間は無限の繰り返しによって永遠に保たれるが、内容量は永久に増えない。
言ってみれば、その人にとって、世界の長さは100年間なのである。つまり、有限であることに変わりはない。
こうなってくると、「時間が流れる」という観念も問題にしなければならなくなる。以前の日記でも少しだけ触れたが、「時間が流れる」というのは、実感を表現する語として優れているが、しかし、真理であるかは分からない。
上の「永久に繰り返す100年間」ということを思うと、むしろ、時間は流れ行くのではなく、ここに在るもの、としても考えられる。現在(という言い方が適切かはさておき)、自分の肉体は、空間上で、ある決まった分量の体積を持つ。それと同様に、また、時間上でも「自己」は決まった分量の幅を有する。つまり、「今、自分がここにいる」という自己は、時間の推移によって消滅するのではなく、無限(或いは有限ながら膨大)に伸びる座標上の一点に、確かに存在する。
このように認識すると、喪失という問題は、最早なくなってくる。
しかし、有限性という問題は残される。というよりも、強められるのである。自分の一生が確固として存在していようと、いくら繰り返されようと、期間・体験が限られることは変わらない。
更に言えば、この時間観では、「昨日の自分」と「今日の自分」の同一性、「ついさっきの自分」と「今の自分」の同一性はなくなる。一つの「自分」が時の流れの上を進んで行くのではなく、時間軸上に範囲として存在するのだから、その一点一点は別々のものと考えるべきかもしれない。謂わば、パラパラマンガのようなもので、始まりから終わりへ至る範囲の中で連続性(に見えるもの)を有するために、それを順番にめくれば一体のキャラクターが動いているかのように見えるが、一枚一枚は別々の紙である。
「今この瞬間の自分」は確かに存在し、それは永遠に続くが、その一点のみの存在で、前後の自己もまた別個の「今この瞬間の自分」であり、分割され得る。記憶や痕跡というものによって「自分」が続いているかのように思われるが、それは茶碗の中の米粒を「一杯のご飯」と認識するようなことに過ぎない。その形・色・質感・位置から「一杯のご飯」として世界の他の存在から区分して認識するが、それは傾向から連続性を判断しているに過ぎず、一粒一粒は別の個体である。
すると、自他の区別というのも曖昧なのではないか。
今この瞬間では間違いなく「今この瞬間の自分」であるが、「さっきの瞬間の自分」とは同一ではない。それは、「今この瞬間の自分」と「今この瞬間の他人」とが同一でないことと、本質的に異なることはない。同じ茶碗の中の米粒同士というのが、異なる茶碗の中の米粒より近しいとは断言できないだろう。
かつ、「今この瞬間」というのを如何に考えるべきか。座標上に於ける点の如く、限りなく最小の時間幅と考えた時、それに「自己」を見出す意味こそ怪しくなって来る。
ゼノンのパラドクスは、小麦粉の一粒一粒は落としても音の出ないのに、大量に一緒に落とすと音が出ることについて疑問を投げかけた。それに対して原子論者は「小麦粉一粒を落とした時にも小さな音が出る」と答えて罠に嵌った。
「今この瞬間」の一枚一枚が重なって、一つの「自己」を生むことについて、如何に回答すべきか。
荘子は言う。
全ては斉しく、かつ無である、と。
彼にかかっては、そもそも「自己」は存在しないのである。失うものも無ければ、限られるものも無い。故に、畏れも無ければ悲しみも無い。
では、何故、我思う、のであろうか。
回答はこうである。
それも幻に過ぎない、と。
思うに、世界というのは、幻の「自己」の巨大な集合体なのかもしれない。
このように言うと、「では、その“幻の自己”を見ている主体は何者なのか」と問いたくなる。
それについて、「神(God)」と答えるのも良いであろう。極端な汎神論。
或いは、「無限の可能性(無にして為さざる無し)」と言うのもアリかもしれない。時空を問わないあらゆる可能性が同時多発的に表現されている幻の中の一つ一つに、「自己」が有ったり無かったりする。実現するかもしれないし実現しないかもしれないという無限の枝分かれの末に、幻としての「自己」が、あたかも連続した存在かのように、出現して来るのかもしれない。










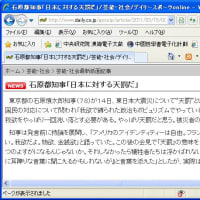

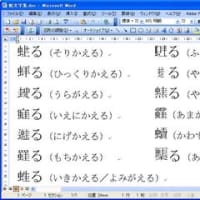




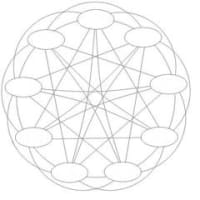


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます