以前の日記に書いた寓話は、中学生の頃に考えた話である。
私は、小学校に上がるか上がらないかという頃に、自らの死について考えていた記憶がある。おそらく、今まで最も長く考え続けたことであろう。
死後の世界、というのは、有るのか無いのかわからない。
ただ、脳細胞が傷ついただけで怒りやすくなったり、思考・判断が変わったり、記憶が失われたりするのだから、死んで脳味噌が丸々なくなれば、少なくとも生前の人格は保存されないであろう。
スピリチュアルの類で、死後の霊魂が生前の人格のままに語りかけるという話はある。しかし、その生前の人格というのが一体どの時点の人格なのかを聞いたことはない。例えば88歳で末期癌で脳に腫瘍ができている状態で亡くなった人だったら、亡くなる直前の、記憶も感情も大変な状態の人格で霊魂が存在するのだろうか。そうでないとしたら、病気になる直前の85歳くらいの「健康」な状態の頃の人格だろうか。それとも、80歳とか60歳とか40歳とか、もっと若い頃の人格だろうか。あるいは、88年間の生涯全ての瞬間の記憶と性格と価値観が統合されたものだろうか。結局、あれは、霊魂を呼び出したのが事実であれ虚偽であれ、その場にいる生者が見たいと思っている故人の人格を見ているに過ぎず、死後の人格そのものについては、何もわからない。
残された者たちが「死霊」に何を見出すかは残された者たちの認識であって、死んだ当人にとっては何も意味をなさないだろう。
自分の死は、本人の問題である。
周囲でいくら人が死のうと、それによって親しい人との死別の悲しみに慣れることはあっても、自らの死に慣れることはない。他人の死と自身の死は全く別の物である。死の先に何が有るか、あるいは無いかは、生前の経験で得ることはできない。
たとえ生前に死後のことを知ったとしても、死後が無であれば、あらかじめそれを知っていようと知るまいと、同じく無意味なことであろう。生前に得たもの全てが失われることを知った悲しみですら、死後には失われる。そして、悲しみを失う悲しみすら、死後にはないかもしれない。
それでも、自分の問題に他ならないからこそ、常にこの不可知なことを考えてしまう。そして、考えてしまうからこそ、こうした生者に対し、死後の情報を宗教が提供するのである。
私は、小学校に上がるか上がらないかという頃に、自らの死について考えていた記憶がある。おそらく、今まで最も長く考え続けたことであろう。
死後の世界、というのは、有るのか無いのかわからない。
ただ、脳細胞が傷ついただけで怒りやすくなったり、思考・判断が変わったり、記憶が失われたりするのだから、死んで脳味噌が丸々なくなれば、少なくとも生前の人格は保存されないであろう。
スピリチュアルの類で、死後の霊魂が生前の人格のままに語りかけるという話はある。しかし、その生前の人格というのが一体どの時点の人格なのかを聞いたことはない。例えば88歳で末期癌で脳に腫瘍ができている状態で亡くなった人だったら、亡くなる直前の、記憶も感情も大変な状態の人格で霊魂が存在するのだろうか。そうでないとしたら、病気になる直前の85歳くらいの「健康」な状態の頃の人格だろうか。それとも、80歳とか60歳とか40歳とか、もっと若い頃の人格だろうか。あるいは、88年間の生涯全ての瞬間の記憶と性格と価値観が統合されたものだろうか。結局、あれは、霊魂を呼び出したのが事実であれ虚偽であれ、その場にいる生者が見たいと思っている故人の人格を見ているに過ぎず、死後の人格そのものについては、何もわからない。
残された者たちが「死霊」に何を見出すかは残された者たちの認識であって、死んだ当人にとっては何も意味をなさないだろう。
自分の死は、本人の問題である。
周囲でいくら人が死のうと、それによって親しい人との死別の悲しみに慣れることはあっても、自らの死に慣れることはない。他人の死と自身の死は全く別の物である。死の先に何が有るか、あるいは無いかは、生前の経験で得ることはできない。
たとえ生前に死後のことを知ったとしても、死後が無であれば、あらかじめそれを知っていようと知るまいと、同じく無意味なことであろう。生前に得たもの全てが失われることを知った悲しみですら、死後には失われる。そして、悲しみを失う悲しみすら、死後にはないかもしれない。
それでも、自分の問題に他ならないからこそ、常にこの不可知なことを考えてしまう。そして、考えてしまうからこそ、こうした生者に対し、死後の情報を宗教が提供するのである。










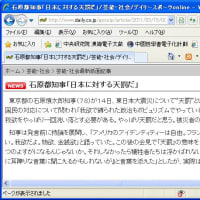

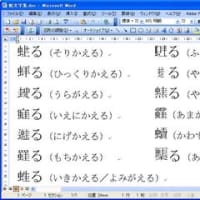




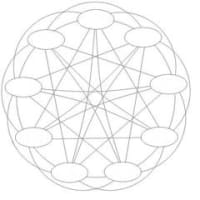


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます