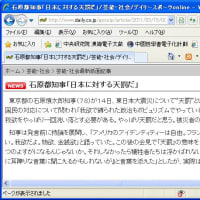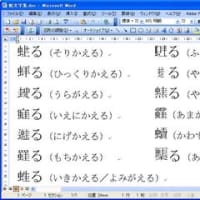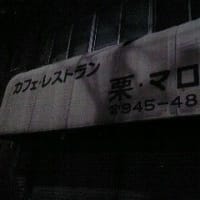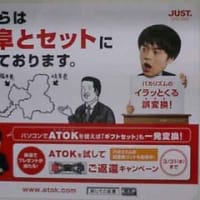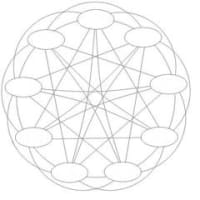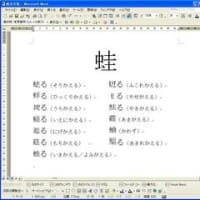震災発生以降、どうも気持ち悪い雰囲気が漂っている。
「一致団結」して「未曾有の国難」を乗り切ろう。大変な状況でマナーを守り、思いやりを持って助け合っているから、「日本人は素晴らしい」。等々。
足の引っ張り合いばかりだった政治や輿論が建設的方向に向かうのは良いことなのだが、私にはどうも気持ち悪い。後輩曰く、「いがみあっていたライバル同士が、協力して共通の強敵に立ち向かう、という筋書がみんな好きなんですよ」と。確かにそうかもしれない。
節電自体は、大変良いことだと思う。
しかし、「使っていない電灯は消す」「冷蔵庫にものを入れ過ぎない」「暖房の設定温度は下げる」程度のことは、普段から「でんこちゃん」が言い続けていることだ。デパートの電灯が明るすぎる、ネオンや巨大広告テレビが電気の無駄遣いだというのも、大抵の人間が前々から思っていたことではなかろうか。地震が起きて「ヤシマ作戦」が発動されなければ実行できないというのは、褒められたものではない。
そして、この非常時に、「節電しなければ非国民」のような言論が飛び交うのが気持ち悪い。確かに停電ともなれば、自宅療養中で医療機器に電気が必要な人が大変なことになるのだから、極力避けたい。しかし、言わせてもらえれば、普段からこの程度の節電をできていなかった者は、地球人として二流である。
最も気持ち悪いのは、様々なイベントを「自粛」する雰囲気である。
被災地を思えば、ガソリンや物資を買い込まず、募金くらいはすべきである。しかし、「自粛」については、よくよく考えなければならない。そして、これについては、「人間としての感情」と「市民としての務め」との衝突が関わってくるように思う。
何十、何百万もの人たちが苦しんでいる中で自分たちが心から楽しむことはできない、というのは人間として自然な感情である。しかし、多くの人間がその感情に従って行動したらどうなるだろうか。
東大の卒業式程度なら、問題は小さい。東大生協が安っぽいアカデミックガウンでボロ儲けすることができなくなるくらいだろう。
しかし、例えば、社会全体で宴会・旅行が「自粛」されれば、飲食店や旅行会社は次々と経営難に陥る。これは、二次的に、被害者を増やす行為である。つまり、人災だ。
似たような話で、阪神大震災の時に、被災者たちにとって一番迷惑だったのは、ボランティアだった、と聞いたことがある。大して役に立たないのに、食糧を消費する足手まといだった、という話。
ボランティアたちは、瓦礫の中で何百万もの人たちが苦しんでいる映像を見て、いてもたってもいられずに駆け付けたのであろう。これは、人間として自然な感情である。しかし、その結果、却って被災者たちに迷惑をかけた。すなわち、「駆け付けて協力したい」という自然の欲求を満たす、自己満足にしかならなかったのである。
彼らがすべきは、沸き上がる感情をぐっと抑え、普段通りに生活することだったのである。多少気を利かせて、「ボランティアに行ったつもり」で一日働いた分の給料を寄付しても良かった。
特に非常時に問われるのは、「良き市民」であるか否か、である。それは、自己の感情や周囲の雰囲気に流されず、自分の能力・立場が何の役に立つか、少なくとも迷惑にならないように振る舞えるか、を理性的に判断して実行することだと思う。
感情の発露や周囲への雷同は、人間が本来的に持つ性質である。しかし、それを我慢し、直感的に判断せず、よく考えることが必要となる。自分一人がこれをしたって構わない、ではなく、みんなが自分と同じようなことをした場合に社会全体がどうなるか、を視野に入れる。
たとえ人間の性が善であるとしても、善なる性に従うのみでは、必ずしも社会的に善とはならない。社会的に善なる市民となるには、理性的な判断と適度な実行力が必要である。そして、時にその行動には、自己の人間性を抑圧することも伴う。
地震発生以降の「不謹慎」「自粛」の蔓延を見ていると、暗澹たる思いを否めない。情感と配慮の細やかさは、日本人の美点である。しかし、これを裏返せば、盲目的な団結と雷同は、すなわち「衆愚」である。この体質は戦前から変わっていないのかもしれない。
戦時中に、このような話があった。
ある者がレコードでベートーヴェンをかけていたところ、憲兵が現れて、「敵性音楽をかけるとは何事か」と叱った。その者は「ベートーヴェンはドイツ人ですから、同盟国の人間であります」と反論した。しかし、結局押し問答の末、無理やり停止させられたという。
要するに、西洋のクラシックをかけること自体が、集団の均質性を乱すものとして、憲兵たちには受け入れ難かったのであろう。
それほど好きな人物でもないが、福沢諭吉には、このような話がある。
戊辰の戦乱の中、彼の塾では粛々と学問が続けられた。街中から斬り合いや砲火の音が響いて来ても、それは中断されなかったという。
彼は、長期的視野に立ち、自分が今すべきことが何かをよく考えていたのであろう。
「一致団結」して「未曾有の国難」を乗り切ろう。大変な状況でマナーを守り、思いやりを持って助け合っているから、「日本人は素晴らしい」。等々。
足の引っ張り合いばかりだった政治や輿論が建設的方向に向かうのは良いことなのだが、私にはどうも気持ち悪い。後輩曰く、「いがみあっていたライバル同士が、協力して共通の強敵に立ち向かう、という筋書がみんな好きなんですよ」と。確かにそうかもしれない。
節電自体は、大変良いことだと思う。
しかし、「使っていない電灯は消す」「冷蔵庫にものを入れ過ぎない」「暖房の設定温度は下げる」程度のことは、普段から「でんこちゃん」が言い続けていることだ。デパートの電灯が明るすぎる、ネオンや巨大広告テレビが電気の無駄遣いだというのも、大抵の人間が前々から思っていたことではなかろうか。地震が起きて「ヤシマ作戦」が発動されなければ実行できないというのは、褒められたものではない。
そして、この非常時に、「節電しなければ非国民」のような言論が飛び交うのが気持ち悪い。確かに停電ともなれば、自宅療養中で医療機器に電気が必要な人が大変なことになるのだから、極力避けたい。しかし、言わせてもらえれば、普段からこの程度の節電をできていなかった者は、地球人として二流である。
最も気持ち悪いのは、様々なイベントを「自粛」する雰囲気である。
被災地を思えば、ガソリンや物資を買い込まず、募金くらいはすべきである。しかし、「自粛」については、よくよく考えなければならない。そして、これについては、「人間としての感情」と「市民としての務め」との衝突が関わってくるように思う。
何十、何百万もの人たちが苦しんでいる中で自分たちが心から楽しむことはできない、というのは人間として自然な感情である。しかし、多くの人間がその感情に従って行動したらどうなるだろうか。
東大の卒業式程度なら、問題は小さい。東大生協が安っぽいアカデミックガウンでボロ儲けすることができなくなるくらいだろう。
しかし、例えば、社会全体で宴会・旅行が「自粛」されれば、飲食店や旅行会社は次々と経営難に陥る。これは、二次的に、被害者を増やす行為である。つまり、人災だ。
似たような話で、阪神大震災の時に、被災者たちにとって一番迷惑だったのは、ボランティアだった、と聞いたことがある。大して役に立たないのに、食糧を消費する足手まといだった、という話。
ボランティアたちは、瓦礫の中で何百万もの人たちが苦しんでいる映像を見て、いてもたってもいられずに駆け付けたのであろう。これは、人間として自然な感情である。しかし、その結果、却って被災者たちに迷惑をかけた。すなわち、「駆け付けて協力したい」という自然の欲求を満たす、自己満足にしかならなかったのである。
彼らがすべきは、沸き上がる感情をぐっと抑え、普段通りに生活することだったのである。多少気を利かせて、「ボランティアに行ったつもり」で一日働いた分の給料を寄付しても良かった。
特に非常時に問われるのは、「良き市民」であるか否か、である。それは、自己の感情や周囲の雰囲気に流されず、自分の能力・立場が何の役に立つか、少なくとも迷惑にならないように振る舞えるか、を理性的に判断して実行することだと思う。
感情の発露や周囲への雷同は、人間が本来的に持つ性質である。しかし、それを我慢し、直感的に判断せず、よく考えることが必要となる。自分一人がこれをしたって構わない、ではなく、みんなが自分と同じようなことをした場合に社会全体がどうなるか、を視野に入れる。
たとえ人間の性が善であるとしても、善なる性に従うのみでは、必ずしも社会的に善とはならない。社会的に善なる市民となるには、理性的な判断と適度な実行力が必要である。そして、時にその行動には、自己の人間性を抑圧することも伴う。
地震発生以降の「不謹慎」「自粛」の蔓延を見ていると、暗澹たる思いを否めない。情感と配慮の細やかさは、日本人の美点である。しかし、これを裏返せば、盲目的な団結と雷同は、すなわち「衆愚」である。この体質は戦前から変わっていないのかもしれない。
戦時中に、このような話があった。
ある者がレコードでベートーヴェンをかけていたところ、憲兵が現れて、「敵性音楽をかけるとは何事か」と叱った。その者は「ベートーヴェンはドイツ人ですから、同盟国の人間であります」と反論した。しかし、結局押し問答の末、無理やり停止させられたという。
要するに、西洋のクラシックをかけること自体が、集団の均質性を乱すものとして、憲兵たちには受け入れ難かったのであろう。
それほど好きな人物でもないが、福沢諭吉には、このような話がある。
戊辰の戦乱の中、彼の塾では粛々と学問が続けられた。街中から斬り合いや砲火の音が響いて来ても、それは中断されなかったという。
彼は、長期的視野に立ち、自分が今すべきことが何かをよく考えていたのであろう。