親知らずは20代の頃に3本抜いた。上二本と右下の一本です。上二本はアッサリ抜けたのですが右下の一本が頑固で歯医者さんが1時間近くかかって苦労して抜いてくれた。抜いた歯を見せてもらったところ、三叉のいかにも強そうな立派な頑固者の様相を呈していたことを覚えています。しかし、これに懲りてその歯科医は残りの一本は口腔外科で抜いてもらえワシはもう嫌じゃ、といって抜いてくれませんでした。30年以上前の事です。
その残った一本の親知らずが最近、冷たいものなどが沁みるようになってきた。おまけに食べ物がやたらに引っかかるのだ。1年ほど我慢していたが先日歯医者に見てもらったところ知覚過敏だな、抜いたほうが良いぞ、とおっしゃる。しかし、ワシは抜かないから大病院の口腔外科に紹介状を書いてやる、ということで紹介状を書いていただきました。
その紹介状をもってノコノコ病院に出かけると、早速パノラマ・レントゲンなるものでぐるりを鮮明に撮影してもらい見たところ影が見える。どうやら虫歯らしい。おまけに相方の上の歯が無いので3mmくらい浮いている。それで、直ぐに抜いてくれると思いきや、今日は抜かないから予約しろとおっしゃる。それなら速いほうが良いなと思い翌日の午後(本日)予約を入れて抜いてもらった。
前回(30年前)はえらく苦労したので今回も凄いことになるぞ、と恐怖と期待で緊張していたが、麻酔をチクチク注射した後、アゴを押さえてゴリゴリやってペンチみたいなものでグイッと引っこ抜いてくれた。なんとアッサリ5分もかからずに抜けてしまった。抜けた時は全然わからなくて先生にもう抜けました、と言われて思わずエッと口走ってしまった。口腔外科の医師は腕が良いのかなあ?まだ30歳を超えたばかりの若い先生でしたが有りがとうございました。
抜けた歯がこれ、

拡大はややグロなので見たいヒトだけクリックしてください。
知覚過敏どころか真ん中に大穴が開いてる。浮いてむき出しになった歯根部が隣の歯とこすれあって虫歯になってたらしい。この穴にやたらに食べ物が引っかかってたわけだ。最初の歯医者さん、これが見えなかったんかな、藪医者じゃね。
と、麻酔がまだ効いていて口がしびれたままこれを書いていたが、やばい、すこし痛みが出てきた。これは麻酔が切れるとけっこう痛いかもね ( ̄  ̄;)
その後の経過ー1
昨日は普通に食事をして(右側だけで咀嚼)鎮痛剤と抗生物質を飲んで寝ました。一晩経過しましたが今のところ痛みはほとんど無い。ネットで調べるとドライソケットというのが有って抜いた跡の穴に上手く血餅が固まらないと歯槽骨がむき出しになって、それはそれは痛い事になるらしい。とにかく上手く歯肉が塞がってくれる事を祈ります。
その後の経過ー2
二晩経過して痛みも腫れも無い、順調です。鎮痛剤は7日分出たが1回しか飲んでない。抗生物質は4日分出てる。抗生物質ももう飲む必要は無いと思うが医者からは4日分飲み切れという指示が出てる。耐性菌が出るのを防ぎたいんだな。まあ人類の為だと思って飲みますよ。後は、いつから抜いた側で食べ物を噛めるかだね。
その後の経過ー3
6日経過し傷口がほぼ塞がった感じがする。4日目あたりであごの下のリンパ節が少し腫れて痛みが出たので感染したかな、と思ったが次の日には直った。どうも、回復の過程でその様なことが起るらしい。傷口を早く治すにはビタミンCが必要らしいのでせっせとキウイやトマトを食べている。
その後の経過ー4
10日経って再診に行ってきた。塩水で洗浄して3分で終了、キレイな傷口でもう来なくて良いといわれました。ただ、穴はまだ開いてるのであと二週間くらいは反対側で噛んだ方が良いね、との事
以下、Wiki 参照
炎症反応、異物除去
受傷6~24時間は、周辺の毛細血管から好中球が滑り出てくる(好中球は、もし創(そう、傷口)が不潔な場合、細菌などを貪食処理する)。そして好中球は短時間で消滅する[14]。 受傷後12~48時間は、単球が創内に集まってくる。単球はアメーバ状に形をかえつつ、細菌や組織分解物の貪食を開始し、次第に捕食消化する能力を高めてゆく。これは単球がマクロファージに分化し、活性化マクロファージへ変化したことを意味する(もし、創内に向かってマクロファージが集まらなかったり力が弱かったりする場合は、分解物が除去できず炎症が長く続く
瘢痕治癒
マクロファージによる異物の除去作業が終了するころに、毛細血管の新生が起こり、線維芽細胞が出現する。 線維芽細胞はコラーゲン、タンパク質、多糖類を合成し、細胞間腔に分泌を開始する。線維芽細胞によるタンパク質合成には十分な酸素と栄養素が必要で、毛細血管の新生は、線維芽細胞にそれを供給する役割を果たしている(毛細血管は、周囲の血管から発芽状に発生、創内へとループ状に発育し、網目状になる)。コラーゲン分子は凝集し、原線維となり、瘢痕組織が形成され、創の修復が進む[14][15]。
この過程にかかわる注意点として、 コラーゲンは線維芽細胞の中にある粗面小胞体で合成されるが、水酸化されてから細胞から分泌される。もし水酸化が進まないと、線維束化されず、治癒は延滞してしまう。コラーゲン線維の水酸化には、ビタミンCが欠かせないとされる[14][16]。
受傷後12~48時間の、創に近い表皮細胞の端は、細胞が外観を失い、無定形化および膨化し、移動し、凝血内にある血清タンパク質や線維素の切れ端を貪食消化する(これは細胞分裂の準備を行っている)[14]。そして、連続性を備えた細胞層を形成しつつ、正常な外観を取り戻してゆき、表皮再生と真皮での治癒がほぼ同時に完了する[14]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%B2%BB%E7%99%92%E5%8A%9B














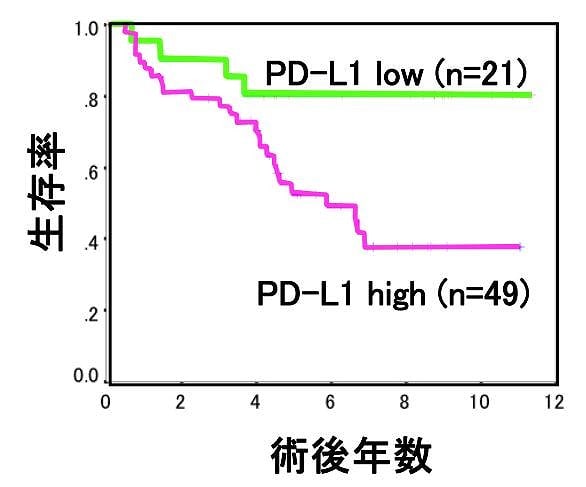







 左図 エボラ・ウィルス
左図 エボラ・ウィルス