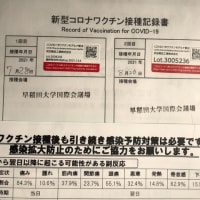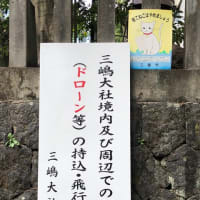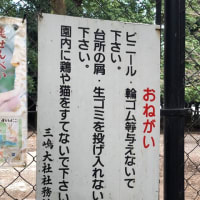こんにちは。
大学院の『銃・病原菌・鉄』を読む授業が終わりました。
次の本は、『これからの『正義』の話をしよう』になりました。(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)
担当回数の事情から、私が第一回目を担当することになりました。
以下、同書の第一章の要約を掲載します。
『銃・病原菌・鉄』より読みにくかったです。
ーーーーーーーーーーーーーーー
『これからの正義の話をしよう』 第1章 正しいことをする
2004年夏ハリケーンチャーリーが通り過ぎた後に怒った便乗値上げを巡る論争は道徳と法律に関する難問を提起している。商品やサービスの売り手が自然災害に乗じて、法外な価格を付けることは間違っているのだろうか。だとすれば法律は何をすべきだろうか。売り手と買い手が取引の自由に介入することになっても、州は便乗値上げを禁止すべきであろうか。
福祉、自由、美徳
〇これらの問題は正義にかかわることで、正義の意味を探求しなければならないと解決しないことだ。正義に関して異なる考え方を提示する理念(便乗値上げ禁止法への賛成反対の3つの理念)として、福祉の最大化、自由の尊重、美徳の推進があり、これによって正義に対して考え方が異なっていく。
〇二つの立場
・束縛のない市場の擁護論の論拠
1 市場は全体の福祉を増大させる
2 市場は個人の自由を尊重する
・禁止法の支持者
1 困っているときに請求される法外な値段は社会の福祉に資することはない
2 特定の状況下では自由市場と言っても本当は自由ではない
〇美徳の問題
しかし、そうした論拠(社会の福祉・自由)よりも、便乗値上げ禁止法を支持する理由は、憤りを感じるからである。強欲とは悪徳なのだ。
つまり、便乗値上げ禁止法をめぐる議論はたんなる福祉や自由の問題ではない。それは美徳に関する問題といえる。良き社会の土台となる心構えや意識、つまり品位を育むという問題である。一方で、美徳に関する問題について政府は介入すべきでないとする考えがある。
〇政治思想と正義
正義にかなう社会とは市民の美徳を養おうとするものなのか。それとも、美徳をめぐる相容れない考え方に対して中立を守り、市民が選択できるようにするものなのか。この問いに対して古代と近代の政治思想はわかれている。
・アリストテレス:望ましい生き方について考えなければ、どのような法律が正義にかなうかわからない。
・カント:正義にかなう社会は、各人がよき生を選ぶ自由を尊重するもの
→正義をめぐる理論は、古代では美徳から、近現代では自由から出発しているのだ。
〇正義の判断の困難性
・パープルハート勲章にふさわしい戦傷とは?→この勲章が求めるのは、英雄的行為ではなく傷の程度だけである。
・企業救済への怒り
2008~2009年の金融危機の際、投資家は大損害を被った。しかし企業の幹部は多額のボーナスをうけとった。このことに対して、国民から猛烈な批判がまきおこった。それは正義に反するという感覚にもとづくものであった。その正義とは、失敗した者が報酬を得てはならないということであった。それは強欲に対してではなかったのである。
〇正義への3つのアプローチ
ある社会が正義にかなうかと問うことは、われわれが大切にする、収入や財産、義務や権利、権力や機会、職務や栄誉がどう分配されるかということである。正義にかなう社会ではこうした善きものが正しく分配される。
本書では、以下のように考えて行く。
福祉の最大化:功利主義をとりあげる。そして、福祉はなぜ最大化すべきなのかを考える。
自由の尊重:正義とは自由および個人の権利の尊重を意味すると考えられている。
美徳の促進:正義は美徳や善き生と深い関係があるとする理論
〇予測できない事態
暴走する路面電車の例で、暴走する電車を止めるために、一人の作業員を殺して5人の命を救うか(または逆)/5人の作業員を救うために一人の太った男を線路上に突き落とすか。これは罪のない一人の命を奪うことによって、さらに多くの命が奪われるのを防ぐという意識的な選択であり、「できるだけ多くの命を救うべし」と「正当な理由があっても無実の人を殺すのは間違いだ」というジレンマの状態である。しかし、いずれかを判断したとしても、予測できない事態でだれもが助かるかもしれない。
アフガニスタンのヤギ飼いの例では、アメリカの兵士がアフガニスタンのヤギ飼いを見逃したことにより、兵士が大勢死んでしまった。予測できないためにそうなってしまった。
これらは、事態がどう展開するかわからないためますます正義の判断が難しくなっている。
〇本書の目的
本書は、正義と不正義、平等と不平等、個人の権利と公共の利益が対立する領域で、進むべき道を見つけ出すにはどうすればいいのか。その問いに答えるために書かれた。
上記のような葛藤に直面して、われわれは正しい行為についての判断を修正するかもしれないし、当初信じていた原則を見直すかもしれない。具体的な状況における判断と、そうした判断の土台となる原則のあいだを行ったり来たりすることが大切である。
こうした考察は孤独な作業ではなく、社会全体で取り組むべき試みでもある。われわれは内省だけでは正義の意味や最善に生き方を発見することはできないのだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
価値観がわかれるテーマがとりあげられので、院生との話し合いがもりあがるといいなと思い、この本を選びました。
今日も来てくださってありがとうございました。