




朝里駅付近、船見坂の通行人のマナー問題、朝里川温泉行きバスや天狗山行きバスの混雑、いつも行くお店が外国人客でいつも満杯で入れなくなったりと、身近な出来事として実感している市民も多いはず。
観光資源を守りながら地域の魅力を持続可能にするためには、訪問者への意識啓発や観光規制の整備は不可欠だ。
京都市の宿泊税引上げの報道もあった。
地域の声を尊重しつつ、住民の生活環境と観光振興のバランスを考慮していくこと、財源を確保しながらオーバーツーリズム対策を講じていくこと。
外国人観光客が増加傾向にあって、これらは今後も大きな行政課題となっていくのだろう。
ドライヤーとヘアアイロンがたて続けに壊れたとのこと。
ガーン。
「なんでそんなもん壊れた」と言ったところで覆水盆に返らず。
壊れたものは仕方ない。
何をしなければならないか未来を向いて考えよう。
毎日使うものだから、ある程度の性能があって、安物買いの銭失いにならないようなものをと、グーグル先生にあれこれ尋ねてみる。
先生には、色々教えてもらったのだが、結論としては、
①メーカーは日本製が間違いなさそう
②人気ランキング上位のものを買っておけば間違いなさそう
と、結局ごくごく無難で一般的な考えに落ち着いた。
そして、購入。


パナソニック製のヘアドライヤーとヘアアイロン。
高浸透ナノイーがなんちゃらかんちゃらで、キューティクルの損傷をうんぬんかんぬんにより防ぎ、紫外線ダメージをかくかくしかじかで抑えるらしい。
普段ドライヤーもヘアアイロンも使わない自分。
そんなもんいるのかよ、もっと安いのでいいっしょ、手痛い出費だよ。
そう言ってやろうと思ったが、今までのよりも格段にいいわーとか言いながらフンフン使っている娘たちに、
壊さないように使ってねー💦
精一杯の明るさでそう言って、そして、ため息ひとつの中年オヤジ(´;ω;`)

おもてなし(ホスピタリティ)とは、以下自分用メモとして。
ーーーーーーー
おもてなし(ホスピタリティ)とは
人と人との関わりの中でお互いの価値となる行動。
人としての優しさ、気遣い、品格、地域ボランティア、地域貢献活動
接客接遇、CIS管理、CRS、エンパワーメント、権限移譲デリゲーション
エンパワーメント
部下の自律や育成が主目的。
業務の進め方を部下に委ねることで、自律的に業務が遂行できるように促します。
デリゲーション
仕事を任せることそのものが目的。
業務の進め方などを全て担当者に委任する。
ISO23592
エクセレントサービス 卓越した顧客体験
サービスとおもてなしとの違い
サービス → おもてなし
等価価値交換 → 付加価値共創
主従関係 → 主客同一
満足(期待どおり) → 感動
マズロー 欲求段階
自己超越 自己の利益追求ではなく他人愛、コミュニティの発展などのための行動
アドラー
共同体感覚 共同体に自分が貢献している状態が最も精神的に健康な状態でいられる。
期待は十人十色。自分への期待値を理解する。
相手の様子を窺いながら相手の気持ちを察知する。
相手からの反応を引き出せるか、コミュニケーションをとっていこうとする姿勢。
期待<<現実 感動
期待<現実 大満足
期待=現実 満足
期待>現実 不満
期待>>現実 被害者意識
CIS Customer Impressive Satisfaction お客様感動満足
丁寧な対応
相手のために一秒待つ。
ホスピタリティの気持ちを持って相手を捉えることで自分のコンディションもよくなる。
相手の気持ちの前提を理解。納得感。
マジックフレーズ 言われたいことを言う。凝ってますね。お疲れですね。
環境に慣れると違和感がなくなる。固定概念の打破。

ホスピタリティを象徴する画像を生成してとチャットgptにお願いしたら作ってくれた。
やっぱりホテルのフロント、コンシェルジュサービスの印象あるよなあ。
寝ている部屋の蛍光灯のひもが切れた。
近ごろは光が多少チカチカもしているし、考えて見れば、この照明器具はここに住んでから23年間ずっと使い続けている。
そろそろ買い替え時なのかも。
新たに購入しようと、アマゾンを開くと、あるわあるわ。
そして、メーカーに拘らなければ、LED照明ってこんなに安いのね。
自分が浦島太郎だったと知る。

購入したのがこれ。
2,208円なり。
安いものでよしと、まずは試しに。


昨日届いたので、さっそく設置してみる。
ちょっと心配だったけど、簡単につけれたー!
今まで使ってきた大きな照明と比べ、とてもコンパクト!
大きさは感覚的に3分の1だ。
それでいて、明るさは申し分なく、電球色、昼白色、昼光色と色を変えることができて、明るさも無段階で調光可能。
さらに、リモコンで操作できるので、暗闇でベッドからヨッコイショと起き上がり、ヒモを引く必要もない。
枕元でピッ、ピッだ。
小型のLEDだから消費電力も低く経済的。
メリットしかないじゃないか。
どうしてもっと早く購入しなかったのだろう。
長く当たり前に使っている電化製品も、実は、今は進化していて、より使い勝手が良いものがたくさんあるのだろうな。
何も不自由がないと思っていても、IoT家電とか、暮らしがより便利に豊かになる、いわゆるQOLを上げてくれる商品が巷にはあふれているのだ。
中年オヤジとなった今でも、そういう情報を収集するためのアンテナは張っていないといけないなあ。
いや、中年オヤジだからこそ、意識して情報収集すべきなのかも。
ただでさえ歳を取るにつれて、どんどんとそういうものに疎くなっていくのだろうから。
蛍光灯のヒモが切れて困ったというのではなく、蛍光灯のヒモが切れてくれて、気付きを得て、結果的に良かったのだというお話。
そういう話にしてしまおう。
幸せ感度アゲアゲで、今日も頑張ります!
本日から仕事始め。
年末年始の長い連休のあとの仕事始めは、この歳になっても億劫な気持ちになってしまうのですが、本来もっと喜びを感じなければなりません。
こうして健康で元気に働かせてもらえることが、当たり前ではないのだから。
自分というリソースを使い切れるように、今年一年間も精一杯頑張ります!

「仕事はじめを象徴するイラスト」をAIが作成してくれました。
今年も希望に満ちているじゃないか。














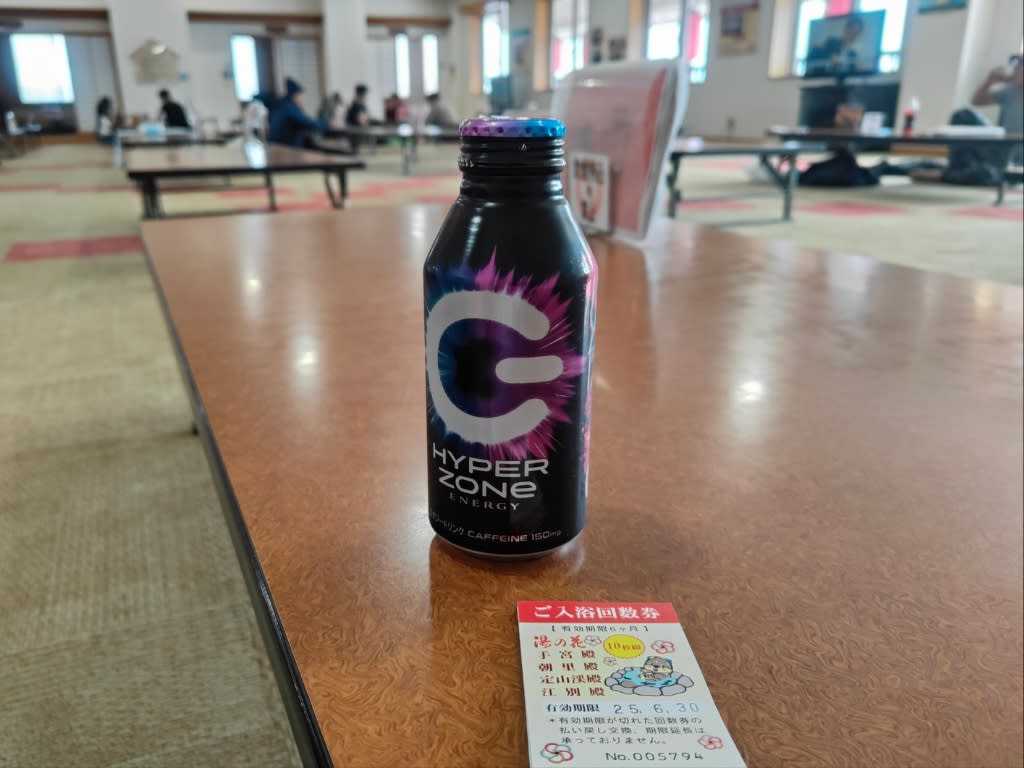





ーーーーーーーーーーーーーーーー
サランラップは、「ピッと切れて、ピタッと密着、気持ちいい」というコンセプトで、旭化成ホームプロダクツ株式会社が販売している食品包装ラップです。アメリカ合衆国で誕生し、日本には1952(昭和27)年に販売が開始されました。元々は、太平洋戦線で「蚊帳」や水虫から守る「靴の中敷き」、銃や弾丸を湿気から守るための「包装フィルム」として使用されていました。戦後にフィルムが改良され、食品包装用として製造されるようになりました。ラップの原材料は「ポリ塩化ビニリデン」で、「水分を保つ」「酸素を通さない」「臭いを通さない」という特徴を持っています。
クレラップは、「いちばんうれしいラップになろう」というコンセプトで、株式会社クレハが販売している食品包装ラップです。日本生まれの食品包装ラップ。日本では1960(昭和35)年に販売が開始されました。最初から「食品の保存」を目的として製造されました。ラップの原材料はサランラップと同様「ポリ塩化ビニリデン」で、「水分を保つ」「酸素を通さない」「臭いを通さない」という特徴を持っています。なお、添加物として「脂肪酸誘導体(柔軟剤)」、「エポキシ化植物油(安定剤)」を利用しています。対応温度は、-60℃~140℃。ラップを切る刃は、植物生まれのプラスチック刃採用(業務用除く)で、触れても手を傷つけにくく、廃棄時の刃の取り外しも簡単です。安全対策や利用しやすさを意識した改良を重ねています。
食品の鮮度保持に不可欠な酸素や水蒸気のバリアー性(遮断性)が高く、食器との密着性も優れる。 冷凍庫から電子レンジまで対応する使い勝手の良さも普及を後押しした。 約500億円の国内市場でNEWクレラップは35%、サランラップは48%を占める。
ーーーーーーーーーーーーー
サランラップのほうが売れているんだね。
大築紅葉(おおつきくれは)代議士はクレハのクレラップを選んでいると思う🤭
話を戻そう。
安いのは大変ありがたいが、反面、自分にとっては、精神的な負担がかなり大きく感じられてしまっているようだ。
ラップといっしょに、この精神的な負担軽減部分も買っていると考えればどうだろう。
コスパやタイパの視点から言えば、432円だって決して高いわけではないのかもしれない。
ひいては、人生のウェルビーイング、QOLにまでつながる話なのかもしれない。
ストレスなく豊かな人生を送るために、僅かなお金をケチってはいけないのかもしれない。
貧すれば鈍する。
日々の倹約で大局を見失い、判断を誤り、卑しい考えに流されてはいけない。
たかがラップでと言うなかれ。
というわけで、結論。
①クレラップは決して高くない。
②55ラップはもう購入しない。
いや、これだけではない。追加しよう。
③今後、以下の実験を試してみる。
実験:55ラップの使用を一旦やめてクレラップを使い、クレラップを使い切ったら箱だけ再利用し、55ラップの中身をクレラップの箱に移し替えて使ってみる。
これがうまくいったら最強じゃないか!
って、そんなふうに考えること自体が時間の無駄か。
大局を見失い、判断を誤り、卑しい考えに流されてはいけない。
って、難しい









温暖化によって雪が減った地域も多く存在するはずだ。
降水が雪から雨に変わるから。
長野、新潟など本州方面の地域のほか、ヨーロッパのアルプス山脈や北アメリカのロッキー山脈などのスキーリゾートでも雪不足が深刻だと聞く。
北極圏でも気温の上昇により雨が増え、一部地域で積雪の減少が見られるという。
雪が減ることで、水資源、冬季観光、地域経済など、国内外の多くの分野に影響を及ぼす。
温暖化の進行とともに、さらにこの変化は加速していくのだろう。
毅然とした態度は必要だと思いますが、ちょっと言い過ぎなのですかね。
賛否両論があるのは理解できますが、私個人的には、当事者である秋田県民の気持ちを代弁したこの知事を発言を支持します。
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/tvasahinews/nation/tvasahinews-000392478
クマに怯えて暮らす生活がどれだけ大変なのかを、よりリアルに想像する力が必要なのでしょう。


本物のクマって、少なくなくとも、こういうのではないですから。