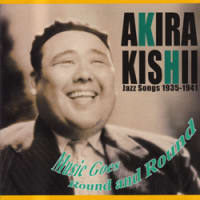中央アジア、タジキスタンの首都ドゥシャンベ。カメラは町の壁面を大雑把に撮り流していったあと、滞在型ホテルの一室で一組の男女が別れを惜しむ光景を写し出す。「もう潮時だと思っている」。外国人らしき男は地元の女にそう告げ、別れを惜しむ女からもさして深刻な悲しみは感じられない。彼女もおそらく、男の「潮時」という言葉に内心で同意しているのだろう。この去りゆく男、彼が『あの頃エッフェル塔の下で』の主人公であるフランス出身の人類学者ポール・デダリュスである。ポール・デダリュス、この名はアルノー・デプレシャンの長編第2作で出世作ともなった『そして僕は恋をする』(1996)と同じ名であり、その点では同作の続編的性質を持っていると言え、より正確にはポール・デダリュスの青春時代と、その頃を回想する中年時代の2つの時代を描いていることから、『そして僕は~』の前日譚と後日譚を兼ねているとも言える。
しかしポール・デダリュスという人物像は、トリュフォーの「ドワネルもの」のような人格的一貫性を持ってはおらず、さらに『クリスマス・ストーリー』(2008)ではマチュー・アマルリックではなく、エミール・ベルリングがポール・デダリュス役を演じていることを考えると、この固有名詞はあるひとつの存在を示すものではなく、言うなれば作者にとって(やや自伝的な)「扱いづらいと一族で忌避される、情緒不安定なわがまま息子」というような存在をジェネラルに拾い集めた符牒だと言えるのではないか。
パリ在住のポール・デダリュスと地方在住の女子高校生が頻繁にかわすラブレター。それらは単に書き文字としての物質性から軽々と遊離し、過剰なるナレーションのコーラスを形成する。2人は、フランソワ・トリュフォーの最も名高い一本『恋のエチュード』におけるジャン=ピエール・レオーとイギリス姉妹の文通を模倣する。その真剣なまなざしと文の読み上げは、私たち観客の心を激しく打つと同時に、滑稽さの印象も抱かせる。作り手側はおそらく病にうなされたこのラブストーリーを、愉快な遊び感覚で眺めつつ作ってもいるのだろう。前作『ジミーとジョルジュ 心の欠片を探して』(2013)が非常にシリアスであっただけに、今回はよけいに遊戯性を強めたのかもしれない。
本作の副題 Nos Arcadies(私たちのアルカディア)という語こそ、本作を解くキーであろう。アルカディアとはラテン語で桃源郷、牧歌的な楽園を意味しているが、その語はおのずとバロック時代の画家ニコラ・プッサンの有名な絵画のタイトル「Et in Arcadia ego」つまり「アルカディアに我(死神)もまた」へとつながっていき、それはつまり、いかなる楽園の図においても髑髏が描きこまれるという宿命をも示唆し、いかなる生の謳歌の最中にあってさえ、死はすぐそこにあるという警句となっていく。
「アルカディアに我(死神)もまた」については、今福龍太が2014年に出した『琥珀のアーカイヴ 書物変身譚』(新潮社)という本の中の「にもかかわらず(書物の)生を」という章で、レヴィ=ストロースへの考察を導入としつつ、くわしく論じているので、ぜひご参照いただければと思う。非常に美しい文章である。この映画の主人公ポール・デダリュスもレヴィ=ストロースを愛読していたことを思えば、大いなる必然的な関連を有している文章だと言えるだろう。
12/19(土)よりBunkamuraル・シネマ(東京・渋谷 東急本店裏)ほか全国順次公開
http://www.cetera.co.jp/eiffel/
しかしポール・デダリュスという人物像は、トリュフォーの「ドワネルもの」のような人格的一貫性を持ってはおらず、さらに『クリスマス・ストーリー』(2008)ではマチュー・アマルリックではなく、エミール・ベルリングがポール・デダリュス役を演じていることを考えると、この固有名詞はあるひとつの存在を示すものではなく、言うなれば作者にとって(やや自伝的な)「扱いづらいと一族で忌避される、情緒不安定なわがまま息子」というような存在をジェネラルに拾い集めた符牒だと言えるのではないか。
パリ在住のポール・デダリュスと地方在住の女子高校生が頻繁にかわすラブレター。それらは単に書き文字としての物質性から軽々と遊離し、過剰なるナレーションのコーラスを形成する。2人は、フランソワ・トリュフォーの最も名高い一本『恋のエチュード』におけるジャン=ピエール・レオーとイギリス姉妹の文通を模倣する。その真剣なまなざしと文の読み上げは、私たち観客の心を激しく打つと同時に、滑稽さの印象も抱かせる。作り手側はおそらく病にうなされたこのラブストーリーを、愉快な遊び感覚で眺めつつ作ってもいるのだろう。前作『ジミーとジョルジュ 心の欠片を探して』(2013)が非常にシリアスであっただけに、今回はよけいに遊戯性を強めたのかもしれない。
本作の副題 Nos Arcadies(私たちのアルカディア)という語こそ、本作を解くキーであろう。アルカディアとはラテン語で桃源郷、牧歌的な楽園を意味しているが、その語はおのずとバロック時代の画家ニコラ・プッサンの有名な絵画のタイトル「Et in Arcadia ego」つまり「アルカディアに我(死神)もまた」へとつながっていき、それはつまり、いかなる楽園の図においても髑髏が描きこまれるという宿命をも示唆し、いかなる生の謳歌の最中にあってさえ、死はすぐそこにあるという警句となっていく。
「アルカディアに我(死神)もまた」については、今福龍太が2014年に出した『琥珀のアーカイヴ 書物変身譚』(新潮社)という本の中の「にもかかわらず(書物の)生を」という章で、レヴィ=ストロースへの考察を導入としつつ、くわしく論じているので、ぜひご参照いただければと思う。非常に美しい文章である。この映画の主人公ポール・デダリュスもレヴィ=ストロースを愛読していたことを思えば、大いなる必然的な関連を有している文章だと言えるだろう。
12/19(土)よりBunkamuraル・シネマ(東京・渋谷 東急本店裏)ほか全国順次公開
http://www.cetera.co.jp/eiffel/