前記事で小津安二郎の『東京の女』(1933)にふれたけれども、同作でヒロイン岡田嘉子の弟役で出ていた江川宇礼雄はドイツ人と日本人のハーフである。物語上は新派悲劇ふうである『東京の女』のバタ臭さは、ひとつには小津の演出、もうひとつには配役によるところが大きい。
 今週、サイレント期の松竹女優・井上雪子が97歳で亡くなった。この人については、出世作となった小津の『美人哀愁』(1931)のフィルムが現存していないのが悔やまれる。ただ、清水宏の『港の日本娘』(1933)のさめざめとしたモダニズムは衝撃的で、先述のドイツ人ハーフたる江川宇礼雄と、オランダ人ハーフの井上雪子の新スターコンビが、じつにバタ臭い夫婦役を演じている。当時17歳の彼女の役名は「ドラ」。イプセン『人形の家』のヒロインがノラならこちらはドラということで、こんなけったいな役名が板につくのも、井上雪子くらいなものだろう(写真左は及川道子、右が井上雪子 =同作のスチール)。
今週、サイレント期の松竹女優・井上雪子が97歳で亡くなった。この人については、出世作となった小津の『美人哀愁』(1931)のフィルムが現存していないのが悔やまれる。ただ、清水宏の『港の日本娘』(1933)のさめざめとしたモダニズムは衝撃的で、先述のドイツ人ハーフたる江川宇礼雄と、オランダ人ハーフの井上雪子の新スターコンビが、じつにバタ臭い夫婦役を演じている。当時17歳の彼女の役名は「ドラ」。イプセン『人形の家』のヒロインがノラならこちらはドラということで、こんなけったいな役名が板につくのも、井上雪子くらいなものだろう(写真左は及川道子、右が井上雪子 =同作のスチール)。
モダニズム全盛の1930年代横浜。山下町あたりのモダンな町並みは、現代日本の開発者がどんなにがんばって再現してみても、模型にしかならない。もちろん当時のモダニズム建築だって西欧近代の模型にすぎないのだけれども。
『港の日本娘』はスクリーンやビデオで何度か見ているが、非常に感動的だったのは、2003年の東京フィルメックス〈特集上映 清水宏生誕100年〉における朝日ホールでの楽団演奏つき上映で、その夜の演奏の質の高さは衝撃的だった。澤登翠さん、柳下美恵さんらの多大な貢献にもかかわらず、それまでの私は、「サイレント映画は同時代に見るのでない以上、もはや弁士も伴奏も不要で、純粋に映画として対峙するためには、無音で見るのが一番好ましい」などと偏狭な解釈に囚われていた。しかし、あの時の『港の日本娘』楽団演奏つき上映は、そんなわが短絡を徹底的に痛めつけたのだ。
斎藤達雄の演じる画家がラスト、腐れ縁の愛人と共に大型客船で日本を去る。スクリーン前に陣取る楽団が、惜別のマーチを情感豊かに響かせる。デッキに立つ画家は、自分が今まで描いてきた絵を海へと投げ捨てる。波光きらめく横浜港の水面に、ぷかぷかと浮かぶキャンバス。日本映画史上でもっとも輝けるショットのひとつだろう。
上映後、フィルメックスの林加奈子さんが「会場には、特別な方が駆けつけておられます」と言うと、関係者席からとてつもなく上品な令夫人が立ち上がり、挨拶を述べた。井上雪子その人である。自分もこの映画を見たのは70年ぶりだ、と彼女は言った。そして、自分の座席からそのままホール出口へと退場する主演女優を、私たち観客の全員がスタンディング・オベーションで見送ったのは言うまでもない。
 今週、サイレント期の松竹女優・井上雪子が97歳で亡くなった。この人については、出世作となった小津の『美人哀愁』(1931)のフィルムが現存していないのが悔やまれる。ただ、清水宏の『港の日本娘』(1933)のさめざめとしたモダニズムは衝撃的で、先述のドイツ人ハーフたる江川宇礼雄と、オランダ人ハーフの井上雪子の新スターコンビが、じつにバタ臭い夫婦役を演じている。当時17歳の彼女の役名は「ドラ」。イプセン『人形の家』のヒロインがノラならこちらはドラということで、こんなけったいな役名が板につくのも、井上雪子くらいなものだろう(写真左は及川道子、右が井上雪子 =同作のスチール)。
今週、サイレント期の松竹女優・井上雪子が97歳で亡くなった。この人については、出世作となった小津の『美人哀愁』(1931)のフィルムが現存していないのが悔やまれる。ただ、清水宏の『港の日本娘』(1933)のさめざめとしたモダニズムは衝撃的で、先述のドイツ人ハーフたる江川宇礼雄と、オランダ人ハーフの井上雪子の新スターコンビが、じつにバタ臭い夫婦役を演じている。当時17歳の彼女の役名は「ドラ」。イプセン『人形の家』のヒロインがノラならこちらはドラということで、こんなけったいな役名が板につくのも、井上雪子くらいなものだろう(写真左は及川道子、右が井上雪子 =同作のスチール)。モダニズム全盛の1930年代横浜。山下町あたりのモダンな町並みは、現代日本の開発者がどんなにがんばって再現してみても、模型にしかならない。もちろん当時のモダニズム建築だって西欧近代の模型にすぎないのだけれども。
『港の日本娘』はスクリーンやビデオで何度か見ているが、非常に感動的だったのは、2003年の東京フィルメックス〈特集上映 清水宏生誕100年〉における朝日ホールでの楽団演奏つき上映で、その夜の演奏の質の高さは衝撃的だった。澤登翠さん、柳下美恵さんらの多大な貢献にもかかわらず、それまでの私は、「サイレント映画は同時代に見るのでない以上、もはや弁士も伴奏も不要で、純粋に映画として対峙するためには、無音で見るのが一番好ましい」などと偏狭な解釈に囚われていた。しかし、あの時の『港の日本娘』楽団演奏つき上映は、そんなわが短絡を徹底的に痛めつけたのだ。
斎藤達雄の演じる画家がラスト、腐れ縁の愛人と共に大型客船で日本を去る。スクリーン前に陣取る楽団が、惜別のマーチを情感豊かに響かせる。デッキに立つ画家は、自分が今まで描いてきた絵を海へと投げ捨てる。波光きらめく横浜港の水面に、ぷかぷかと浮かぶキャンバス。日本映画史上でもっとも輝けるショットのひとつだろう。
上映後、フィルメックスの林加奈子さんが「会場には、特別な方が駆けつけておられます」と言うと、関係者席からとてつもなく上品な令夫人が立ち上がり、挨拶を述べた。井上雪子その人である。自分もこの映画を見たのは70年ぶりだ、と彼女は言った。そして、自分の座席からそのままホール出口へと退場する主演女優を、私たち観客の全員がスタンディング・オベーションで見送ったのは言うまでもない。

















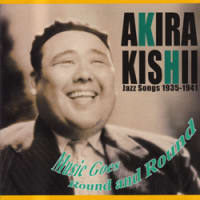


「港の日本娘」はやっと今年のゴールデンウィークに観ることができました。
足に絡まる毛糸玉も詩情を帯びて素晴らしかったと思います。またラストシーンでは、ただただ、まだ終わらないでくれと叶うはずのない願いを抱くしかありませんでした。
上映前には場内で年配の方々は井上雪子さんのことばかり話されていました。
柳下さんの伴奏もよかったですね。
嗚呼、終わっちゃうのか、惜しいなあと私もラストの客船で思いました。あんなに短期間にいろいろな事が起こって、登場人物たちが以前は感じなくていいストレスを抱え込み、拘束されていきますよね。でもそれを振りきるように、ひとつの旅立ちが、裁ち切りが傍観者によって演じられていました。
見直さずにうかつな記憶で書きますが、清水宏は翌年(1934)の『金環蝕』でも桑野通子をアメリカに旅立たせていたと思います。絶望を捨象するためにホームを捨てるんですね。『恋も忘れて』『按摩と女』も、戦後の『小原庄助さん』もそうでした…。
旅立ちという表象をあのように描くことができるのは、生まれもった才能だと思わざる得ません。