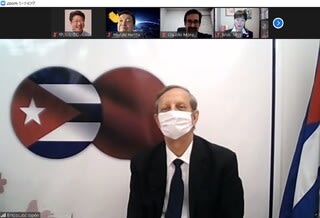(1)感染者情報について
【中川】山梨県では、新型コロナウイルス感染症に係る「調査中」案件で新たな情報が判明すると、ホームページに「追加情報」として掲載している。長野県でも「調査中」のその後の状況を明らかにし、経路を確認して封じ込めに活かすべきではないか。
【健康福祉部長】本県では、原則として陽性判明日の翌日にプレスリリースを行い、感染者の年代、性別、居住地等の基本情報や症状、経過等を公表している。
また、その後の調査で判明した他の発症例との関連や発症2週間前の滞在歴、濃厚接触者の状況等については、随時、県ホームページに掲載し、公表している。
今後も、保健所における丁寧な積極的疫学調査を行う中で、感染拡大防止のために県民の皆様に知らせる情報や、一定の安心感を持って生活を営んでいただけるような情報などを、正確かつ迅速に提供する。
【中川】これまで、無症状病原体保有者の濃厚接触者から陽性反応が出た例はあるか。
【健康福祉部長】本年9月28日現在の新型コロナウイルス感染者305例のうち、無症状病原体保有者は39例確認されている。この39例の濃厚接触者180名のうち、検査で陽性が確認されたのは、4例ある。
なお、無症状病原体保有者は、文字通り症状が出現していないことから、感染者とその濃厚接触者との感染の順番、すなわち、どちらからどちらに感染したのかを推定することが困難な場合があることをご理解いただきたい。
【中川】感染者情報を活用するHER-SYS(ハーシス)の利用状況を伺う。
【健康福祉部長】ハーシスは、より効率的に患者等に関する情報を収集し、地域の関係者間で共有できるようにするとともに、保健所の事務負担の軽減を図るため、本年5月29日より運用が開始されている。
本県においても、7月6日検体採取分より、医療機関や保健所などにおいて情報の登録を開始し、現在、帰国者・接触者外来及び検査協力医療機関など、114機関において利用されている。
一方で、データ入力にあたっては、保健所での代行入力が全体の6割を占めるなど、入力項目の多さなどから、却って医療機関や保健所の負担となっている。
今後は、これらを踏まえた国の運用見直しの動向を注視しつつ、効果的な活用を図っていく。
【中川】感染者の公表について、性別年齢は必要か。県民が知りたいことは個人特定できる情報ではなく行動履歴であるが、改めて公表についての考え方を伺う。
【健康福祉部長】感染者に係る情報の公表にあたっては、当初より、感染の拡大防止のために必要な情報を公表していくという基本姿勢に立つとともに、その一方で、感染者等の人権、プライバシーの保護には十分留意することとしている。
こうした考え方から、例えば不特定多数の濃厚接触者がいる場合には、その把握のため、具体的な場所や店舗名についても公表してきた。
逆に、調査の中で濃厚接触者が特定され、そこから感染が拡大する恐れがない場合には、感染者の行動歴を明らかにすることにより、個人の特定につながったり、一つ一つの行動について、誹謗・中傷のもとになるといった事態も危惧している。
また、感染者の行動歴を公表することとした場合、今後の積極的疫学調査において協力が得られなくなるといった懸念もあり、慎重かつ適切に判断すべきものと考えている。
(2)医療・検査体制の強化について
【中川】診療所などで新たに検査を行う場合、発熱外来テントや防護服などが必要となる。また、診療所での感染拡大の恐れがあることから、新型コロナウイルス感染症の検査はこれまでと同様に外来・検査センターを使うべきと考えるが、具体的に展開していくための方針について伺う。
【健康福祉部長】これからインフルエンザ流行期を迎えるにあたり、過去の発熱患者の発生状況を勘案して、本県のピーク時における検査需要を1日約9000件と見積もった上で、体制の整備を進める。
これだけの多数の患者が発生した場合には、できるだけかかりつけ医等の地域で身近な医療機関において相談、診療、検査を行っていただきたいと考えている。国においてもそのための支援措置を講ずることとしている。県でも、こうした体制を構築するため、今回の補正予算において医療機関に対する協力金を計上した。
一方、地域によっては、個々の医療機関ではなく、外来・検査センターなどで対応する方法が効果的または適切な場合があると考えられる。この場合には、センターの増設や能力向上といった取組も必要になってくる。
今後それぞれの地域において、保健所が医師会や市町村と連携して、地域の実情に合った体制を構築することとしており、県もしっかりとその支援をしていく。
【中川】病院、高齢者施設、障がい者施設などで働く方への一斉定期的な検査を行うべきではないか。
【健康福祉部長】国は、本年8月28日に発出した「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」において、「感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域においては、その期間、医療機関、高齢者施設等に勤務する者、入院・入所者全員を対象に、いわば一斉・定期的な検査の実施を都道府県等に対して要請する」としている。
もとより県としましても、医療機関や高齢者福祉施設等の入所者は重症化リスクが高いことから、県民の命と健康を守り抜くという目的のもと、施設内感染対策は最重要であると認識している。
今後、こうした検査にも対応できるようPCR等検査の処理能力のさらなる拡充を図るとともに、これらの施設に対する積極的な検査の実施を検討していく。
【中川】高齢者や基礎疾患を有する方への検査の実施について、考え方を伺う。
【健康福祉部長】国は、9月15日に閣議決定された予備費活用事業において、感染拡大や重症化を防止する観点から、市町村が高齢者や基礎疾患を有する者の希望により検査を行う場合に、その費用を助成することとしている。
県としても、市町村とていねいに協議を行い、検査体制整備計画に位置付けることにより、高齢者等に対する検査を円滑に実施できるよう努める。
【中川】感染拡大地域との往来者への積極的な検査の呼びかけを行うとともに、自己負担検査の拡充と検査費用の支援を行うべきではないか。
【健康福祉部長】第一波収束以降、海外渡航や県外への出張など、仕事に係る検査需要が増えてきており、県内でも十数か所の医療機関で全額自己負担の保険適用外検査を実施している。
検査は、安心して経済社会活動や日常生活を送るためにも、重要な前提となるものと認識しており、今後、これらの検査にも十分に対応いただけるよう、まずは県内におけるPCR等検査能力のさらなる拡充など、環境整備に努める。
【中川】病院等のPPE(個人防護具)は、依然として不足感がある。何をもって足りているのか病院によって判断が異なるため、県としても丁寧に調査を行うべきではないか。
【健康福祉部長】病院等における個人防護具の充足状況については、国の新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム、通称G-MIS(ジーミス)に各病院が1週間あたりの使用見込や在庫数量を入力することにより、県及び国において把握している。これに基づいて国によるプッシュ型の配布や調達困難時における緊急配布を行ってきた。
しかしながら、このシステムでは各病院の使用実態に基づく結果としての状況は把握できるものの、各病院においてどのように節約した使い方をしているのかといった取組までは明らかにならない。
そこで県では、これまでも数度にわたり電話による聞き取り調査やメールによるアンケートを実施するとともに、先月下旬にはいくつかの病院を訪問して使用状況や調達状況について聞き取り調査を行った。
診療や検査に欠かすことのできない個人防護具については、今後も丁寧に実態把握に努めるとともに、国や県の供給システムについて医療機関と共有することによって、必要な資材を必要な医療機関に迅速に供給できるよう取り組む。
【中川】宿泊療養施設の入所にあたっては、外部からの差し入れ禁止やSNSへの投稿禁止を条件にしているが、その理由と行動を制限できる根拠はどこにあるのか。また、これらの条件に合意できない場合はどのような扱いになるのか。
【健康福祉部長】宿泊療養施設は、医療機関の負担軽減のため、軽症者や無症状者の方で高齢者や基礎疾患のある方を除き、一旦入院して経過観察した後の療養場所として用意しているもの。
この宿泊療養施設は、安心・安全な環境下で運用を行っていく必要があるため、様々な点に配慮が必要であり、施設を設置・運営する県の責任において、入所にあたっての利用条件を設けている。
プライバシー保護の風評被害防止の観点により施設名自体を公表していないことから、入所者のSNSへの投稿についてご配慮いただくことを条件の一つとしており、また、感染防止の観点から外部者との接触を抑制するため、必要な薬等を家族の方が届ける場合を除いて外部からの差し入れを原則として禁止している。
宿泊療養への移行の際には、こうした条件も含め患者本人に説明し、同意いただくこととしている。同意いただけない場合には、引き続き入院していただくことになる。
【中川】長野県は平均寿命日本一を誇ってきた。その要因はいろいろと挙げられているが、新型コロナウイルス感染症に感染しても重症化しない理由とも重なると考える。これまで県が取り組んできた健康増進政策を、免疫力向上の政策としても打ち出していくことが今こそ必要だと思うがいかがか。
【健康福祉部長】免疫力の向上には、常日頃からのバランスのとれた食事と適度な運動により基礎体温を上げること、十分な睡眠などが重要である。
県では、これまで、県民の健康づくりに関して、県民の健康増進を図る運動、信州ACEプロジェクトを推進し、「毎日の運動」や「健康的な食事」といった生活習慣の実践を促してきた。
こうした取組は、県民の免疫力を高めることにも、少なからず効果があるものと考えている。
そこで今後は、免疫力向上につながるといった視点からも動機づけを行うなど、新型コロナウイルス感染症への恐れをプラスのエネルギーに換えて、県民に一層健康づくりに取り組んでいただけるよう働きかけていく。
【中川】第3波に備え、保健所の体制強化を更に図るべきではないか。
【健康福祉部長】第2波の振り返りからも、保健所の体制強化は重要かつ喫緊の課題である。
感染が拡大し、Level4(特別警報)を発令した上田地域においては、上田保健所の保健師に加え、クラスター対策チームの派遣や他の保健所等から延べ86名、1日最大10名の保健師の応援を行い、積極的疫学調査を徹底して実施した。このような人的資源の集中投入が感染の拡大防止につながったものと考えている。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大時における保健所の体制につきましては、7月に国から示された算式に基づいて試算した。県の10保健所での人員不足は、計31名となる。これを踏まえて、県では、その倍の61名を確保することを目標に取組を始めている。このうち、保健師については、これまでに12名、さらに今後13名の臨時的任用を行うとともに、臨床検査技師等についても大幅な増員を図っていく。
また、これら人員体制の強化に加えて、外部委託の活用や地域振興局をはじめとした現地機関や市町村保健師による協力体制の確立を図り、次の波に備えていく。
(3)今後の感染対策について
【中川】集会や会議開催時、参加者の住所・氏名・電話番号の記載を求められる。主催者管理となっていない場合もあるようだが、個人情報の取扱について県としてどのように指導しているのか。
【危機管理部長】連絡先等の把握については、国の基本的対処方針や内閣官房からの通知により、感染者が発生した場合に調査を行いやすくし、感染拡大防止につながるよう、催物の主催者や施設管理者に対し参加者の連絡先等を確実に把握することを求めている。
県としては、国の方針等に基づき連絡先等の把握について特措法第24条第9項により協力の要請をするとともに、関係団体や市町村を通じて主催者や施設管理者に周知を依頼し、あわせて連絡先等を記載した名簿に関する考え方を伝えている。
この中で、個人情報の保護の観点から、名簿は参加者等に対し保健所が実施する調査に限って利用するという目的や使用方法を説明し同意を得た上で作成することや、名簿の目的外利用の禁止、保管方法、保管期限などを示し、協力をお願いしている。
今後も、こういった方法により周知するとともに、催物開催の事前相談があった場合には、名簿の適切な取扱いを求めていく。
【中川】教育委員会は子どもたちの行動履歴把握等の通知を行ったが、その趣旨とプライバシー保護の観点から取扱いに対してどう考えているか。
【教育長】通知の趣旨は、夏休み中、児童生徒が県外に行ったり、県外の方と接触する機会も多いことから、そのような児童生徒について、夏休み明けの学校生活において、教職員がきめ細やかに健康観察をするために行ったものである。
これにより、そうした児童生徒が安心して県外に行くこと等ができ、また、休み明け後、その子らも含め児童生徒が安心して学校生活を送ることができると考えたもの。
しかしながら、プライバシー保護の観点からは、個人の行動について学校が把握することに対しては慎重に対応する必要があることから、今後の感染症対策を進めるうえで十分留意する。
【中川】学校によっては十分な感染症対策が行われていないところもあるようだが、県として学校への対策状況の調査は行っているか。また、調査結果を踏まえた今後の対策について伺う。
【教育長】県立学校については、月2回程度、健康チェックや消毒、換気、身体的距離の確保等の感染症対策について、県教育委員会として聞き取り調査等により確認を行っており、必要な対策がとられている。
また、市町村立学校については、教育事務所の主幹指導主事が学校訪問を行う中で状況把握に努め、助言を行っている。また、今月中には、全ての学校を対象とした感染症対策の調査を依頼する予定であるので、調査結果を踏まえ適切な対応をとっていく。
今後とも学校における感染症対策の徹底に努める。
【中川】保育所における感染症対策の状況を調査しているか。また、その状況を踏まえ、今後どのように対策を行うのか。
【県民文化部長】対策の状況は、県庁及び保健福祉事務所に配置する保育専門推進員等が保育施設を訪問して、現場を確認し、施設の責任者から直接状況を聞き取る形で把握している。
それによるとあ、保育現場では、今のところ消毒用アルコールやペーパータオルなどの感染対策用品は行きわたっている一方、子どもたちと保育士が触れ合うことにより保育を行うことが一般的なため、密になりやすく、ソーシャルディスタンスの確保が困難といった特有の課題もある。
給食やおやつの時に、透明のパーテーションを設置する、あるいは昼寝の際には子どもの頭と足を互い違いの方向に寝かせるなど、それぞれ施設で実情に応じて、様々な工夫がされている。
県としては、引き続き保育所からの問い合わせに対して丁寧な対応を行うほか、巡回訪問により、状況を把握し、必要なアドバイスを行うとともに、現場での効果的な取組について、保育所間で共有を図っていく。
また、衛生用品の購入や感染対策の研修等の経費について補助を行うなどにより、保育現場における感染対策を支援していく。
(4)子どもたちの環境について
【中川】学校再開後、子どもたちの変化について「疲れやすい」「生活習慣の乱れ」「落ち着きがない」という学校の先生たちの受け止めがある。また、「学習意欲の減退」「不安傾向」「不登校傾向」「無気力」など心のケアが必要と考えられる傾向も指摘されている。子どもたちへのケアは現在どのように行われているか。
【教育長】学校再開後、早期に担任等が「心と体のチェック票」を活用し、子どもたち一人一人と面談を実施している。子どもの表情やしぐさ、声の調子なども含め、子どもたちの状況を丁寧に把握し、心のケアに努めてきた。
子どもたちが抱えるストレスや悩みごとに対して、現在、多くの学校で学校生活アンケートや三者懇談を実施し、子どもや保護者とじっくり向き合える時間をつくって対応に努めている。
さらに、その中で支援が必要な子どもに対しては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家と連携し、適切な心のケアを行っている。
県教育委員会でも、今年度は長期休業前後だけではなく、毎週水曜日にLINE相談を実施している。また「学校生活相談センター」では24時間相談を受け付けている。引き続き子どもの悩みに寄り添っていく。
【中川】ゲーム内のいじめが現実社会のいじめに繋がっているなど、増加傾向にある子どものネットトラブルへ県教委はどのような対応をしてきたのか。また、今後の課題は。
【教育長】県が以前から実施している児童生徒約4千人を対象とする調査では、インターネットを利用している児童生徒のうち、昨年度は小学生の1.4%、中高生の0.6%が「ネットの中でいじめにあった」という回答があった。
こうしたことも踏まえまして、県ではこれまで、「性被害防止教育キャラバン隊」の派遣や「高校生ICTカンファレンス」の開催、ネットの専門家を講師に迎えた教職員向け研修会の開催等により、インターネットの適正利用に関する啓発やトラブルの未然防止を図ってきた。
今年度は、初めて、県内の教員や小児科医からなる「子どものメディア信州」の皆さんと協力し、約7万2千人の児童生徒を対象にインターネット等の利用についてのアンケート調査を実施した。長期休業の影響について聞いたところ、長期休業を経て使用時間が増えたとした児童生徒が5割を超え、トラブルの増加が懸念されるところである。
現在、アンケート結果を分析しているところ。「子どもとメディア信州」の皆さんと共に、今後取り組むべき方策について検討を進め、さらなる有効な取組につなげていく。
(5)今後の総合的な対策強化について
【中川】第2波について市町村別で見た場合、感染者数が10万人あたり20人を超える時期もあったが、「休業の検討の協力依頼」はされなかった。協力依頼に至らなかった理由と、第2波への対策・取組は条例を生かした取組であったか伺う。
【知事】条例6条1項によります「休業の検討の協力の求め」については、感染警戒レベル5に達するなど、感染が顕著に拡大し、人の移動や本県との往来を極力少なくする必要がある場合を想定している。
いわゆる第2波においては、医療提供体制の拡充も進み、重症者向けを中心に病床にはまだ余裕があったことなどから、こうした措置を講ずることなく対応を行った。
いわゆる第2波への対応については、まず条例第4条の規定に基づく基本的方針を策定して、その対応方針を基に対応を行ってきている。また、対応方針に定めた様々な取組は、条例第5条による感染症対策として実施している。
さらに、これらの方針の決定や対策の実施につきましては、第8条により学識経験者等から意見を聴取し、第9条によりまして議会へ報告させていただくなど、条例に基づき適正な手続きをとって行っている。
【中川】先般の上田圏域における対応では、県と上田市が連携して対応にあたった。今後についても、市町村と必要な情報を共有し、市町村や医師会との協力体制をさらに強化していくべきではないか。
【知事】県医師会の会議に参加したり、また市長会・町村会とはWEB会議等を通じて意思疎通を図っている。市町村や医師会との連携、非常に重要だ。
現在、季節性インフルエンザ流行期に向けた対策が喫緊の課題となっているが、これも、保健所が中心となりながらも、群市医師会や市町村の皆様の協力が不可欠である。
引き続き市長会・町村会並びに県医師会、さらには郡市医師会の皆様方の力を借りながら新型コロナウイルス対策を進めていく。
【中川】新型コロナウイルス感染症により県税収入の大幅な減収が見込まれる。一方で、新型コロナ対策や災害対応への歳出増が見込まれ、中長期的な財政の見通しが必要であると考えるがいかがか。
【知事】県税収入の大幅な減少が見込まれる中、他方で、新型コロナ対策や災害からの復旧・復興、大変大きな財政支出を行ってきているところであり、厳しい財政運営を迫られている状況。
通常債残高の縮減、あるいは財政調整のための基金の積増しなどをこれまで行ってきたので、現時点の見込みでは財政健全化に関する指標の上昇も限定的であるので、ただちに財政の健全性が大きく損なわれる状況にはない。
ただ、次年度以降、慎重な財政運営が必要となってくるので、来年度の県税収入、地方財政対策の内容も踏まえ、また新型コロナウイルスの影響も見極めた上で、試算を行い、来年度の当初予算案と合わせて、新たな中期財政試算として公表して、それに基づく対応を行う。