朝のジョギング、田園の中を走るのは気持ちいいもんです。
麦の穂が青々としてきました。丈も伸びて、さあ、そろそろ収穫も近いんでしょう。
爽やかな春の日々であります。
今日は、シューベルトの交響曲第9番ハ長調「グレート」を。
ハインツ・レーグナー指揮ベルリン放送交響楽団の演奏。
1978年6月、東ベルリンのキリスト教会での録音。
当時盛んだったDENONの東ドイツ録音で、東独ドイツ・シャルプラッテンとの共同制作の1枚。LP初出の時は2枚組で2800円。PCM録音の良さを贅沢に味わってもらおうと、2枚組4面に各楽章を割り当てていた。
LPから買い直したこのCDは1990年の廉価盤。税込み(3%だった・・・)1875円。当時としては戦略的に安い価格だった・・・・。
(ところで、「ザ・グレイト」と書くべきなのか・・・・最近はこの表記が多いような気がするが。昔は「グレート」だったので、今もついついそう書いてしまう・・)
さて第1楽章。
レーグナーの「グレート」、最も聴きものは、この序奏部。
遅い。非常に遅い。ボクが持つ「グレート」の中で最も序奏部が遅い演奏。
雄大なスケール。ゆったりと深々としたフレージング。シューベルトが友人に「今度、大きな交響曲を書くんだ」と語ったというその大きさが予感されるような出だし。
オーケストラの残響も素晴らしく、録音も暖かく柔らかいので、この序奏部を聴いているだけで幸福になる。
レーグナーはスゴイ指揮者なんじゃないか・・・・序奏部を初めて聴いた時、ボクはそう思ったものだった。(その後、徳間音工のブルックナーを何枚も聴いて、速めのテンポ、スケール感があまりないのに戸惑ったのだが・・・)
マイクがややオフ気味で、教会独特のホールトーンが美しい。残響によってスケールの雄大さがさらに際だつのだが、序奏部のラスト部分、あまりにも遅すぎてアンサンブルが乱れるのはご愛敬か。
主部に入るとテンポは普通。確かな歩みのアレグロ・マ・ノン・トロッポ。
第2楽章はゆったりとしたテンポ。遅すぎることはない。テヌートが多用されて、たっぷりと旋律が歌われる。リズムがやや停滞しても旋律の流れを優先している感じ。ヴァイオリンのトゥッティはとても美しい。
曲は第3楽章、そして終楽章へ。残響成分の多い録音がこの楽章でもスケール感を演出してくれる。楽器がよく融け合って、フンワリとした暖色系の音になっている。上手いオケだとは思わないが、東独時代の放送オケなので、機能性はたかいんじゃないかと思う。
終楽章は圧倒的なクライマックス。金管が大活躍するが、野卑な感じにならないのは、教会録音の暖かさだろう。柔らかなフォルティシモに包まれるのは快感だ。
ハインツ・レーグナーの録音は、日本では徳間音工、ドイツ・シャルプラッテン原盤が多いんですが、このDENONの「グレート」ほど見事な録音はなかったように思います。
レコードやCDでブルックナー、ビゼー、ワーグナーなどがありましたが、この「グレート」のように雄大なスケール感はありませんでした。
ボクにとってはレーグナーの遺した録音では最高のものになっています。

麦の穂が青々としてきました。丈も伸びて、さあ、そろそろ収穫も近いんでしょう。
爽やかな春の日々であります。
今日は、シューベルトの交響曲第9番ハ長調「グレート」を。
ハインツ・レーグナー指揮ベルリン放送交響楽団の演奏。
1978年6月、東ベルリンのキリスト教会での録音。
当時盛んだったDENONの東ドイツ録音で、東独ドイツ・シャルプラッテンとの共同制作の1枚。LP初出の時は2枚組で2800円。PCM録音の良さを贅沢に味わってもらおうと、2枚組4面に各楽章を割り当てていた。
LPから買い直したこのCDは1990年の廉価盤。税込み(3%だった・・・)1875円。当時としては戦略的に安い価格だった・・・・。
(ところで、「ザ・グレイト」と書くべきなのか・・・・最近はこの表記が多いような気がするが。昔は「グレート」だったので、今もついついそう書いてしまう・・)
さて第1楽章。
レーグナーの「グレート」、最も聴きものは、この序奏部。
遅い。非常に遅い。ボクが持つ「グレート」の中で最も序奏部が遅い演奏。
雄大なスケール。ゆったりと深々としたフレージング。シューベルトが友人に「今度、大きな交響曲を書くんだ」と語ったというその大きさが予感されるような出だし。
オーケストラの残響も素晴らしく、録音も暖かく柔らかいので、この序奏部を聴いているだけで幸福になる。
レーグナーはスゴイ指揮者なんじゃないか・・・・序奏部を初めて聴いた時、ボクはそう思ったものだった。(その後、徳間音工のブルックナーを何枚も聴いて、速めのテンポ、スケール感があまりないのに戸惑ったのだが・・・)
マイクがややオフ気味で、教会独特のホールトーンが美しい。残響によってスケールの雄大さがさらに際だつのだが、序奏部のラスト部分、あまりにも遅すぎてアンサンブルが乱れるのはご愛敬か。
主部に入るとテンポは普通。確かな歩みのアレグロ・マ・ノン・トロッポ。
第2楽章はゆったりとしたテンポ。遅すぎることはない。テヌートが多用されて、たっぷりと旋律が歌われる。リズムがやや停滞しても旋律の流れを優先している感じ。ヴァイオリンのトゥッティはとても美しい。
曲は第3楽章、そして終楽章へ。残響成分の多い録音がこの楽章でもスケール感を演出してくれる。楽器がよく融け合って、フンワリとした暖色系の音になっている。上手いオケだとは思わないが、東独時代の放送オケなので、機能性はたかいんじゃないかと思う。
終楽章は圧倒的なクライマックス。金管が大活躍するが、野卑な感じにならないのは、教会録音の暖かさだろう。柔らかなフォルティシモに包まれるのは快感だ。
ハインツ・レーグナーの録音は、日本では徳間音工、ドイツ・シャルプラッテン原盤が多いんですが、このDENONの「グレート」ほど見事な録音はなかったように思います。
レコードやCDでブルックナー、ビゼー、ワーグナーなどがありましたが、この「グレート」のように雄大なスケール感はありませんでした。
ボクにとってはレーグナーの遺した録音では最高のものになっています。











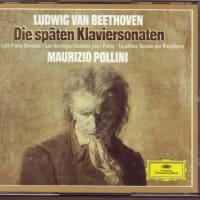
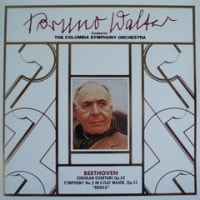
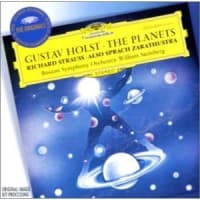
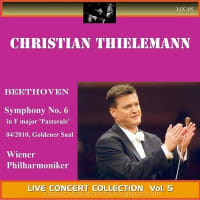
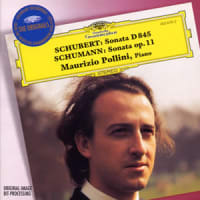
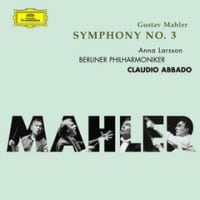
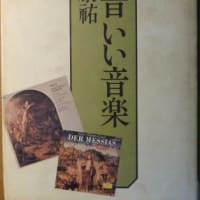

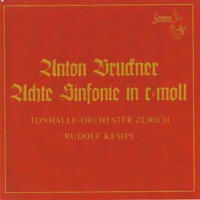
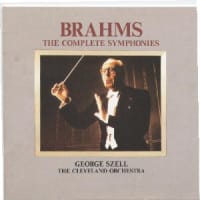

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます