この人に聞きたい
By マガジン9編集部 2022年3月16日
ロシアによるウクライナ侵攻を機に、軍事力の増強や憲法9条改正を求める声が目立っています。政治家の中からは、国是であるはずの非核三原則の見直しに踏み込むような発言も。果たしてそれは、本当に私たちの安全を守ることにつながるのでしょうか。ウクライナの状況を前に、私たちが考えるべきことは? 防衛ジャーナリストの半田滋さんにお話をうかがいました。
プーチン政権はなぜ、ウクライナ侵攻に踏み切ったか
──今回のロシアによるウクライナ侵攻を、どう見られていましたか。
半田 ロシア軍は昨年11月ごろからウクライナ国境周辺に10万人規模の兵力を展開し、今年2月末にはそれを19万人体制にまで拡大させていました。ですから、何らかの軍事行動はあるだろうとは思っていましたが、ここまで大規模な侵攻になるとは考えていませんでした。狙いはウクライナ東部のドンバス地方の実質的な占領であって、そこをNATOの東方進出に対する緩衝地帯にしたいのだろう、しかしそれにしては展開されている戦力があまりにも大きい……と思っていたら、今回の全面侵攻になったわけです。
──なぜロシアのプーチン大統領は、ここまでの大規模な侵攻に踏み切ったのでしょう。背景には「NATOの東方拡大」があるといわれていますが……。
半田 もともと、NATOというのは冷戦時代、西側諸国が「ソ連の脅威」に対抗するためにつくった軍事同盟ですから、プーチンの立場からすれば、冷戦終了とともに解散するべきだったということになります。それが、解散するどころかどんどんヨーロッパから東側へと拡大し、かつてNATOと対立するワルシャワ条約機構に加盟していた国々や、バルト三国などロシアとともにソ連邦を構成していた国々までが加わるようになった。プーチンは2010年に出した「軍事ドクトリン」ですでに、「NATOはロシアにとっての安全保障上の脅威」だと明言していました。
そして、2014年にはウクライナで革命が起こり、反ロシアの親米政権が成立。19年に就任したゼレンスキー現大統領はNATO加盟を選挙公約に掲げ、憲法にも努力目標として書き込みました。ロシアから見れば、ウクライナのNATO加盟はもはや秒読みの段階に見えたでしょう。
昨年12月には、プーチンはNATOに「NATOがこれ以上東方拡大をしないという法的な根拠を求める」などと記した、最後通牒ともいえる書簡を出しています。しかし、バイデン米大統領はじめNATO側は、ロシアがウクライナ国境に兵力を展開させ始めた後も、これに応じようとはしませんでした。
──大規模な侵攻にまでは踏み切ることはないという読みだったのでしょうか。
半田 最近は、ロシアからの天然ガスの輸出入などを通じて、西側諸国とロシアとの経済的なつながりが非常に強くなっていました。それだけに、ロシアもまさか無茶なことはしないだろうと「なめていた」ところがあったのだと思います。
しかしロシアにしてみれば、アメリカとの関係においても、弾道弾迎撃ミサイル制限条約(ABM条約)、中距離核戦力全廃条約(INF条約)と、ソ連時代に結んだ軍縮条約を次々反故にされているわけで、NATOの東方進出との「二段構え」で脅かされているという感覚があったでしょう。そして、今後ウクライナのNATO加盟が実現したら、ウクライナを攻めればNATO軍が出てきて全面戦争になる、その前に…という、プーチンにとってはぎりぎりの判断だったのかもしれません。
また近年、プーチンの65歳の誕生日にあわせてロシア各地で反体制デモが起こるなど、プーチンの政権基盤は必ずしも盤石とはいえません。「外憂」を作って国民の目をそちらに向け、国内政治を安定させたいという意識もあったのではないでしょうか。
──戦争の早期終結に向けて、ウクライナ側に「妥協」を求める声もあります。
半田 ロシアはウクライナの「非軍事化・中立化」を求めていますが、「NATOに入らない」くらいのことでは、もはや合意は不可能でしょう。プーチンの狙いはゼレンスキー政権を倒してウクライナに傀儡国家を作ることでしょうから、その目的が果たされない限り、ロシアが退く可能性はほぼないと思います。ゼレンスキー政権が倒れるか、経済制裁などの結果としてロシアでプーチン退陣を求める声が高まり政権崩壊に至るか、そのどちらかでしか戦争終結はあり得ないのではないでしょうか。国際社会としては、なんとかプーチン退陣のほうが先になるようウクライナを支援するしかないのだと思います。
日本がやるべきは、まず人的貢献でしょう。国際緊急援助隊の医療隊をウクライナに隣接する東欧諸国へ派遣する、医薬品を送る、ポーランドなどで難民支援をしているNGOを政府として支援する……。自衛隊の装備品提供も否定はしませんが、小銃や弾薬など殺傷兵器の提供にまでエスカレートしないよう、注視が必要だと思います。
日本とウクライナとでは、状況が大きく異なる
──さて、ウクライナ侵攻があって以降、ドイツが防衛費の大幅な引き上げを決定するなど、世界的にも軍事力重視の傾向が強まっています。日本でも「軍事力を強化すべきだ」という声をしばしば耳にするようになりました。
半田 今回、国連加盟国の模範となるべき安保常任理事国のロシアが真っ先に国連憲章を破り、隣国に侵攻したわけですから、各国とも軍事費を増大させて守りを固めていこうという流れが出てくるのは、ある程度やむを得ないともいえます。
ただ、冷戦終了後に軍事費を大きく削減したヨーロッパ諸国などと違って、日本はそもそも冷戦後も防衛費は高止まり、特に第二次安倍政権が成立した2012年以降は急速な増額が続いています。ただでさえそうした方向性で進んでいるところに、さらに「軍事力の強化」を進めるのはやり過ぎだと思います。。
「ウクライナのように攻められたら反撃できるよう、憲法9条の改正が必要」だという人もいますが、9条のもとでもこれまでの政府解釈上、自衛戦争は否定されていません。しかも、日米安保条約がある以上、日本が攻撃されれば必ず米軍も出動することになります。
──今回、アメリカはウクライナへの派兵を見送りました。同じように、たとえば台湾有事の際にも米軍は出てこないのでは、という声もあります。
半田 ウクライナについては、バイデン米大統領は昨年12月の時点で「派兵しない」と明言していました。一方で、台湾に対しては「防衛の責務がある」と繰り返し発言しています。それが中国の警戒感を増大させているという問題はあるにせよ、対ウクライナとはまったく違う態度を見せているのは確かです。
ましてや日米安保条約があり、5万人の米兵が駐留する日本が攻められたときに、それを「見捨てる」という選択肢は、アメリカにはないといえます。つまり日本は、侵略を企てる国から見れば、恐ろしく手強い国だということです。
それを、まったく状況の違うウクライナの場合と一緒くたにして人々の不安につけ込み、これまでの政府の憲法解釈も無視して軍事力の増大に向かうなどというのは、火事場泥棒としか言いようがないでしょう。
──ただそうなると、やはり日米安保は重要だということになりますか。
半田 私は、安保条約自体はあっていいと思っています。ただそれは、アメリカの言いなりになるということではありません。政治家には、そのメリットとデメリットをしっかり見据えた上で、日米安保を「一つの知恵」として賢く利用してほしい。かつて戦後日本は「軽武装・経済重視」といって、防衛はもっぱらアメリカに任せて経済に全力投球することで、急速な経済発展を遂げました。そのように、ときには「ずる賢く」立ち回るのも政治だと思うのです。
しかし、近年の日本はそのまったく逆で、アメリカが求めてもいないのにこちらから忖度して動いています。アメリカ製の武器を大量買いしたり、安全保障関連法をつくって集団的自衛権の行使を容認したり……。その一方で、米軍基地や米兵による犯罪はいっこうに減らず、思いやり予算は増額されて、米兵が日本に来るときだけなぜかPCR検査なしでも構わないなどという、めちゃくちゃな状況になっている。そうではなく、日米安保を維持するのならそれをしっかりと利用できるように、政治家にまともな仕事をしてほしいと思うのです。
「核共有」は、意味のない精神安定剤
──ロシアによる「核の脅し」を受けて、日本の一部の政治家からは「非核三原則を見直すべきだ」といった発言も出てきています。
半田 まず認識しておかなくてはならないのは、日本は核不拡散条約(NPT)加盟国であって、「核保有国5カ国以外の国」として核兵器の開発・保有を禁じられているということです。そこを破って世界中から経済制裁を受けているのが北朝鮮ですが、それと同じことをするのか? という話になります。
──安倍元首相などは、自分たちで保有するのではなく、アメリカ製の核兵器を日本に配備して共同運用する「核共有」を検討すべきと主張していました。
半田 「NPT加盟国のドイツやイタリアなども核共有している」といわれますが、実はこれらの国で核共有が始まったのは1950年代。NPTに関する交渉が始まるより前のことです。そして交渉の段階では、核共有についての事実は隠されていました。だから、NPTの解釈上も脱法的な行為であって、すでにNPTに加盟している日本がこれから核共有をしたいと言っても、認める国はないでしょう。
──ドイツやイタリアにおける核共有の事実が明らかになった後、問題にはならなかったのでしょうか。
半田 NPTは平時における条約であって、有事においてはそこまでの効力はない、共有されている核を実際に用いることがあれば、それはもはや有事なんだからNPTには縛られないんだというのがアメリカの主張です。とはいえ、核使用のための訓練などは平時に行うわけで、あまりにも無理のある主張なのですが。
ただ重要なのは、共有されている核は、当然ながらアメリカの許可がないと使えないということ。そしてアメリカが許可することはまずありませんから、結局は「絶対に使えない武器」です。しかも、ドイツやイタリアに配備されているのは旧式の、戦闘機に搭載して投下するタイプの核兵器。制空権を確保していないとほぼ投下は不可能ですが、制空権があるくらい勝っているのなら核兵器なんて使う必要はないわけで、その意味でも「使えない」。だからこそ広島・長崎への原爆投下の後、各国は離れたところからミサイルで撃てる核兵器の開発を目指したわけです。
一方で、核共有している国々、とりわけ第二次世界大戦の枢軸国であるドイツやイタリアが「核開発をしたい」と言い出したときには、「あなたの国にはアメリカの核兵器がすでにあるでしょう」と言って止められる、そういう意味では共有に意味はあるといえます。事実、フランスはド・ゴール大統領の時代に、「アメリカが核使用を認めるとは思えないから、自前の核を保有する」として、核共有に加わることを拒否しました。
こう見てくると、核共有などというのは、何の意味もない安っぽい精神安定剤、お守りに過ぎません。冷戦終了後、カナダやギリシャなど何カ国もが核共有を終了させたことも、それを証明しています。その核共有を今になって日本が、しかも首相経験者が言い出すというのはあまりに愚かで、とても信じられないという思いです。
核兵器禁止条約を起点に、核廃絶の国際世論を
──半田さんは現代ビジネスの記事で、ロシアの「核の脅し」によって各国が「核兵器の復権」に目を向けざるを得なくなった一方、「核の脅しには屈しない」という国際世論を高めることができれば、「核の先制不使用」を国際会議のテーブルの上に載せられるのではないだろうか、と書かれていました。「国際世論を高める」ためには、具体的にどうしていくべきだとお考えですか。
半田 もっとも重要なのは、昨年1月に発効した核兵器禁止条約だと思います。これまで、核軍縮に向けた条約といえばNPTでしたが、核保有国はいっこうに軍縮義務を果たそうとしてきませんでした。そもそも今回「核の脅し」を使ったロシアもNPT加盟国であって、ここでいくら議論したところで、軍縮が進むとは到底思えません。その一方で、草の根の活動によって核兵器禁止条約が生まれ、施行されたことには本当に大きな意味があるし、そこでの議論を世界の主流にしていくべきだと思うのです。
まだ核兵器禁止条約の締結国会議は開催されていませんが、開催されれば国連という世界中が注目する場で、各国が核に対する思いを述べることになります。ウクライナ侵攻の直後に国連総会の緊急特別会合が開かれ、ロシア非難決議が採択されたときのように、そこから国際世論が生まれていく。核が本当に非人道的、犯罪的な兵器だということへの理解が深まり、共有されれば、核を保有すること自体が恥だという意識を広げていくこともできるのではないでしょうか。
その他にも、「東アジア非核会議」といった地域ごとの非核会議を開くなど、非核の方向へ世論を高めていくための方法はたくさんあると思います。ウクライナ問題が少し落ち着いてからでも、改めて核について議論しようという機運を高めていくことが、まず重要ではないでしょうか。
──「核の脅し」を機に、各国が「だからわが国も保有しよう」という方向に行ってしまう可能性もあるけれど、その逆の可能性もあるということですね。
半田 世界中が「わが国も」という方向に行くのなら、いずれはすべての国が核を持たなくてはならないということになります。そうなれば、事故や偶発的な使用がいくらでも起こってくるでしょう。そもそも、すべての国がまともな判断力を持つ指導者のもとにあるとは限らないのだから、あまりにも危険です。
──しかし、その重要な核兵器禁止条約に、日本は参加していないという問題があります。
半田 それは、国内世論を高めていくしかないでしょう。「日本はアメリカの核の傘に入っているから」といいますが、核共有の当事者であるドイツも、メルケル首相退陣後のシュルツ政権がオブザーバー参加を表明しています。そもそも、核自体が「保有しているけど使えない」という矛盾に満ちた存在なのだから、矛盾した行動に見えてもいい。その矛盾も飲み込んだ上で、どうすれば核軍縮を進められるか、議論によって各国間の最大公約数を見いだしていくしかありません。
まして、日本は世界で唯一の戦争被爆国です。その日本が、核に対する矛盾をあらわにしたところで何が悪いのか。もちろんアメリカは条約参加には反対するでしょうが、これはわが国の主権の問題です。反対を押し切って参加したからといってアメリカが、自分たちにとってのメリットも多い安保条約を一方的に破棄するとも思えません。
──ありがとうございます。最後に、先ほども少し触れていただきましたが、ウクライナ侵攻を機に、改めて求める声が高まっているように思える「憲法9条改正」についてもう一言お願いします。
半田 現状でも自衛の戦争は可能だというのが政府解釈なのだから、自衛のための改憲の必要はないということはすでにお話ししました。それでも9条を変えるというのならそれは、日本を「戦争を仕掛ける国」に変えるということ。つまり、今プーチンがやっていることをできるような国にするということです。
9条があることで、仮にプーチンのような政治家が出てきても、日本は他国に侵略できないという歯止めがかかっている。その歯止めをなくしてしまっていいのでしょうか、ということだと思います。(構成・仲藤里美)
*
はんだ・しげる●1955年(昭和30)年生まれ。防衛ジャーナリスト。元東京新聞論説兼編集委員。獨協大学非常勤講師。法政大学兼任講師。防衛省・自衛隊、在日米軍について多くの論考を発表している。2007年、東京新聞・中日新聞連載の「新防人考」で第13回平和・協同ジャーナリスト基金賞(大賞)を受賞。著書に、『変貌する日本の安全保障政策』(弓立社)、『零戦パイロットからの遺言-原田要が空から見た戦争』(講談社)、『日本は戦争をするのか-集団的自衛権と自衛隊』(岩波新書)、『僕たちの国の自衛隊に21の質問』
今朝、除雪車が入りました。
江部乙高速道路脇の道も除雪され車が通れるように。
今日もこれ。

















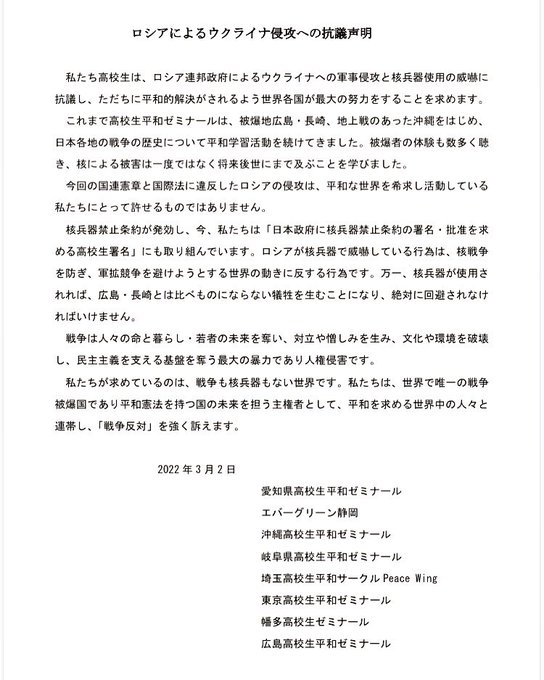







 この木で3年分くらい(?)の薪ができる。
この木で3年分くらい(?)の薪ができる。






