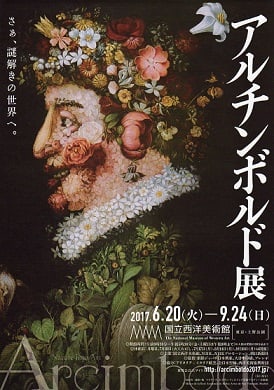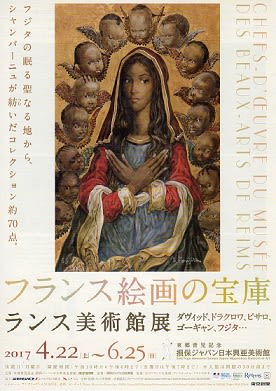東京都美術館で開催中の「ボストン美術館の至宝展」。もう、行きました?ボストン美術館の名品がいっぱいで、ファンはうっとり。
注目は、ポスターの『郵便配達人 ジョゼフ・ルーラン』(1888年)と『子守唄、ゆりかごを揺らす オーギュスティーヌ・ルーラン夫人』(1889年)。
作者はフィンセント・ファン・ゴッホ(1853~1890年)。日本でもたくさんのファンがいます。1886年、パリにやって来たゴッホは…
日本の浮世絵に出会います。他の印象派の画家と同様に、様々な影響を受けたゴッホの作品には、びっくりするくらい目を見張る作品が!
これまでの展覧会でも来日したことがありますが、この秋の展覧会は必見です。それが「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」です。
構成は、第1部/ファン・ゴッホのジャポニスム、第2部/日本人のファン・ゴッホ巡礼。本展はオランダ、アムステルダムにある…
ファン・ゴッホ美術館とのプロジェクトで、終了後、ファン・ゴッホ美術館でも開催されます。ポスターの絵は、『花魁(溪斎英泉による)』(1887年)。
そして影響を受けた、溪斎英泉作『雲龍打掛(うんりゅううちかけ)の花魁』や龍明作『芸者と富士』(1870年代) ← 鶴の元絵。
歌川芳丸作『新板虫尽(しんぱんむしづくし)』(1883年) ← 蛙の元絵。いくつかの作品からモチーフを得ているのがよくわかります。
初公開の『雪景色』『タラスコンの乗合馬車』『夾竹桃と本のある静物』(1880年)、『ポプラ林の中の二人』(1890年)もお見逃しなく!
注目は、ポスターの『郵便配達人 ジョゼフ・ルーラン』(1888年)と『子守唄、ゆりかごを揺らす オーギュスティーヌ・ルーラン夫人』(1889年)。
作者はフィンセント・ファン・ゴッホ(1853~1890年)。日本でもたくさんのファンがいます。1886年、パリにやって来たゴッホは…
日本の浮世絵に出会います。他の印象派の画家と同様に、様々な影響を受けたゴッホの作品には、びっくりするくらい目を見張る作品が!
これまでの展覧会でも来日したことがありますが、この秋の展覧会は必見です。それが「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」です。
構成は、第1部/ファン・ゴッホのジャポニスム、第2部/日本人のファン・ゴッホ巡礼。本展はオランダ、アムステルダムにある…
ファン・ゴッホ美術館とのプロジェクトで、終了後、ファン・ゴッホ美術館でも開催されます。ポスターの絵は、『花魁(溪斎英泉による)』(1887年)。
そして影響を受けた、溪斎英泉作『雲龍打掛(うんりゅううちかけ)の花魁』や龍明作『芸者と富士』(1870年代) ← 鶴の元絵。
歌川芳丸作『新板虫尽(しんぱんむしづくし)』(1883年) ← 蛙の元絵。いくつかの作品からモチーフを得ているのがよくわかります。
初公開の『雪景色』『タラスコンの乗合馬車』『夾竹桃と本のある静物』(1880年)、『ポプラ林の中の二人』(1890年)もお見逃しなく!