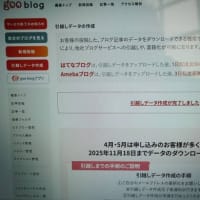新年度の4月入りとなれば我家の飾りつけも端午の節句バージョンとなります、お雛様の時よりは少ないものの玄関と居間食堂に、今年は長男が子供の時に飾っただけで20年以上お蔵入りだった兜も引っ張り出してきて、こんなに大きかったかなぁと置く場所に困ってしまって、冒頭写真のお雛様バージョンからのままでいいかとしていた場所に入れ替えることに、市松人形は仕舞って兜がいっぱいいっぱいに占拠することとなりました。
玄関正面の時代箪笥の上に配したこの兜飾りは女房の両親が長男の誕生祝に買ってくれたもの、中学校ぐらいまでは毎年飾っていたが、その後は天井裏納戸に仕舞いっ放しだったものを出してきて、本当は孫の祝いになればいいんだけどねぇ。隣の日向延岡の郷土玩具ののぼり猿も菖蒲の絵の幟があるように端午の節句用ですね。

上の飾りの隣にある奥への通路入口には目隠しの暖簾をかけるようにしていて、この時期は鯉図の藍染を、これは益子の日下田藍染工房の先代のもので、今では作っていないみたい、厚手でシッカリした布地ですよ。

玄関のもう一ヶ所の飾り棚には土人形をいくつか、天神様と鯛乗り恵比須はご愛敬で。

居間の窓辺には吊るし雛は残したままで和紙の鯉登り飾りを、今は子供の日として女の子も参加していいでしょうと。

居間の階段箪笥の上には下の方4段に端午の節句らしい飾りつけを、その上は干支の人形やミニドールなどを仕舞うのが面倒なのでそのままに。一番下の2体の土人形は何か分かりますか、神功皇后と赤ちゃんの応神天皇を抱く武内宿祢です、その上は金太郎と山姥でいずれも庄内土人形で山形に旅行した時に安く買ってきたもの。ほかも武者人形などの郷土玩具などと小物をいろいろと、この場所は折々に飾り物をとっかえひっかえして楽しむことにしているんです。

食堂の食器棚の中間の飾り棚も壁まで利用して飾りつけ、鋳物の兜は大昔に家にあったものが天井裏から出てきて、でも一部がなくなっていましたがそれなりに飾りにはなるからと、でも重いですよ。

ほかにも武者絵の幟旗がひとつあるのだが飾る場所が無くて、まぁお雛様よりは地味ながら、らしくはなっているでしょう。