






「おかしゃんね、時々(ほんの時々)、突然熱くなるんらよね
 ほら、どこかへ行っちゃったろ
ほら、どこかへ行っちゃったろ 」
」
 先日、京都滋賀旅行の記事の中で町田久成のことに少し触れたのですが、何故お墓詣りにまで参じたのか、上手にまとめることができないので
先日、京都滋賀旅行の記事の中で町田久成のことに少し触れたのですが、何故お墓詣りにまで参じたのか、上手にまとめることができないので 順番にお話しさせて下さい
順番にお話しさせて下さい )
)事の起こりは・・・・先々月、お茶の先生から薩摩藩英国留学生の記念館に行かれて感激したお話を伺ったこと。 ちょうど翌日は紅福父もお休みだったのでドライブがてら行ってみることに
 京都・滋賀旅行の約一ヶ月前の話です
京都・滋賀旅行の約一ヶ月前の話です
串木野羽島・・静かな漁村の一画に立派な記念館ができていました。その時の私の薩摩スチューデントに関する知識と言えば、「薩英戦争後、薩摩藩の命を受けた若き藩士たちが英国近代技術を学ぼうと「国禁を犯して」渡英し、後に各方面で日本の近代化に大きく貢献したと言うこと。 留学生たちの中には初代文部大臣の森有礼、大阪の経済に貢献した五代友厚、後にカリフォルニアのワイン王と呼ばれた長沢鼎らがいた」 これくらい
 町田久成と言う名前はこの記念館に行って初めて知ることになります
町田久成と言う名前はこの記念館に行って初めて知ることになります

館内には一人一人の経歴が紹介されていてとても興味深かかったですよ

この写真の左奥に町田久成の肖像画が展示されていました。 ドキッ
 見た瞬間に心が捕らえられました
見た瞬間に心が捕らえられました 眼光鋭くとてもご立派なお顔(今言葉で言うイケメン系
眼光鋭くとてもご立派なお顔(今言葉で言うイケメン系 )
) 見ると横に三井寺住職と書いてあるではありませんか
見ると横に三井寺住職と書いてあるではありませんか 三井寺と言えば(この時点で)これから私達が訪れるお寺
三井寺と言えば(この時点で)これから私達が訪れるお寺 何と言う偶然
何と言う偶然 (偶然その1)
(偶然その1) 資料を読むと初代国立博物館の館長と書いてあります。まあ、こんな方がいらしたのね
 恥ずかしい~知らなかった~
恥ずかしい~知らなかった~ でもどうして出家されたんだろう????
でもどうして出家されたんだろう???? 
さて、こちらが薩摩スチューデントの写真です。 町田久成は左のグループの真ん中に座っている方です。

町田久成に気持ちを残したまま、館内を巡り、二階のデッキへ
二階は船のデッキを模して作られています。

見つかれば死罪になるかも知れない。・・そんな危険を冒しながらも強い使命感と冒険心に燃えて皆ここから旅立ったのですね。
この時町田久成は28歳。 長沢鼎はなんとわずか13歳です


この地で息を潜めて2ヶ月待機しての渡英・・・・一人一人の気持ちを考えると感慨深いものがあります。

帰ってからも町田久成が気になってをネットで検索
 この続きは
この続きは ブログの最後に載せますのでご興味のない方はスルーして下さいね
ブログの最後に載せますのでご興味のない方はスルーして下さいね
「 ぼくは興味ないれす
 」
」
それはそうらよね

 おまけ
おまけ

 いつかの晩ご飯・・・牡蠣フライとイカのお刺身と湯豆腐
いつかの晩ご飯・・・牡蠣フライとイカのお刺身と湯豆腐 
ポテトサラダは以前ご紹介した黄爵で作ってみました

ずっと下
↓
↓
↓
まだまだ
↓
↓
 ご興味のない方はスルーして下さいね
ご興味のない方はスルーして下さいね
ネットで町田久成を検索すると・・・・・これが実に面白いんです
 「生まれは島津一門三大名家の生まれ。学問を好み、書をよくし雅楽をたしなむ侍、官僚にして文化人。」ほお~
「生まれは島津一門三大名家の生まれ。学問を好み、書をよくし雅楽をたしなむ侍、官僚にして文化人。」ほお~ 「28歳で
「28歳で の監督役として渡英。 帰国後は政界の中心で活躍するも、当時の複雑な情勢に巻き込まれ左遷とも言える文部省へ飛ばされる」
の監督役として渡英。 帰国後は政界の中心で活躍するも、当時の複雑な情勢に巻き込まれ左遷とも言える文部省へ飛ばされる」  なんと
なんと 「が、英国留学中にしばしば訪れた大英博物館のような博物館を作りたいとの信念に基づき、実にさまざまな、さまざまな、さまざまなな困難を経て、明治15年悲願の国立博物館の完成を見る」
「が、英国留学中にしばしば訪れた大英博物館のような博物館を作りたいとの信念に基づき、実にさまざまな、さまざまな、さまざまなな困難を経て、明治15年悲願の国立博物館の完成を見る」 が
が 「同年いろいろいろいろあって罷免」 え~~
「同年いろいろいろいろあって罷免」 え~~ 「その後農商務大書記官や元老院議官などを歴任 明治22年52歳の時出家。」 どうしてどうして? 「59歳、上野の韻松亭で亡くなる。」
「その後農商務大書記官や元老院議官などを歴任 明治22年52歳の時出家。」 どうしてどうして? 「59歳、上野の韻松亭で亡くなる。」韻松亭
 偶然にも数日前、関東の友人から聞いていた名前でした!上野に素敵な懐石料理のお店があってお食事したよ、と。古い日本家屋でとても落ち着いた佇まいだったよ、と。もうびっくり
偶然にも数日前、関東の友人から聞いていた名前でした!上野に素敵な懐石料理のお店があってお食事したよ、と。古い日本家屋でとても落ち着いた佇まいだったよ、と。もうびっくり (偶然その2) 偶然が2回も続くと単純な紅福母、「これは何かのご縁だ!」と思ってしまった訳です
(偶然その2) 偶然が2回も続くと単純な紅福母、「これは何かのご縁だ!」と思ってしまった訳です もっと知りたくてアマゾンで町田久成に関する本を検索して注文しました
もっと知りたくてアマゾンで町田久成に関する本を検索して注文しました
あったのはこの中古の本・・・なんと1円
 しかも帯付きで綺麗な状態です
しかも帯付きで綺麗な状態です (←これは町田久成様からの贈り物に違いないと思いこんでる紅福母)
(←これは町田久成様からの贈り物に違いないと思いこんでる紅福母)
この本は博物館の成り立ちとそれに関わる人々に関して書かれた本ですが、筆者の町田久成への思いが随所に感じられます。
「いまに残る東京国立博物館の膨大なコレクションは、急激な明治の欧風化と開発の波の中で、町田久成が守り抜いた日本人の大きな遺産でもある。そこには博物館づくりを通して、新興日本の国威と特色ある民族の伝統を欧米に示したいとする、若い町田久成の熱い思いが込められている」 (序文より)
読み進めると、博物館の完成までがどんなに困難な道だったのか、そして町田久成の貢献がどんなに大きかったのかが分かります。特に印象に残っているのがこのくだり。
「幕末から明治初年にかけて、・・・、神道の国教化をすすめる神仏分離の政策が・・やがて破壊的な様相を見せてきた。」(いわゆる廃仏毀釈です。)「破壊はまず比叡山の麓から始まり、火の手はまたたくまに全国に広がった。」「・・・神職者たちが境内の社殿に流れ込み、祭壇にまつってあった仏像や仏具をことごとく持ち出して焼き払った・・」
「町田久成は荒廃している全国の社寺の宝物を調査し、調査した古希旧物(歴史的文化財)を保護するために「古希旧物保存方」と名付けた文化財の保護法の制定と、保護した文化財を保管して展示するための「集古館の建設」を移送具用太政官に求めた」
「今でこそ、正倉院や法隆寺と言えば、日本を代表する歴史的な文化財の宝庫として、その文化的歴史的価値も十分認識され、管理も行き届いているが、「古器旧物保存法」が制定された明治の始め頃には、まだ僧侶や周囲の人の古文化財に対する関心も薄く、荒れるにまかされていた・・・ 」(本当に
 目も当てられない状態だったようです
目も当てられない状態だったようです )
)もし町田久成が中央に提言していなかったら・・・・、もし文化財がきちんと調査され保護されていなかったら・・・ もっと多くの美しい文化財が失われていたかも知れません
 しかも当時の政府には十分な資金がなく、町田は私財を投じて文化財を買い上げていたとのこと。
しかも当時の政府には十分な資金がなく、町田は私財を投じて文化財を買い上げていたとのこと。面白い話があります
 町田久成は古美術品の購入に金の糸目はつけなかったとのこと
町田久成は古美術品の購入に金の糸目はつけなかったとのこと 。京都御所の宝物調査を行った後、祇園の茶屋井筒屋で遊んだことがあり、芸者福栄が所持する琴(名作)に惚れ込み、幾度も茶屋に通い、琴を譲り受けるため再三交渉したが福栄は応じなかった。この楽器に魅了された町田はあきらめきれず、ついに大金を払って琴を持った福栄を身請けして、琴だけを手元に残したという
。京都御所の宝物調査を行った後、祇園の茶屋井筒屋で遊んだことがあり、芸者福栄が所持する琴(名作)に惚れ込み、幾度も茶屋に通い、琴を譲り受けるため再三交渉したが福栄は応じなかった。この楽器に魅了された町田はあきらめきれず、ついに大金を払って琴を持った福栄を身請けして、琴だけを手元に残したという 嘘のような本当のお話。 町田久成の審美眼と美しい物に対するなみなみならぬ情熱を感じさせるお話です。この情熱があったからこそ博物館が誕生したのですね
嘘のような本当のお話。 町田久成の審美眼と美しい物に対するなみなみならぬ情熱を感じさせるお話です。この情熱があったからこそ博物館が誕生したのですね
まだまだたくさん興味深い逸話がありますが、長くなるので
 最初に私が疑問に思った「何故あの若さで出家を?」のお話を。
最初に私が疑問に思った「何故あの若さで出家を?」のお話を。明治20年12月6日、島津久光が生涯を閉じます。本には「幼年期から50年ほど、主君久光を変わらず支えてきた重臣町田民部(久成)は、俗世における自分の役割もここで終わったとみた」とあります。 「久光の死を見届けた町田久成は奈良で内室の千代を出家させ、久光三回忌の仏式供養にあわせ、明治22年12月1日に滋賀県の園城寺(三井寺)で剃髪。」
薩英戦争、決死の英国留学を経て、時代の大きなうねりの中で、その時その時を精一杯真摯に生き抜いて、悲願の博物館の完成もみた・・侍としての忠義も果たした・・・波乱の人生を生ききった町田久成の心中はきっと穏やかな水の流れのようだったのではないかと思われます。
韻松亭は・・なんと、町田久成が名付け親でした!博物館館長時代に「鐘は上野か浅草か」と唱えられた鐘が松に響くさまを愛でて名付けたのだそうです。 美しい名前ですよね
 韻松亭を滞留所としていたのだそうです。最後の時を思い出深い上野の地で迎えられて本望だったのではないでしょうか・・
韻松亭を滞留所としていたのだそうです。最後の時を思い出深い上野の地で迎えられて本望だったのではないでしょうか・・私達がお詣りした法明院のお墓は歴代の住職たちの無縫塔がならぶ、小さな墓地でした。町田久成のお墓も他の住職たちと同じ小さな塔で、よく見ないと名前すら読み取れないほど。でもその小ささがかえって心に迫りました。ひっそりと目立たぬように。名も残さずに。 ああでも、私達に遺して下さったものの何と大きなことか・・・・・心から「ありがとうございました」と手を合わせました。 2つの偶然がなければ、三井寺に行っても鐘を撞いて帰って来ただけだったかも知れません
 この歳になって、郷土の偉人の一人にこんな方がおられと知ることが出来て幸いです
この歳になって、郷土の偉人の一人にこんな方がおられと知ることが出来て幸いです
 (ふつふつ・・・心に沸き立つ願望の音
(ふつふつ・・・心に沸き立つ願望の音 次は上野の博物館と韻松亭に行きたいろ~
次は上野の博物館と韻松亭に行きたいろ~ )
)長くなりました
 こんなところまでおつきあい下さり本当にありがとうございました
こんなところまでおつきあい下さり本当にありがとうございました




















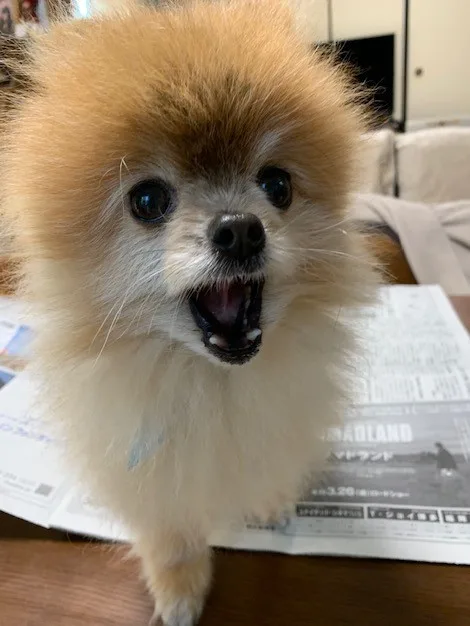



町田久茂どんのお名前は紅福母さんのブログ記事で知ったうつけものの
国立博物館ファンなので早速、興味を持って調べたところ、1円の新書を紅福母さんが買われた後には794円+送料から、というのしか残ってないれすけろけろ
あっ、串木野の記念館で運命の出会いをなさったのですね。私も行ってみたいところです。
串木野ならナビの指示に従って行けるかな~行ってみようかな~ (鹿児島)市内の友達と行く機会があったのですが、彼らと合流してって考えたら余分な時間がかかるから断っちゃったんですよね。
おひとりさまで行ってみようかな~
ええ~
串木野にある記念館は是非是非行って頂きたいです
一人の方がじっくり見られるかも知れません
今日も紅と福になでなで&投げチューありがと~