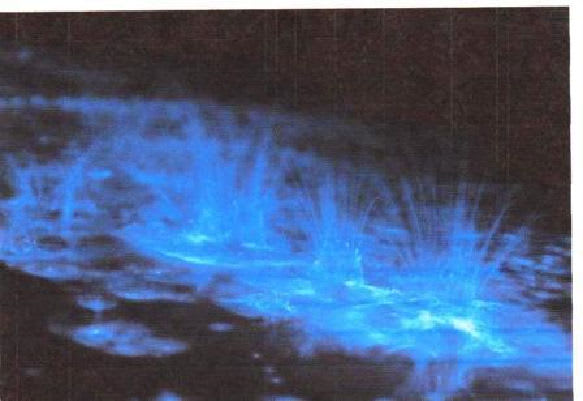9月29日( 日)、第4回鏡川こども祭 沢山の親子でにぎわいました。天気にも恵まれて、昨年を大きく上回る、2千数百人の親子で、鏡川トリム公園が膨らんでおりました。
毎回好評の川の生きものさがしや、アユ1000匹のつかみ取り、水切り大会など、川の中で遊ぶお楽しみのメニューが沢山あり、ずっと川から離れない子どもや ものづくりのブースで竹とんぼや間伐材で森の動物づくり、マイハシづくりなど・・・どのブースも大盛況でした。
遊びのコーナーでは、竹馬に挑戦したり、高知工科大生が指導するジャクリングや、金ちゃん工房の木のおもちゃには長い列が出来ていました。
今回も参加してくれた皆さんに感謝を込めて、取り組み内容を連載していきますので、よろしくお願いします。
その1 オープニング

1回~3回まで司会を担当してくださっていた浜田道雄先生(元・市内中学校の校長)が、今回は所要で参加できず、急きょ岩崎弥太郎こと、元キリンビール高知支社長の宮本典晃さんと、高知大好き!乙女ねーやんの武内妙さんが担当してくれました。参加者が多くて大変な中、絶妙なお二人のコンビで、実にスムーズにプログラムを流していただき、お陰様で最後まで盛り上がりました。


実行委員長・森田俊彦さんの、開会宣言です。

主催者を代表して、鏡川漁協の高橋徹組合長が挨拶しました。


地元旭地区の93町内会を代表して、旭地区町内会連合会の 井上会長より、歓迎のあいさつがありました。

高知市環境部長の黒田さんからも、ご挨拶がありました。
元鏡村村長の川村貞夫さんや、高知市環境政策課長の氏原さんが紹介されました。

今回の第4回こども祭から事務局長に就任した、地元町内会長の菅井清次さん(旭地区安全推進協議会事務局長)より、注意事項とキャラクター名の募集などのお知らせがありました。


地元、旭子どもよさこい「はっぴーぼいす」のよさこい披露です。

今年も元気に踊ってくれました。


つづいて、タツヤスファンクダンスクルーのダンス披露です。

踊が好き!! と身体全体で主張しているような、そんな子ども達が日ごろの練習の成果を披露してくれました。