FOSS4Gシドニーも二日目。今朝の基調講演で、「あ、これはFOSS4Gでしか得られない体験だ」と思うことがあった。ちょうどGoogleのシドニーオフィスのメンバーによる講演と、NSWの大学教授であるAndy Pitmanによる地球規模の気候変動に関する講演を続いて聞いてそう感じたのだ。
前者は、GoogleMapsとGeoLocatioAPIの話。5月のWhere2.0で聞いていたこともあるので新鮮味に欠けていることもあるが、多様な地理的なデマンドをリードする気迫はどうにも感じられなくて、拍手も少ない。一方、Andyの講演は、アカデミックな分野が、どれだけオープンソースコミュニティに期待をしているかをひしひしと感じさせるもので、盛大な拍手に包まれた。気候モデリングのソフトが、アメリカを除くと皆ソースコード非公開で、それぞれの政府機関が独自に持っているらしい。ソフト開発が本業でない彼らにとって、メンテナンスも大変で、バグも多くて困っているそうだ。
(ところで、気候モデリングのソフトがFORTRAN66で書かれているのには驚き、さらに会場参加者の3割くらいがFORTRANを知っているのも驚いた;そういう人はおじさんばかりだけど)
Googleは情報を(地理的にも)整理する会社、我々が直面する問題を解決する会社ではない。
FOSS4Gは、多様なGeoSpatialな課題を解決するためのソフトウェアツール群とそれを支えるコミュニティからできている。FOSS4Gは、利用者にシリアスなアカデミック界を抱えている。それぞれの専門領域の、しかもそれぞれが真剣な要求である。そうした要求にFOSS4Gコミュニティが、一つ一つ地道に応えてきたからこそ、今日のような地位が築かれたのだ。
FOSS4Gコミュニティは、アカデミック界そのものではない。しかも、単なるITディベロッパーでもない。どちらかというと、ソフトウェアディベロッパーに近いスキルを持っているが、多様なGeoSpatialな課題をそれぞれの立場から理解していることが特徴である。OSGeo財団は、それぞれがニッチなGeoSpatialなコミュニティの集合体である。そして「ベンダー」と「ユーザー」に分かれることもない。この世界には「ユーザー会」とか「ユーザーカンファレンス」はないのだ。誰もが制限無くソースコードにアクセスできるし、意見を言えるし、質問をできるし、普及を支援することができる。
私は改めて、FOSS4Gコミュニティは今後も”多面的”に発展することを強く確信した。なぜならば、多様なGeoSpatialな課題に応えられるのはこのコミュニティしかないからだ。
ところで、嘉山さんのブログによると、国内のGIS専門家でもまだFOSS4Gについて知識のない人がまだまだいるらしい。これはとても残念だが、我々の普及活動がまだまだとても足りないのだと思う。FOSS4Gでしか得られない体験を、少しでも他の人と共有できるようにしなければならない。
何はともあれ、11月はじめのFOSS4G Tokyo/Osakaにお越しください。ハンズオンセッションも募集中です。
前者は、GoogleMapsとGeoLocatioAPIの話。5月のWhere2.0で聞いていたこともあるので新鮮味に欠けていることもあるが、多様な地理的なデマンドをリードする気迫はどうにも感じられなくて、拍手も少ない。一方、Andyの講演は、アカデミックな分野が、どれだけオープンソースコミュニティに期待をしているかをひしひしと感じさせるもので、盛大な拍手に包まれた。気候モデリングのソフトが、アメリカを除くと皆ソースコード非公開で、それぞれの政府機関が独自に持っているらしい。ソフト開発が本業でない彼らにとって、メンテナンスも大変で、バグも多くて困っているそうだ。
(ところで、気候モデリングのソフトがFORTRAN66で書かれているのには驚き、さらに会場参加者の3割くらいがFORTRANを知っているのも驚いた;そういう人はおじさんばかりだけど)
Googleは情報を(地理的にも)整理する会社、我々が直面する問題を解決する会社ではない。
FOSS4Gは、多様なGeoSpatialな課題を解決するためのソフトウェアツール群とそれを支えるコミュニティからできている。FOSS4Gは、利用者にシリアスなアカデミック界を抱えている。それぞれの専門領域の、しかもそれぞれが真剣な要求である。そうした要求にFOSS4Gコミュニティが、一つ一つ地道に応えてきたからこそ、今日のような地位が築かれたのだ。
FOSS4Gコミュニティは、アカデミック界そのものではない。しかも、単なるITディベロッパーでもない。どちらかというと、ソフトウェアディベロッパーに近いスキルを持っているが、多様なGeoSpatialな課題をそれぞれの立場から理解していることが特徴である。OSGeo財団は、それぞれがニッチなGeoSpatialなコミュニティの集合体である。そして「ベンダー」と「ユーザー」に分かれることもない。この世界には「ユーザー会」とか「ユーザーカンファレンス」はないのだ。誰もが制限無くソースコードにアクセスできるし、意見を言えるし、質問をできるし、普及を支援することができる。
私は改めて、FOSS4Gコミュニティは今後も”多面的”に発展することを強く確信した。なぜならば、多様なGeoSpatialな課題に応えられるのはこのコミュニティしかないからだ。
ところで、嘉山さんのブログによると、国内のGIS専門家でもまだFOSS4Gについて知識のない人がまだまだいるらしい。これはとても残念だが、我々の普及活動がまだまだとても足りないのだと思う。FOSS4Gでしか得られない体験を、少しでも他の人と共有できるようにしなければならない。
何はともあれ、11月はじめのFOSS4G Tokyo/Osakaにお越しください。ハンズオンセッションも募集中です。










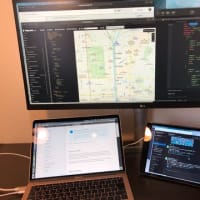
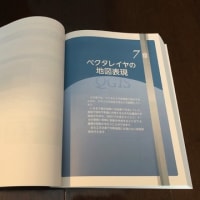
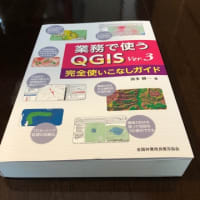







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます