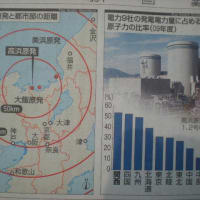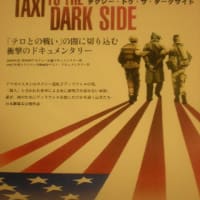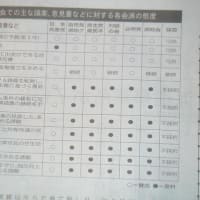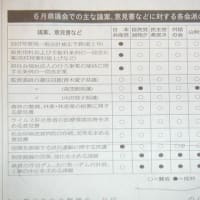先月(2月)、米原市内で開かれた解放研究第14回県集会に出席し、解放同盟県連の建部五郎委員長(58)と知り合った。大阪市の「飛鳥会」事件、奈良市職員の長期休職問題など解放運動にとって“逆風”とも言える不祥事が明るみに出る中、建部委員長は信頼回復への決意を語るとともに、マスコミに解放運動の取り組みの必要性を訴えた。そこで建部委員長に、運動にかける思いなどを語ってもらった。(石井裕之)
《解放運動にかかわったきっかけを教えてください》
20歳の時、父親が病気になったので大阪の会社を辞めて帰郷し、運動に参加しました。県連の初代委員長だった上田一夫さん(故人)が同じ地区の出身で、当時の厳しい差別の中で信念をもって活動され、あこがれがありましたから。学校では同和教育を一度も受けていなかったので、差別と闘う偉大な先輩がいなかったら、丑松(うしまつ)(島崎藤村作「破戒」の主人公)になっていたかもしれませんね。
《大阪や奈良、京都で不祥事が相次ぎました》
同和問題の解決に、真剣に取り組んでくれている多くの人々の信頼を裏切り、失望させ、本当に申し訳ないという思いです。同和事業は、あくまで差別をなくすための手段なのですが、目的と勘違いした人たちがいるということです。一方で、今回の不祥事は、行政などから「相手がうるさいから」という目で見られていた結果。そうした点では、これまでの同和行政のあり方を見直していく必要があります。
「人の世に熱あれ、人間に光あれ」と人間の尊厳を訴えた宣言。そこに立ち返る。そういう意味で今回の不祥事を教訓に、このピンチを信頼回復のチャンスにしたいと考えています。
《具体的な方策は》
同和問題を悪用して利権を得ようとする「エセ」の防止対策本部を発足させました。不祥事以来、「うわさが出た段階で迅速に対処する」という考えになっています。これは中央本部の方針でもあり、今年1月には、中央のオルグが県連に入り、「活動状況や課題について」や「エセ行為がないか」など、組織改革に向けた総点検を実施しました。
《逆に、運動の成果として訴えたいことは》
最初は同和対策として出発した制度が、全体に浸透したことです。例えば、就職差別に対する取り組みの中で、履歴書などに本籍や家族の学歴、職業などを書かなくてよくなったこと。就職は、あくまで本人の職業能力です。これによって、就職差別を防ぐことなどに役立っています。
《差別問題については「知ってしまうから意識する」という考えが根強くありますが》
いわゆる「寝た子を起こすな論」ですね。それに対しては、最近こう言っているのです。「職場の仲間や学校の友人など、周りで人権問題や差別で苦しんでいる人がいることを知らない方がいいと思う?」と。差別というのは、している側は気付かなかったら不都合はないかもしれないが、される方にとっては時には死を選ぶほどの苦痛なんです。そうした苦しみを知らないでいいはずがないでしょう。
《今後の抱負は》
人権問題は問題だけでなく、女性問題や障害者問題など様々に存在します。そうした問題をもっとお互いが勉強して日本を人権立国にし、人権文化というものを根付かせたい。理想とするのは、人々が安心・安全に暮らせること。その原点には、人間の尊厳を守るという思想がある。解放同盟がその火付け役となり、さまざまな差別撤廃の原動力になりたいですね。
■1968年、解放同盟県連呉竹支部の青年部入りし、支部書記長、支部長などを歴任。2002年10月、5代目の県連委員長に就任した。解放運動の傍ら、地元・甲良町呉竹で「村づくり委員会」の仲間たちと「人権・自然・環境」「自立・交流・協働の汗」を合言葉に清掃活動や公園整備、梅の生産、コイ放流などに取り組んでいる。座右の銘は「不屈献身」。上田委員長が「報いられるを期待せぬ愛情と献身」、4代目の村田良一委員長が「屈しない強い信念」を信条とし、同じ地元出身の両先輩の薫陶を受けたことから、その思いを受け継いだ言葉という。
(3月26日付け読売新聞が報道)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shiga/news001.htm