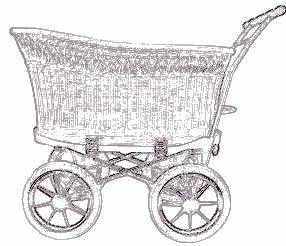今思い出しても自分のバカさに悔いることがあります。レインコート遺失です。中1のときに起きました。その後だれにもしゃべっていない、恥ずかしくもあることです。
朝から雨が降りそうな日でした。かあちゃんにレインコートを持たされて登校しました。そのころは電車通学をしていました。幸い、あるいは不幸にも帰りも雨は降りませんでした。
レインコートを大事に脇に挟んで持っていました。このレインコートはかあちゃんがわたしの小学校入学前に買ってくれたものです。かあちゃんは目先が利くのか、入学の服も早く買ってくれていました。
当時は電車の運行数は少なく、乗客は多かったです(この時間の乗客はほとんど中学生でした)。
電車がホームに入ってきました。みな乗降口に群がりました。小さいわたしは押しに押されて、電車に乗られたのはいいのですが、レインコートを線路に落としてしまいました。
電車はそのまま発車します。次の駅まで身動きできませんでした。
わたしが降りるのは次の駅です。
ほんとにバカです。駅員さんに届けることも乗車駅に引き返すこともなく、家へ帰りました。
かあちゃんからはレインコートはどうしたか、しっこく聞かれました。このころレインコートは貴重品でした。買おうとしても買えなかったと思います。
わたしはだんまりを続けました。
かあちゃんは腹を立て、叱りました。時計を壊した時よりも叱られました。それでも、わたしはだんまりを続けました。
駅に届けたらもしかしたらコートは帰ってきたかもしれません。でも、それもしませんでした。
最近、ある所に傘を忘れました。数日してそこに行くと傘は無くなっていました。だれかが差して帰ったようです。それをカミさんに言うと「なんで責任者に言わんと、いちばんよか傘じゃったとに」と責められました。
今でも脳の回転が悪いのです。
朝から雨が降りそうな日でした。かあちゃんにレインコートを持たされて登校しました。そのころは電車通学をしていました。幸い、あるいは不幸にも帰りも雨は降りませんでした。
レインコートを大事に脇に挟んで持っていました。このレインコートはかあちゃんがわたしの小学校入学前に買ってくれたものです。かあちゃんは目先が利くのか、入学の服も早く買ってくれていました。
当時は電車の運行数は少なく、乗客は多かったです(この時間の乗客はほとんど中学生でした)。
電車がホームに入ってきました。みな乗降口に群がりました。小さいわたしは押しに押されて、電車に乗られたのはいいのですが、レインコートを線路に落としてしまいました。
電車はそのまま発車します。次の駅まで身動きできませんでした。
わたしが降りるのは次の駅です。
ほんとにバカです。駅員さんに届けることも乗車駅に引き返すこともなく、家へ帰りました。
かあちゃんからはレインコートはどうしたか、しっこく聞かれました。このころレインコートは貴重品でした。買おうとしても買えなかったと思います。
わたしはだんまりを続けました。
かあちゃんは腹を立て、叱りました。時計を壊した時よりも叱られました。それでも、わたしはだんまりを続けました。
駅に届けたらもしかしたらコートは帰ってきたかもしれません。でも、それもしませんでした。
最近、ある所に傘を忘れました。数日してそこに行くと傘は無くなっていました。だれかが差して帰ったようです。それをカミさんに言うと「なんで責任者に言わんと、いちばんよか傘じゃったとに」と責められました。
今でも脳の回転が悪いのです。