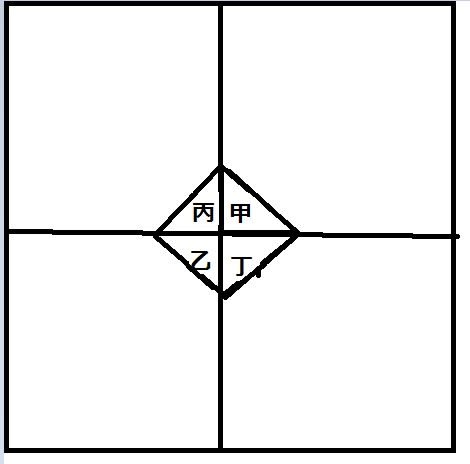国道沿いにあるちゃんぽんやで昼食を食べました。そのあと駐車している車のところへ歩いていると、
「ブォー、ブォー」という鳴き声が聞こえて来ました。
これは確かにあの鳴き声だ。そう思って下水の方へ歩いて行きました。草に覆われた下水がありました。
鳴き声の主はどこにいるかわかりません。この声の主はあまり姿を見せないと聞いています。
そしてこの声の主を食べたことを思い出しました。
泣き声が牛に似ているから(わたしはそう思いませんが)ウシガエルと言います。わたしは1度食べたので食用ガエルと覚えています。
北アメリカの原産で、大正時代に輸入されて各地で繁殖したそうです。
としおじさんの家で、やわらかい肉を食べました。
食べた後で「食用ガエル」と教えられました。
カエル?
吐き出しはしませんでしたが、カエルかと思いました。
わたしのなかにカエルはイボガエルしかありませんでした。川も小川も近くにないので、カエルはほとんど見ませんでした。
町なかのわが家には夏になるとイボガエルが出てきました。下の写真のように全身にイボがあるカエルです。

ワクドとか敬称を付けてワクドサンと呼んでいました。
町なかで見るのはこのワクドサンだけでした。ワクドサンの印象が強くて、ウシガエルはこの時の一口だけです。
それ以後は口にしていません。
「ブォー、ブォー」という鳴き声が聞こえて来ました。
これは確かにあの鳴き声だ。そう思って下水の方へ歩いて行きました。草に覆われた下水がありました。
鳴き声の主はどこにいるかわかりません。この声の主はあまり姿を見せないと聞いています。
そしてこの声の主を食べたことを思い出しました。
泣き声が牛に似ているから(わたしはそう思いませんが)ウシガエルと言います。わたしは1度食べたので食用ガエルと覚えています。
北アメリカの原産で、大正時代に輸入されて各地で繁殖したそうです。
としおじさんの家で、やわらかい肉を食べました。
食べた後で「食用ガエル」と教えられました。
カエル?
吐き出しはしませんでしたが、カエルかと思いました。
わたしのなかにカエルはイボガエルしかありませんでした。川も小川も近くにないので、カエルはほとんど見ませんでした。
町なかのわが家には夏になるとイボガエルが出てきました。下の写真のように全身にイボがあるカエルです。

ワクドとか敬称を付けてワクドサンと呼んでいました。
町なかで見るのはこのワクドサンだけでした。ワクドサンの印象が強くて、ウシガエルはこの時の一口だけです。
それ以後は口にしていません。