
腰を痛めてからもう20日も経つのに未だ完治ではなく曲げ伸ばしがシブイ。
とは言っても余命の少ない爺イにとっては毎日ブラブラ生活は勿体無い。
足慣らしのため、手軽なハイキング。場所は手馴れた中之条・嵩山で序に
上の写真にある33観音巡りを計画。「33」と云うのは法華経の中で観音菩薩が
衆生を救うのに33の姿に変化するという信仰に由来するのだそうだ。
根源は平安期から存在したという「西国三十三所」でこれらの観音菩薩を
巡礼参拝すると現世で犯した全ゆる罪業が消滅して極楽往生出来ると言う物。
尤も爺イには消滅させたい罪業は無い筈だが。この「西国三十三所」とは
何処にあるかと言えば、直ぐに連想される四国ではなく、下図のように
近畿2府4県に跨る33ヶ所の観音霊場である。

これに倣ったのが頼朝の信仰に影響された「坂東33観音」で東京(1)神奈川(9)
埼玉(4)千葉(7)茨城(6)栃木(4)そして群馬は水沢と白岩の(2)で合計(33)。
武家の「坂東33観音」に対して民衆から起きたのが「秩父34観音」、
西国と坂東とを全部併せて「百観音」と言われる。
因みに四国のものは「88観音」である。此れに倣ったのが真言宗の寺が結集した
「関東88観音」で高崎・観音山の慈眼寺を一番として埼玉・妻沼の歓喜院を
結願寺としており、群馬からは15ヶ所の寺が入っている。
この他に「武蔵野33観音」や「ボケ封じ観音」と云われる爺イにはうってつけの
「関東33観音」もあると聞く。この「関東33観音」には群馬では前橋の
東福寺・蓮花院及び新田の全性院の三箇所が含まれている。――閑話休題。
例によって途中で色々と寄り道。勿論、趣味に成ってしまった三角点探訪だ。
中之条の地形図を見ると中之条高校内にアンテナの付いた三角点マークがあるので
一寸見物に。 これは群馬に16個所ある電子基準点と附票の一つなのだ。
爺イは高崎の物にタッチしたことがあるだけなのでこれが二つ目。
16ヶ所とは「高崎・桐生・伊勢崎・沼田・渋川・藤岡・富岡・神流・南牧
中之条・嬬恋・草津・片品・水上(3)。
電子基準点とは全国1200ヶ所に配置された「GPS連続観測点」の事。外見は
高さ5Mのステンレスタワーで上部にGPS衛星からの電波を受信するアンテナ、
内部に受信機と通信用機器を備えている優れもの。その基礎部には
「電子基準点附票」という金属票があつて普通の三角点の役目を負っている。
因みに地形図にはアンテナマークつきの三角点に372.1mと記載されているが
これが附票の標高であり電子基準点はアンテナ高として376.45mとなって居る。
ピラーと云われるここの5mステンレスポールは形状からして「02年型」だ。
全国の物は「93年型」「94年型」「95年型」「02年型」の何れかに属する。
中之条高校正門前に駐車して入り口直ぐ右手の庭園の中。

直ぐ脇に「附票」372.12m N-36-35-28-96 E-138-50-52-4

今度は嵩山の1k手前の道を右折して「中之条総合グランド」、ここの土手にある
三角点は二等の立派な物。何しろ点名が「中之条」なので一寸ご挨拶。


嵩山駐車場は連休明けのためか、空いていた。道路の南側に親都(チカト)神社、
目立つのはご親木とされる「大ケヤキ」で1957年に県指定の天然記念物と
なっている。根元周り15.1m、目通り9.7m、樹高15m。「目通り」とは目の
高さの樹木の直径の事らしい。推定樹齢700年とか。
この他に56本の(杉54本・欅2本)の「神社の境内木」が町指定の天然記念物と
され、この地域の古い歴史の象徴になっている。

登山口に近づくと大きな岩に33観音全ての設置位置が彫り込まれている。(10.48)

入り口は「表登山口」、直ぐに傾斜の厳しい登りになる。

1番観音は右に入つて「雨降り神社」脇。

神社と書かれた標識は山の裏側にあり、振り返ると逆光の中石宮が二つ。

次の2番観音が中々現われない。展望台への道を二つ過ぎると小さい岩場。

岩を越えるとその上が休み石。

直ぐに右手(東)への細道をかなり急降して「こうもり穴」でその中に2番観音。



戻って今度は反対側の細道を進むと3番観音。


登山道の八合目道標を過ぎると右に「八番~十番」の道標に従って右折。
直ぐに八番観音。

少し先の崖の上に九番観音。


次の十番は道標が地面に落ちていたが行き止まりの奥まで探索するも
見つからずに断念。
次ページへ続く
ブログランキングへ一票。
次ページへ続く
とは言っても余命の少ない爺イにとっては毎日ブラブラ生活は勿体無い。
足慣らしのため、手軽なハイキング。場所は手馴れた中之条・嵩山で序に
上の写真にある33観音巡りを計画。「33」と云うのは法華経の中で観音菩薩が
衆生を救うのに33の姿に変化するという信仰に由来するのだそうだ。
根源は平安期から存在したという「西国三十三所」でこれらの観音菩薩を
巡礼参拝すると現世で犯した全ゆる罪業が消滅して極楽往生出来ると言う物。
尤も爺イには消滅させたい罪業は無い筈だが。この「西国三十三所」とは
何処にあるかと言えば、直ぐに連想される四国ではなく、下図のように
近畿2府4県に跨る33ヶ所の観音霊場である。

これに倣ったのが頼朝の信仰に影響された「坂東33観音」で東京(1)神奈川(9)
埼玉(4)千葉(7)茨城(6)栃木(4)そして群馬は水沢と白岩の(2)で合計(33)。
武家の「坂東33観音」に対して民衆から起きたのが「秩父34観音」、
西国と坂東とを全部併せて「百観音」と言われる。
因みに四国のものは「88観音」である。此れに倣ったのが真言宗の寺が結集した
「関東88観音」で高崎・観音山の慈眼寺を一番として埼玉・妻沼の歓喜院を
結願寺としており、群馬からは15ヶ所の寺が入っている。
この他に「武蔵野33観音」や「ボケ封じ観音」と云われる爺イにはうってつけの
「関東33観音」もあると聞く。この「関東33観音」には群馬では前橋の
東福寺・蓮花院及び新田の全性院の三箇所が含まれている。――閑話休題。
例によって途中で色々と寄り道。勿論、趣味に成ってしまった三角点探訪だ。
中之条の地形図を見ると中之条高校内にアンテナの付いた三角点マークがあるので
一寸見物に。 これは群馬に16個所ある電子基準点と附票の一つなのだ。
爺イは高崎の物にタッチしたことがあるだけなのでこれが二つ目。
16ヶ所とは「高崎・桐生・伊勢崎・沼田・渋川・藤岡・富岡・神流・南牧
中之条・嬬恋・草津・片品・水上(3)。
電子基準点とは全国1200ヶ所に配置された「GPS連続観測点」の事。外見は
高さ5Mのステンレスタワーで上部にGPS衛星からの電波を受信するアンテナ、
内部に受信機と通信用機器を備えている優れもの。その基礎部には
「電子基準点附票」という金属票があつて普通の三角点の役目を負っている。
因みに地形図にはアンテナマークつきの三角点に372.1mと記載されているが
これが附票の標高であり電子基準点はアンテナ高として376.45mとなって居る。
ピラーと云われるここの5mステンレスポールは形状からして「02年型」だ。
全国の物は「93年型」「94年型」「95年型」「02年型」の何れかに属する。
中之条高校正門前に駐車して入り口直ぐ右手の庭園の中。

直ぐ脇に「附票」372.12m N-36-35-28-96 E-138-50-52-4

今度は嵩山の1k手前の道を右折して「中之条総合グランド」、ここの土手にある
三角点は二等の立派な物。何しろ点名が「中之条」なので一寸ご挨拶。


嵩山駐車場は連休明けのためか、空いていた。道路の南側に親都(チカト)神社、
目立つのはご親木とされる「大ケヤキ」で1957年に県指定の天然記念物と
なっている。根元周り15.1m、目通り9.7m、樹高15m。「目通り」とは目の
高さの樹木の直径の事らしい。推定樹齢700年とか。
この他に56本の(杉54本・欅2本)の「神社の境内木」が町指定の天然記念物と
され、この地域の古い歴史の象徴になっている。

登山口に近づくと大きな岩に33観音全ての設置位置が彫り込まれている。(10.48)

入り口は「表登山口」、直ぐに傾斜の厳しい登りになる。

1番観音は右に入つて「雨降り神社」脇。

神社と書かれた標識は山の裏側にあり、振り返ると逆光の中石宮が二つ。

次の2番観音が中々現われない。展望台への道を二つ過ぎると小さい岩場。

岩を越えるとその上が休み石。

直ぐに右手(東)への細道をかなり急降して「こうもり穴」でその中に2番観音。



戻って今度は反対側の細道を進むと3番観音。


登山道の八合目道標を過ぎると右に「八番~十番」の道標に従って右折。
直ぐに八番観音。

少し先の崖の上に九番観音。


次の十番は道標が地面に落ちていたが行き止まりの奥まで探索するも
見つからずに断念。
次ページへ続く
ブログランキングへ一票。
次ページへ続く
















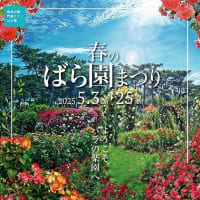



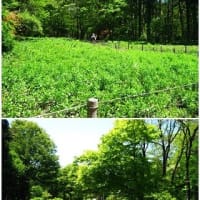





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます