
(16)飯塚町(旧塚沢村)

この標識は広い飯塚町の北端、第一病院西側の旧三国街道の通る小さな
信号に掛かっている。江戸期からの上・下飯塚村は明治22年に他の4ヶ村と
共に塚沢村を形成してその大字となるが、「飯塚駅(現北高崎駅)」より南の
字大橋はこの時、高崎町に編入。飯塚の「塚」と「貝沢」の「沢」で塚沢村。
昭和2年塚沢村は高崎に合併して高崎市大字飯塚、次いで昭和26年に
貝沢・江木・岩押・高関・芝塚町と共に飯塚町成立。35年「飯玉町」
「稲荷町」が独立。
現在、塚沢の名は学校・公民館などに残るのみ。町内、農業神の飯玉神社北の
常福寺辺に1560年頃存在した、和田氏の「上飯塚城」は僅かにその痕跡を
残している。
(17)飯玉町(旧塚沢村)

標識は前橋街道と追川通りの交点。
昭和35年に飯塚町と江木町の一部で成立。町名の「飯玉」は「飯玉神社」の
名前からだが、その神社は飯塚町内。塚沢小・塚沢中・塚沢公民館はこの町。
公民館の庭にある「力石」は90kgと132kgの二つ、大正時代の力比べの道具。
(18)貝沢町(旧塚沢村)

標識は前橋街道と環状線との交叉点。
旧塚沢村の大字、昭和26年の独立。谷地を意味する「貝」と井野川の「沢地」の
「沢」から貝沢とは室町時代からの地名。
環状線近くの「五霊神社」は城の北側にあったものを松平輝貞が鬼門除けとして
ここに移したもの。祭神の「鎌倉権五郎景政」は桓武平氏で平高望の次男・良兼の
4世の孫、現・鎌倉市周辺を領し、源義家に従って1083年の後三年の役に出陣、
右目を射られても奮戦したとの逸話を後世に残した。その三世の孫に
義経の天敵・梶原景時や鎌倉幕府草創期の長老・大場景義がいる。
又、この神社は明治2年の五万石騒動の農民決起場所。
http://blog.goo.ne.jp/gooyamachuu/e/11bd901f73f4e8fbb4fe0d8914059f5d
(19)芝塚町(旧塚沢村)

標識は産業道路と駒形線の交叉点。
芝塚の地名は古く南北朝時代に既に「上野国芝塚郷」の記録が在ると言う。
小字として飯塚町に属していたが昭和26年に江木・高砂の一部と合わさって
芝塚町。「芝」は「草芝」、「塚」は「古墳」から。雑木に被われていない草芝の
古墳が存在したからこの名が附いたという。
(20)井野町(旧中川村)

JR井野駅はこの地名からと理解出来るがそれでは井野川の名は? となると
単純に井野地区を通るからとは片付けられない。何故なら井野川は榛名山から
発して多くの町村を流れて烏川に注ぐが井野町の拘わりはその南端を僅かに
翳めるだけだから。古来、烏川はコースを変更したとはいえ、まさか此の辺まで
北上して居たとは考えられない。
この「井野」は湧水のある低く平らな地形の意味と云われるから、此の辺の
弥生時代の遺構からして流域の中で一番早くから稲作が営まれ人が
住みついたのかもしれない。つまり、流域の中でここだけに人が居て唯一の
地名が在った所か?
(21)日高町(旧新高尾村)

明治22年に新保・新保田中・日高・中尾・鳥羽が合併して新高尾村が
誕生するが中尾の一部と見なされた「鳥羽」は村名に入れなかった。これを
不服として江戸時代の地名を町名とする昭和30年の高崎への吸収の時、
鳥羽は前橋に属するのを選んだ。こんな経緯を持つ地域。
旧道の関越自動車道交叉近くに「「村主神社」があるが「村主」とは古代に半島から
来た智識・文化人に与えられた尊称だから日高遺跡と関連して古代の文化圏
であつたらしい。日高とは神が鎮座する四方が見渡せる所の意味だそうだ。
(22)緑町(旧六郷村)

この標識は高前バイパスと環状線の交叉点にある。昭和41年の高前バイパス、
42年の問屋町誕生(大八木・下小鳥・浜尻・貝沢の一部)、49年環状線全通と
発展して周辺が整備されたが、造成が進んだ昭和55年に「問屋町西」と共に
誕生。新しい町らしく一丁目から四丁目まである。
元は大八木・下小鳥・浜尻・貝沢の一部。県下で「みどり」をつける名は
大間々・東・笠懸の「みどり市」の他にも2箇所ほどあるらしい。
尚、前橋市の問屋町は昭和44年。
(23)大八木町(旧中川村)

緑町の北に位置し、この標識は渋川街道と大八木工業団地から西進する
道との交叉点にある。付近に諏訪神社や妙音寺。八木の地名は1030年頃の
文書に出てくるとの事なので極めて古いがその謂われは不明、八木は
「柳」からとの説があるらしいがあくまでも推論の域を出ないらしい。
鎌倉時代には既に「大」と「小」に分れていたとか。
明治22年に中川村の大字となり昭和30年に全村高崎に合併して大字が町名。
尚、大八木工業団地は昭和36-37年の造成。
(24)小八木町(旧中川村)

大八木町の東北隣、成立は大八木と同じ。北部に旧村名を残す中川小があるが
その向かいに725年の創建と伝わる鏡岩神社があり、6世紀後半の「祭祀巨石」が
ある。その西隣の「妙典寺」には1257年との銘のある「康元の板碑」があり
市の重文指定。詳しくは下記URLをご参考までに。
http://blog.goo.ne.jp/gooyamachuu/e/0cbebea75282e20049d73e3b0e134a32
(25)下小鳥町(旧六郷村)

標識は高渋線と高前バイパスの交叉点、ここは第一病院のある所で町の東南端。
戦国時代は上・下はなく小鳥一つだったが、分割時期の記録はないとの事で不明。
六郷村の形成は明治22年でその大字、昭和26年に高崎市の町。
この地域には1410年銘の石宮のある「幸宮神社」や1704年の供養搭のある
「蓮華院」がある。
(26)上並榎町(旧六郷村)

標識は高前バイパスと通称経大前通りとの交叉点。このバイパスの東が旧市街地の
並榎、西側が旧六郷村の上並榎。地名の興りは並榎と同じ。
かって存在した「稲荷山古墳」は造成用の土砂として切り崩され跡形も無く
出土品の石棺の蓋のみが護国寺の境内西側に置かれている。
http://blog.goo.ne.jp/gooyamachuu/e/cb31271e3dcb8932cc3cda6aa670dcfb
その護国寺は864年の開基、関東一を誇った大伽藍も戦火で焼失。
正面にある小野道風の扁額は勿論レプリカ、本物は寺宝。
経済大学・並榎城址もこの町内。
(27)大橋町

明治18年、信越線が松井田まで開通し「飯塚駅(現・北高崎駅)」が出来た時、
線路によって飯塚村の「字大橋」は分断された。明治22年の高崎町成立時
にはこの分断地は高崎町に編入、大橋町の町名はその13年後。
大橋とは当時から大川と云われた長野堰にかかる橋から名付けられたそうだ。
ジイ散歩第二弾はこれまで。
ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。


この標識は広い飯塚町の北端、第一病院西側の旧三国街道の通る小さな
信号に掛かっている。江戸期からの上・下飯塚村は明治22年に他の4ヶ村と
共に塚沢村を形成してその大字となるが、「飯塚駅(現北高崎駅)」より南の
字大橋はこの時、高崎町に編入。飯塚の「塚」と「貝沢」の「沢」で塚沢村。
昭和2年塚沢村は高崎に合併して高崎市大字飯塚、次いで昭和26年に
貝沢・江木・岩押・高関・芝塚町と共に飯塚町成立。35年「飯玉町」
「稲荷町」が独立。
現在、塚沢の名は学校・公民館などに残るのみ。町内、農業神の飯玉神社北の
常福寺辺に1560年頃存在した、和田氏の「上飯塚城」は僅かにその痕跡を
残している。
(17)飯玉町(旧塚沢村)

標識は前橋街道と追川通りの交点。
昭和35年に飯塚町と江木町の一部で成立。町名の「飯玉」は「飯玉神社」の
名前からだが、その神社は飯塚町内。塚沢小・塚沢中・塚沢公民館はこの町。
公民館の庭にある「力石」は90kgと132kgの二つ、大正時代の力比べの道具。
(18)貝沢町(旧塚沢村)

標識は前橋街道と環状線との交叉点。
旧塚沢村の大字、昭和26年の独立。谷地を意味する「貝」と井野川の「沢地」の
「沢」から貝沢とは室町時代からの地名。
環状線近くの「五霊神社」は城の北側にあったものを松平輝貞が鬼門除けとして
ここに移したもの。祭神の「鎌倉権五郎景政」は桓武平氏で平高望の次男・良兼の
4世の孫、現・鎌倉市周辺を領し、源義家に従って1083年の後三年の役に出陣、
右目を射られても奮戦したとの逸話を後世に残した。その三世の孫に
義経の天敵・梶原景時や鎌倉幕府草創期の長老・大場景義がいる。
又、この神社は明治2年の五万石騒動の農民決起場所。
http://blog.goo.ne.jp/gooyamachuu/e/11bd901f73f4e8fbb4fe0d8914059f5d
(19)芝塚町(旧塚沢村)

標識は産業道路と駒形線の交叉点。
芝塚の地名は古く南北朝時代に既に「上野国芝塚郷」の記録が在ると言う。
小字として飯塚町に属していたが昭和26年に江木・高砂の一部と合わさって
芝塚町。「芝」は「草芝」、「塚」は「古墳」から。雑木に被われていない草芝の
古墳が存在したからこの名が附いたという。
(20)井野町(旧中川村)

JR井野駅はこの地名からと理解出来るがそれでは井野川の名は? となると
単純に井野地区を通るからとは片付けられない。何故なら井野川は榛名山から
発して多くの町村を流れて烏川に注ぐが井野町の拘わりはその南端を僅かに
翳めるだけだから。古来、烏川はコースを変更したとはいえ、まさか此の辺まで
北上して居たとは考えられない。
この「井野」は湧水のある低く平らな地形の意味と云われるから、此の辺の
弥生時代の遺構からして流域の中で一番早くから稲作が営まれ人が
住みついたのかもしれない。つまり、流域の中でここだけに人が居て唯一の
地名が在った所か?
(21)日高町(旧新高尾村)

明治22年に新保・新保田中・日高・中尾・鳥羽が合併して新高尾村が
誕生するが中尾の一部と見なされた「鳥羽」は村名に入れなかった。これを
不服として江戸時代の地名を町名とする昭和30年の高崎への吸収の時、
鳥羽は前橋に属するのを選んだ。こんな経緯を持つ地域。
旧道の関越自動車道交叉近くに「「村主神社」があるが「村主」とは古代に半島から
来た智識・文化人に与えられた尊称だから日高遺跡と関連して古代の文化圏
であつたらしい。日高とは神が鎮座する四方が見渡せる所の意味だそうだ。
(22)緑町(旧六郷村)

この標識は高前バイパスと環状線の交叉点にある。昭和41年の高前バイパス、
42年の問屋町誕生(大八木・下小鳥・浜尻・貝沢の一部)、49年環状線全通と
発展して周辺が整備されたが、造成が進んだ昭和55年に「問屋町西」と共に
誕生。新しい町らしく一丁目から四丁目まである。
元は大八木・下小鳥・浜尻・貝沢の一部。県下で「みどり」をつける名は
大間々・東・笠懸の「みどり市」の他にも2箇所ほどあるらしい。
尚、前橋市の問屋町は昭和44年。
(23)大八木町(旧中川村)

緑町の北に位置し、この標識は渋川街道と大八木工業団地から西進する
道との交叉点にある。付近に諏訪神社や妙音寺。八木の地名は1030年頃の
文書に出てくるとの事なので極めて古いがその謂われは不明、八木は
「柳」からとの説があるらしいがあくまでも推論の域を出ないらしい。
鎌倉時代には既に「大」と「小」に分れていたとか。
明治22年に中川村の大字となり昭和30年に全村高崎に合併して大字が町名。
尚、大八木工業団地は昭和36-37年の造成。
(24)小八木町(旧中川村)

大八木町の東北隣、成立は大八木と同じ。北部に旧村名を残す中川小があるが
その向かいに725年の創建と伝わる鏡岩神社があり、6世紀後半の「祭祀巨石」が
ある。その西隣の「妙典寺」には1257年との銘のある「康元の板碑」があり
市の重文指定。詳しくは下記URLをご参考までに。
http://blog.goo.ne.jp/gooyamachuu/e/0cbebea75282e20049d73e3b0e134a32
(25)下小鳥町(旧六郷村)

標識は高渋線と高前バイパスの交叉点、ここは第一病院のある所で町の東南端。
戦国時代は上・下はなく小鳥一つだったが、分割時期の記録はないとの事で不明。
六郷村の形成は明治22年でその大字、昭和26年に高崎市の町。
この地域には1410年銘の石宮のある「幸宮神社」や1704年の供養搭のある
「蓮華院」がある。
(26)上並榎町(旧六郷村)

標識は高前バイパスと通称経大前通りとの交叉点。このバイパスの東が旧市街地の
並榎、西側が旧六郷村の上並榎。地名の興りは並榎と同じ。
かって存在した「稲荷山古墳」は造成用の土砂として切り崩され跡形も無く
出土品の石棺の蓋のみが護国寺の境内西側に置かれている。
http://blog.goo.ne.jp/gooyamachuu/e/cb31271e3dcb8932cc3cda6aa670dcfb
その護国寺は864年の開基、関東一を誇った大伽藍も戦火で焼失。
正面にある小野道風の扁額は勿論レプリカ、本物は寺宝。
経済大学・並榎城址もこの町内。
(27)大橋町

明治18年、信越線が松井田まで開通し「飯塚駅(現・北高崎駅)」が出来た時、
線路によって飯塚村の「字大橋」は分断された。明治22年の高崎町成立時
にはこの分断地は高崎町に編入、大橋町の町名はその13年後。
大橋とは当時から大川と云われた長野堰にかかる橋から名付けられたそうだ。
ジイ散歩第二弾はこれまで。
ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

















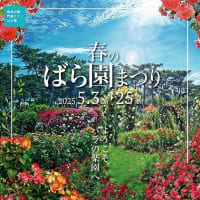



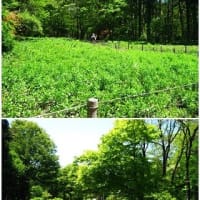





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます