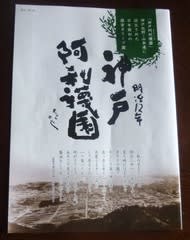近江路を歩く・・木之本観音めぐり (2017.5)
この近江路のツアーは人気で私はぎりぎりの申し込みでバスの席は一番後ろだった
大型バスで40名の参加
JR木ノ本駅でツアーバスを下車 木之本を歩く

旧図書館は公民館になっていた ヤンマーの社長は地元出身 町の雇用の為に工場をここに建てたそうだ


北国街道の街並みを歩く 私達が歩く横をモーターバイクのツーリングが爆音で通る


木之本は馬市あった所 山内一豊の妻がここで馬を買ったそうだ


昔のくすりの札が並ぶ「本陣宿」 薬剤師の第一号の家


酒屋 醤油屋


旧銀行の建物も残り 街道沿いの保存がされている
交差点の立札は「みぎ 京いせみち ひだり江戸 なごや道」 交通の要所だったことが判る


木ノ本駅からの正面に「木之本地蔵尊」がある 本尊は秘仏の為 同形の地蔵像が立っている


秀頼が寄進したという鰐口の鐘 ここは目の神様でお土産は片目のカエル


大型バスは細い山道を登り 「医王寺」へ 最近道路拡張舗装されバスが通れるようになった
村人に守られて寺で住職は無く 予約しないと拝観できない
井上靖が何度も通ってやっと会えたという観音様は柔らかな顔つきで少女を連想する姿 美しかった


山筋を変えて 己高山に行き 己高庵で山菜昼食


周辺の廃寺の仏像を集めて収蔵している「己高閣」は薬師如来を中心に十二神将10体 乾漆像3体等
京都にある寺の仏像に負けない見事な像だった
こちらを見ている女性は人気ガイドの北尻さん

茶畑を通り 鶏足寺へ 紅葉で有名なところで青もみじがきれいだった



石道寺も観音の寺 両側に持国天と多聞天に守られて立つ11面観音は口元に紅が残る仏様


高月にある国宝の向源寺へ 入場は16:00までと急がされて入る
本殿から左へ行く収蔵庫に立っていて周囲を回って見ることが出来る


高月の町をウォーキング 水路にきれいな水の流れていた


雨森芳州は江戸時代の医学、朱子学者。 中国語、韓国語に通じ対馬で外交に活躍した人
境内に「なんじゃもんじゃ」の花が咲いていた


大木の槻木は高月の槻木十選の一つ

他にも大木があちこちに残る



昔は大木にちなんで「高槻」という名だったそうだ
向源寺の駐車場に待つバスに乗り、 帰路へ
歩行距離 17,000歩
近江路を歩く・・金大巌&メタセコイヤ (2017.4)
近江を歩くハイキングツアーで日吉大社に行ったが割愛された部分を見たくて
JRを使って歩いてみた

日吉大社の東照宮
急な階段で割愛されたのを期待して登るが塀に囲まれた拝殿だった

格子の穴から本殿を、横からも見るが保存状態は良くなかった


もう一つ見たかったのは山の上にある「金大巌」。 参道からも見える


東本宮の横にある三ノ宮、牛尾宮遥拝所からの登る

広めのスロープがジグザグに続いて20分 汗ばんで歩く


石段を登ると本殿が見えた 三ノ宮宮と牛尾宮である

二つの宮の間にある大石が金大巌だった 朝日で光るという事だが苔むしていた


ほこらの横に道があるので登って見たら登山道があり、八王子山(381m)に行けた




金大巌からの眺めは坂本の町、琵琶湖が見える

次は最近有名なメタセコイヤ並木を見る為マキノへ
敦賀行の電車は1時間に1本だった

バスが出ているが本数が少なく地図を見ながら歩く
駅から約3km


新緑の並木を見る事が出来た 2.5kmの並木が続くそうだが
通り抜けは次回に残して駅に戻り 帰宅
歩行数 21,000歩
近江路を歩く・・朽木&針江 (2017.4)

今回のウォーキングは残念ながら一日中小雨だった
バスはR367 鯖街道(若狭路)を北上 到着したのは「信長の隠れ岩」
信長の浅井侵攻時の「朽木越え」の岩山に登る
川を見下ろす急な山の中にある岩の大きさに単なる伝説ではないと思った




朽木陣屋跡 資料館になっている
朽木は木材業で栄えた土地 木工の資料を見る




 絵になりそうな日本の原風景
絵になりそうな日本の原風景
安曇川を渡る 堤防には桜の木が並ぶが花はまだだった


ニニギ神社 天照神話の瓊瓊杵の尊を祀る
立派な多宝塔が残されている 中には釈迦如来像と薬師如来像が祀られている


朽木の中心街に戻り 丸八百貨店で昼食
以前来た事あるが1Fを見たのみ 今回は3階で食事だった


鯖寿司と鯖そうめん付 地元の人達手作りの料理


ここ安曇川にだけ残る「シコブチ」信仰 「志子淵神社」へ行く
安曇川は琵琶湖に流れる川で一番水量が多いそうだ
その川を利用して木材を筏で輸送していたから、水難事故から守る祈りの神社と言う
日本遺産になっていた



 クリック
クリック
花の寺14番「興聖寺」 まだ雪が残っていた


本堂に入りお坊さんのお話を聞いた後、仏像を拝見するが「写真どうぞ」と言われてびっくり
遠慮なく、ご本尊、不動像を写させてもらう



ここのお庭が「旧秀隣寺庭園」は足利時代のに作られた 国指定の名庭
椿は殆ど散っていた



ここから安曇川の堤防を歩く 桜並木が続くが今年の開花は遅かった
咲いたら花のトンネルだと思いながら歩く

バスに乗り 琵琶湖沿いの新旭町針江に行く
ここも日本遺産
梅花藻のある川が流れ、各家庭に湧水の洗い場が残る


今では市営の水道が引かれるが、住民は湧水の方が美味しいと水道栓を2個作っているという


歩行距離 13,500歩
比叡山山麓を歩く (2017.3)

 滋賀里地図
滋賀里地図
西大路バイパスを滋賀里で下りる
大津市埋蔵文化財研究センターでトイレを済ませて滋賀里ウォーキングをスタート

千体地蔵堂の内部は沢山の地蔵が並んでいた


国指定史跡 「百穴古墳群」に行く
ここは古墳時代後期(1400年前)に作られた横穴古墳が集まった史跡
山のあちこちに古墳の穴があった こんなに集まっているのは珍しい




次は大津市指定文化財「志賀の大仏」(しがのおおぼとけ)
阿弥陀如来が祠の中でなく外に出ているのが面白い



崇福寺跡は坂を登った上にあり、今は公園になっている
この寺は天智天皇の大津遷都で建てられた寺の跡で古い
琵琶湖が見える位置なのに木が茂って見晴らしは効かない



これで滋賀里の散策は終わり、バスに乗り坂本に向かう
鳥居の左右の桜並木を水路に沿いながら歩く
 坂本周辺地図
坂本周辺地図


樹齢300年以上「スダジイ」の大木を見上げる

伝教大師誕生の地 「生源寺」 本殿に上がり話を聞く
寺の鐘「生源寺の破鐘」と言われ、信長の比叡山打ちの時に打ち鳴らして割れたそうだ


坂本の町は「野面積み」の石垣が有名 加工もせずに積んだ石垣に見えるが地震にも強いそうだ
石垣のきれいな街並みを見て「慈眼堂」に向かう


「慈眼堂」は日本の寺とは雰囲気が違った
特に横にある供養塔やお墓は渡来人の寺であったことを思わせる




昼食は「芙蓉園」でのレストラン食で美味しかった


食事場所からは回遊式の日本庭園が見晴らせた
大きな築山は三か所に入口がある洞穴があり通り抜けが出来る
院主が飢饉のときに仕事を与えるために築いた富士山型の山


向いにある国指定名勝庭園「旧竹林院」を見学
室内には雛人形が飾られ、お茶御頂くことも出来る 庭も広くて立派
お茶室が「天の川席」と言われ、主人の両側に客が並ぶそうだが、どの位置か知りたかった



 庭園拡大図
庭園拡大図
日吉大社の境内に入る
大宮橋 走井橋 立派な石橋を見る



橋の正面の大杉はパワースポット「気が宿る」とか、人が撫ぜた後で色が変わっていた


「山王鳥居」は神仏習合信仰の形 「合掌鳥居」とも呼ばれる 私は初めて見る

西本宮 東本宮を見る 狛犬が本殿内にいるのは木製だからとか


奥宮には「金大巌」の磐座があるそうだ 片道30分の山登りが必要との説明
薙ぎの木と多羅葉の木が珍しい


ここから歩いて明智光秀と一族の菩提寺「西教寺」に行く
境内までの道の両側の桜は咲いたら見事だそうだ


本殿、客殿を拝観するが襖絵はガラス越しに見る
庭園や外回りの立派な寺だった





西教寺の駐車場にバスが待っていてウォーキング終了
歩行距離 8km 16,300歩