
なんとか今週も仕事を乗り切り金曜の夜、晩酌タイム、至福の時。(まぁ、毎日、飲んだくれているのだが、やはり週末は開放感が違う。)
私の様な毎日晩酌派のような人間(年間日本酒だけで四合瓶で100本以上飲んでるのかなぁ…。)にとって、酒の価格というのはシビアにならざるを得ない訳だが、この点で言うとあくまでも個人的意見だが、ワインなどに比べると、日本酒のコストパフォーマンスは非常に高い様な気がする。
大体、ワインだと2,000円を超えてからグッと旨いものが増えてくるという感じだが、日本酒だと1000円前後の本醸造クラスで「おぉ、結構イケるな…。」と言うものが多いような印象。(酒税はワインの方が安いハズだけど…。)
そんな私がいろいろ飲んでみて、最後に戻ってくる…という感じの1本が地元新潟市西区(内野)に酒蔵を置く樋木酒造の鶴の友。
無論、鶴の友の中でもハイグレードのものほど深い味わいと言うことは否定できないが、普通酒である上白は四合瓶で800円台とお安く、普段のみには最適な一本。強烈な個性を持っている訳ではないが、旨みと味わいの絶妙なバランス、所謂、飲み飽きない酒という感じで、「もう、この1本で良いや…。」という説得力がある日本酒という感じ。(ついつい飲みすぎてしまうのが欠点と言えば欠点だが…。)
この鶴の友、ほとんど新潟市内の西地区で消費されている本当の意味での地酒。このような酒が地元で簡単に手に入ることを心から感謝する次第である。














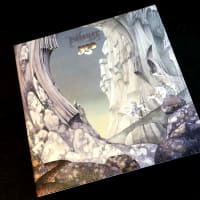



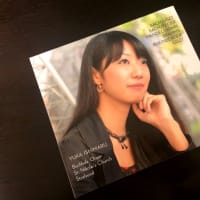

メーカー、国産か外国製かで若干違いますが。
私は2年ほど前からウイスキー主体になっていて
今はラフロイグクォーターカスク、ニッカ余市、トップバリューのブレンド(700ml換算1500円くらい)を主に飲んでます。
経済学で言う「限界効用逓減の法則」ってヤツで、ある程度までは値段に比例してやはり満足度は高まりますね。高額のワインは完全に好みの世界…という気がしますが。
今は日本酒5、ビール2、ワイン2、その他1と言う割合で飲んでますね。冬はやはり日本酒の比率が高まりますね。ウイスキーは余市が多いです。
これからもよろしくお願いします。
一人でじっくり味わうのも良いですが、同じ趣味の方と飲む酒は最高ですね。前の職場は熱心なサッカーファン、アルビサポが多かったのですが、今の職場は女性の方が多いということもあって、サッカー談義が出来ないのが寂しいです。
「〆張鶴・清泉・君の井(山廃)」私も好きですね。
〆張鶴はかなり好きなブランドです。ちょっと奮発して「純」を飲むことが多いですね。久須美酒造というと「亀の尾」のイメージが強いですが、清泉も綺麗な酒ですよね。
まろやかでス-ッと入るのがたまりません>
同感です。これからもよろしくお願いします。
大学の最寄り駅が、内野だったため良く飲みました。昔、内野駅の上に鶴の友の大きな広告が出ておりましたが、どうなったのでしょうか?知らない人は、鶴の友駅と思ってしまいます。
また、よろしくお願いします。
10数年程前、巻町(現西蒲区)に住んでいたとき、内野駅周辺は通勤経路でした。その時から看板はなかったんじゃないかな?鶴の友、決して派手さはありませんが、飲み飽きない良い酒だと思います。
これからもよろしくお願いします。
新潟酒の陣、規模が大きくなり過ぎたせいか、地元では批判的な声もない訳ではありませんが、あそこまで育てたイベント、これからも続けて行って欲しいですね。
鶴の友、素直に旨いです。これからもよろしくお願いします。
造りは、大吟醸とほぼ同じです。