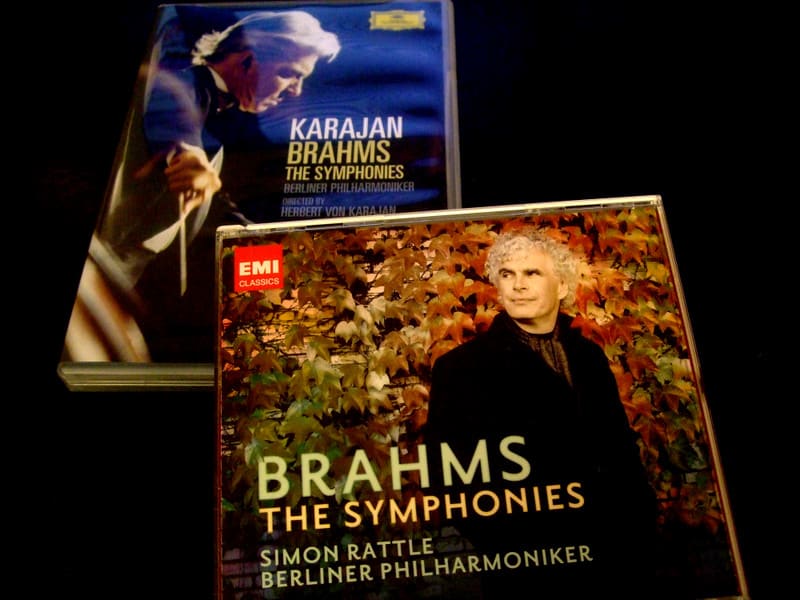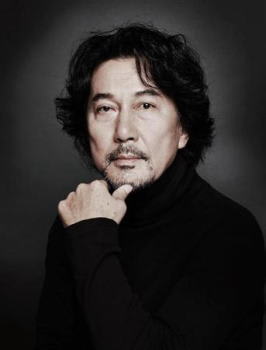最近、国内の2大シンセサイザー・メーカーであるローランドとコルグから相次いで新しいフラッグシップモデルが発売された。
ローランドの「ジュピター80」とコルグの「クロノス」である。


ローランドの「ジュピター80」は81年に同社が発表した名機ジュピター8を意識したモデル。純粋なアナログ音源を搭載していたジュピター8に対し、スーパーナチュラル・テクノロジー(なんのことか良く分からないが)を使ったジュピター80は、音源的には完全なデジタル・シンセなので、「名前とデザイン面のみを継承した」と言う感じ。
逆にコルグのクロノスは、デザイン面では過去の同社のシンセから引き継ぐものはないものの、往年の同社の名機MS-20とPolySixのモデリング音源を搭載していることが大きな話題となっている。
形は違えども、過去の自社シンセをリスペクトした新製品がリリースされたことは興味深い。
60年代に発明されて以来、飛躍的な進歩を遂げてきたシンセサイザーの歴史ももうすぐ半世紀に達する。当初、大重量で扱い難かったシンセが、60年代末、名機ミニ・ムーグ(正確にはモーグなのだろうが、どうしてもムーグと言ってしまう。)の登場以来、ライヴでも使われるようになり、70年代末にはヤマハCS80、プロフェット5、オーバーハイムOB-X、それにジュピター8などのポリフォニック・シンセが続々とリリース。その後、80年代前半にシンクラビア、イミューなどの天上ブランドとともに衝撃的なヤマハDX-7が登場、デジタル全盛時代に…。そして90年代、コルグM-1によりワークステーション・シンセ時代に突入し、パソコンの処理能力の飛躍的な向上により、現在、ソフト・シンセが主役になりつつあるシンセサイザー業界。DMWと併せ、リアルで高音質なサウンドがアマチュアでもクリエイトできるようになったのは素晴らしいことだと言えるだろう。
今、ぱっと振り返ってみたが、シンセの誕生以来半世紀、その進化は目覚ましいものがあったと思う。
しかし、思うのである。その進化、とりわけ、90年代以降の進化によって、我々の心に響く、どれだけ素晴らしい音楽が作られたのだろうかと…。
実際、今回、「ジュピター80」と「クロノス」に見られるように、ハード・ソフトシンセ問わず、過去の名機の音をどれだけ忠実にシュミレートしてあるかが新しいシンセの売りというか、大きな評価基準になっている現実がある。機能という点での向上は続いている。しかし、純粋にその楽器の「音の説得力」ということで考えてみた場合、70年代、80年代のシンセが頂点というか、それを突き抜ける魅力あるサウンドを持ったシンセは生み出されていないのではないだろうか?
ローランドの「ジュピター80」とコルグの「クロノス」のリリースでこんなことをふと思った次第である。
(なお、自分が一番好きなシンセサウンドは、やはりミニムーグのぶっ太いリード・シンセと「ぶおぁぁ~~」と言う分厚いオーバーハイムOB-X系のブラス・シンセの音である。これを凌ぐ凄い音を持ったシンセを聞きたいものだ。)