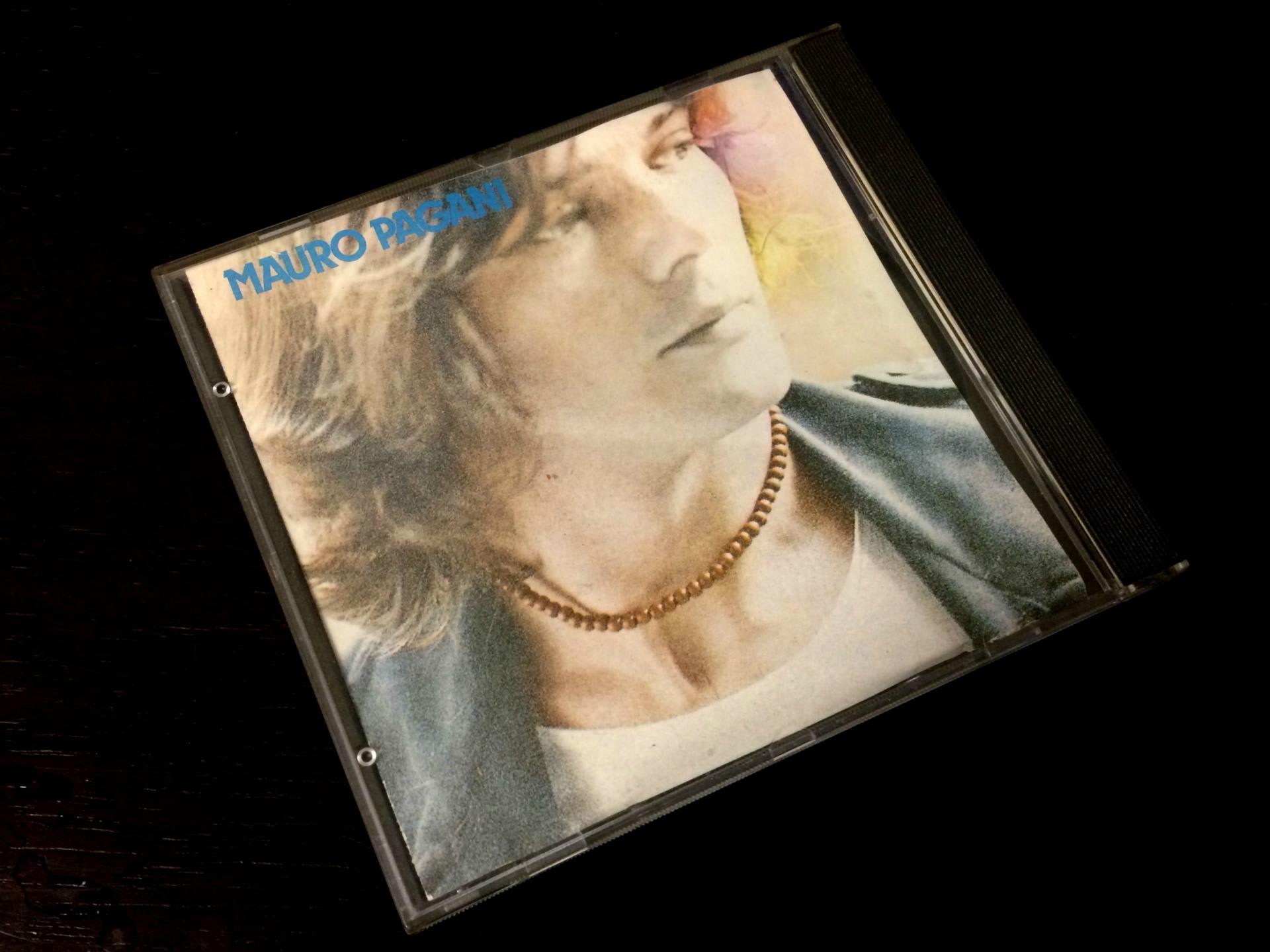今回、「最高傑作」という言葉を使ってしまったが、オフ会など、ロック・ファンどうしの飲み会での定番は「○○の最高傑作はどれか?」という会話。
(「最初は何から入ったんですか~?」、「やっぱりツェッペリンかな…。」、「ツェッペリンと言えばやはりⅣが最高傑作でしょうかね?」、「いや、プレゼンスでしょう!(キッパリ)」…と言う様に話が続いていく。)
「40年前、下手すれば半世紀前に活躍したミュージシャンの最高傑作はどれか?」なんて、はっきり言って「そんなの好みの問題でしょ?」って感じで、ファン以外にはどうでも良い話でしかないとは思うが、これがやっぱり盛り上がるのだ。
特に、自分が世評とは違っているアルバムを最高傑作だと思っている場合、思い入れがあるだけに力が入るし、「あっ、俺も○○の最高傑作は○○だと思うよ!」と言うレスポンスがあるとがっちり握手「同志!!」って感じになる。(はたから見れば完全にバカ…って感じだと思うけど…。)
ということで、見栄なし、本音トークで、思いつくままに自分がこのミュージシャンの最高傑作はこれだ!!というアルバムを書いておこうと思う。(一応、全アルバムを聴いているミュージシャンに限った。)
レッド・ツェッペリン 「コーダ」←こんな人いないかも…でも本気。世評はⅣ、ヨーイチシブヤの影響を受けた人は「プレゼンス」かな。
クィーン 「オペラ座の夜」←順当。個人的に好きなアルバムはⅡ
エアロスミス 「ロックス」← やはり70年代のエアロファンですからね。
イエス 「究極」←普通は「危機」だと思います。ジャケットが残念…。
キング・クリムゾン 「クリムゾン・キングの宮殿」←「レッド」といつも迷います。クリムゾンは難しい。
ELP 「恐怖の頭脳改革」←順当。ワークスⅠのD面とラブビーチのB面カップリングとなら迷うかも…。
ピンク・フロイド 「狂気」←順当。好きなアルバムは「おせっかい」。
ジェネシス 「月影の騎士」 ジェネシスは分かれそう。マニアは「ブロード・ウェイ」一択かな? 好きなアルバムは「デューク」
ラッシュ 「ムービング・ピクチャーズ」←順当
マイク・オールドフィールド 「オマドーン」←一般的には「チューブラー・ベルズ」だろうけど、マニアの間では本作がダントツ人気。ちょっと「呪文」と迷うけど。
ボストン 「幻想飛行」←順当。でも個人的に好きなアルバムはセカンド。
※ やっぱり、自分はロック出身の人間なんだなぁ…。フィジカル・グラフティで3回もひっぱってしまった。