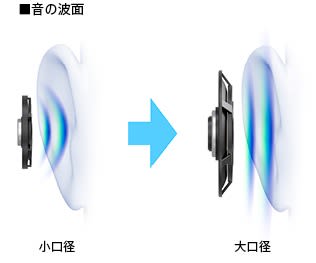エージングもまだ十数時間ってところでしょうから、まだまだってところですが、今のところの使用感など書いておきます。
一般的な製品レビューっぽく項目別でMDR-1ADAC を評価してみます(^_^)
を評価してみます(^_^)
▼デザイン
MDR-1 シリーズなのでほとんどというか全く変化なし。表面処理の違い程度と、各種ポート類の有無ですね。
▼高音の音質
解像度感が高く粒立ちある音がします。低音にも掻き消されるなく、存在感を失いません。反面、楽曲や楽器の音色によってはキツく耳に刺さりがちな面もありますね。特にエレキギターギラギラしがち...アコースティックギターは非常にキレイなんですが。
▼低音の音質
ボワっと膨満することなく立体感があり分離も良く、歯ごたえに喩えるとコシのある音だと思います。時に震動も伝わり嬉しくなることも(^_^)
▼フィット感
イヤーパッドの形状が密になったため、初代機に比べるとちょっと窮屈な感じがします。気温が20度以上だと蒸れてパッドが汗で濡れてしまいます(^_^; 重さは300gとシリーズ歴代最重量ですが、装着してしまえばあまり気になりません。それと私はメガネを常時かけてますが、ツルへの圧力感は全く無いワケではありませんが、それほど負担に感じません。
▼外音遮断性
高いとは思いませんが、そこそこ遮音している感じはあります。
▼音漏れ防止
派手に漏れてます(^_^; 初代機からしてそうなんですが、あまり重視されていない気がします。主にハウジングの上部にある通気孔から漏れ出ていると思われます。なので使い場所は結構限られますねぇ...電車など他人と近い距離にいる場合はかなり音量を絞る必要あります。静かな室内も公共の場では遠慮した方が無難でしょう(^_^;
▼携帯性
スイーベル機構によって平面的に変形するワケですが、自分の使い途ではあまり意味がないかな。無いよりは良いですけど、ヘッドホン自体の絶対的な大きさってものがありますからねぇ...。
▼その他
バッテリーの保ちですが、公称7.5時間もあるかどうか厳密に計ってないので何とも。マニュアル見ると...
電源を入れたときのPOWERランプの点滅回数で、電池残量を確認できます。
3回点滅(緑色):電池残量は充分ある状態です。
2回点滅(緑色):電池残量は中程度です。
1回点滅(緑色):電池残量が少なくなっています。充電してください。
と書いてあるんですが、割と直前まで3回点滅したりするので、使ってるといきなり電源オフ状態になりビックリしてしまいます(^_^;
それと一番良いところは、電池切れてもただのお荷物とならず、アナログヘッドホンジャックに付け替えればMDR-1A 相当品として使い続けられるところです。外付けDACやポタアンだとこうはいきませんからね(^_^;
でもねぇ...細かい使い勝手で、このアナログ接続、非常にクセがあるんですよ。
下の写真はアナログ端子に接続している様子です(モデルが汚いオヤジでスミマセン(^_^ゞ)。


なぜこれだけにカバーがついているのか...ちょっと謎です。開閉が面倒だし、変にフタが主張してイマイチ格好悪い...(´д`)
それとアナログ端子の形状が特殊なヤツで、付属のものでないとちゃんと挿さらないと言う...。下の写真、ステレオミニプラグが2本並んでますけど、右のが付属の専用のもの。見て判るとおり、一般的なものは根元が太いので、ちゃんと挿さってくれないと言う><;

なので現状手持ちのものではリケーブルができないという...。
まぁ臨時的な使用と割り切れば、そんなに大きな問題じゃないんですけどね。ちょっとその辺りがクセ強いです。
さて...このMDR-1ADAC、関連のサイトを見てもイマイチ盛り上がっていない感があって、ちょっと寂しいですね(^_^;
値段も3万円台と決して安くないし、選択肢として悩んでいる人も多く見かけます。一度ポータブルのDACやアンプを使ってみた上でじゃないと、この製品の価値が理解できない気もしてます。
この価格帯で考えると、ヘッドホン本来の性能を重視したくなりますので、割り切れば価格抑えてMDR-1A にしたくなるし、もうちょっと頑張ってMDR-Z7
にしたくなるし、もうちょっと頑張ってMDR-Z7 にした方が...などと考えてしまうと。
にした方が...などと考えてしまうと。
MDR-1ADAC はヘタすると中途半端なキワモノっぽい製品かもしれませんけどね(^_^;
オススメできる層としては、前述したとおり一度でもDACやポタアンの類いを使った事のある人、ガジェット好きの人、そしてiPhone(iOS)ユーザーかもしれません。あとはMac とか、PC での使用ですね。
なぜiPhoneユーザーなのかというと、現状Walkman のようにハイレゾをサポートしていないからです。それでもiPhone環境での使用を勧めたいのは、デジタル音質を最大限活かして、ベストな音質を楽しめるからです。アプコンを補完するDSEE HX こそ備わっていないものの、S-Master HX が効いていると思いますしね。逆にハイレゾ対応Walkman だとMDR-1ADACは不要です。Walkman の本体に実装されてから無駄になってしまうから。それなら他のシンプルなヘッドホンを選択した方が良いと思うからです。
それと前回書き込みで触れましたが、MacとAudirvana の組み合わせで、凄いスペックを示すので(^_^;、性能を最大限に引き出す形で楽しめます(*^o^*)
反面デジタルガジェットに興味ない人には、難しそう、ややこしそうという風に見えてしまうんでしょうねぇ...。何やら見慣れないポートがいっぱい付いてますから(^_^;

最後にオマケ。私は冬場の外出時や室内でもホコリっぽい時はマスクを頻繁に使いますが、MDR-1シリーズはハウジングにちょうど引っ掛かるので便利です(^_^)

まぁ総じて言えば、新しもの好きや、いろんな機能やポートがいっぱい付いてるのが楽しいと感じる...一言でいえば、やっぱりキワモノ上等、デジタルガジェット好きってことになっちゃうのかもしれませんねぇ(´・ω・`)


一般的な製品レビューっぽく項目別でMDR-1ADAC
▼デザイン
MDR-1 シリーズなのでほとんどというか全く変化なし。表面処理の違い程度と、各種ポート類の有無ですね。
▼高音の音質
解像度感が高く粒立ちある音がします。低音にも掻き消されるなく、存在感を失いません。反面、楽曲や楽器の音色によってはキツく耳に刺さりがちな面もありますね。特にエレキギターギラギラしがち...アコースティックギターは非常にキレイなんですが。
▼低音の音質
ボワっと膨満することなく立体感があり分離も良く、歯ごたえに喩えるとコシのある音だと思います。時に震動も伝わり嬉しくなることも(^_^)
▼フィット感
イヤーパッドの形状が密になったため、初代機に比べるとちょっと窮屈な感じがします。気温が20度以上だと蒸れてパッドが汗で濡れてしまいます(^_^; 重さは300gとシリーズ歴代最重量ですが、装着してしまえばあまり気になりません。それと私はメガネを常時かけてますが、ツルへの圧力感は全く無いワケではありませんが、それほど負担に感じません。
▼外音遮断性
高いとは思いませんが、そこそこ遮音している感じはあります。
▼音漏れ防止
派手に漏れてます(^_^; 初代機からしてそうなんですが、あまり重視されていない気がします。主にハウジングの上部にある通気孔から漏れ出ていると思われます。なので使い場所は結構限られますねぇ...電車など他人と近い距離にいる場合はかなり音量を絞る必要あります。静かな室内も公共の場では遠慮した方が無難でしょう(^_^;
▼携帯性
スイーベル機構によって平面的に変形するワケですが、自分の使い途ではあまり意味がないかな。無いよりは良いですけど、ヘッドホン自体の絶対的な大きさってものがありますからねぇ...。
▼その他
バッテリーの保ちですが、公称7.5時間もあるかどうか厳密に計ってないので何とも。マニュアル見ると...
電源を入れたときのPOWERランプの点滅回数で、電池残量を確認できます。
3回点滅(緑色):電池残量は充分ある状態です。
2回点滅(緑色):電池残量は中程度です。
1回点滅(緑色):電池残量が少なくなっています。充電してください。
と書いてあるんですが、割と直前まで3回点滅したりするので、使ってるといきなり電源オフ状態になりビックリしてしまいます(^_^;
それと一番良いところは、電池切れてもただのお荷物とならず、アナログヘッドホンジャックに付け替えればMDR-1A 相当品として使い続けられるところです。外付けDACやポタアンだとこうはいきませんからね(^_^;
でもねぇ...細かい使い勝手で、このアナログ接続、非常にクセがあるんですよ。
下の写真はアナログ端子に接続している様子です(モデルが汚いオヤジでスミマセン(^_^ゞ)。


なぜこれだけにカバーがついているのか...ちょっと謎です。開閉が面倒だし、変にフタが主張してイマイチ格好悪い...(´д`)
それとアナログ端子の形状が特殊なヤツで、付属のものでないとちゃんと挿さらないと言う...。下の写真、ステレオミニプラグが2本並んでますけど、右のが付属の専用のもの。見て判るとおり、一般的なものは根元が太いので、ちゃんと挿さってくれないと言う><;

なので現状手持ちのものではリケーブルができないという...。
まぁ臨時的な使用と割り切れば、そんなに大きな問題じゃないんですけどね。ちょっとその辺りがクセ強いです。
さて...このMDR-1ADAC、関連のサイトを見てもイマイチ盛り上がっていない感があって、ちょっと寂しいですね(^_^;
値段も3万円台と決して安くないし、選択肢として悩んでいる人も多く見かけます。一度ポータブルのDACやアンプを使ってみた上でじゃないと、この製品の価値が理解できない気もしてます。
この価格帯で考えると、ヘッドホン本来の性能を重視したくなりますので、割り切れば価格抑えてMDR-1A
MDR-1ADAC はヘタすると中途半端なキワモノっぽい製品かもしれませんけどね(^_^;
オススメできる層としては、前述したとおり一度でもDACやポタアンの類いを使った事のある人、ガジェット好きの人、そしてiPhone(iOS)ユーザーかもしれません。あとはMac とか、PC での使用ですね。
なぜiPhoneユーザーなのかというと、現状Walkman のようにハイレゾをサポートしていないからです。それでもiPhone環境での使用を勧めたいのは、デジタル音質を最大限活かして、ベストな音質を楽しめるからです。アプコンを補完するDSEE HX こそ備わっていないものの、S-Master HX が効いていると思いますしね。逆にハイレゾ対応Walkman だとMDR-1ADACは不要です。Walkman の本体に実装されてから無駄になってしまうから。それなら他のシンプルなヘッドホンを選択した方が良いと思うからです。
それと前回書き込みで触れましたが、MacとAudirvana の組み合わせで、凄いスペックを示すので(^_^;、性能を最大限に引き出す形で楽しめます(*^o^*)
反面デジタルガジェットに興味ない人には、難しそう、ややこしそうという風に見えてしまうんでしょうねぇ...。何やら見慣れないポートがいっぱい付いてますから(^_^;

最後にオマケ。私は冬場の外出時や室内でもホコリっぽい時はマスクを頻繁に使いますが、MDR-1シリーズはハウジングにちょうど引っ掛かるので便利です(^_^)

まぁ総じて言えば、新しもの好きや、いろんな機能やポートがいっぱい付いてるのが楽しいと感じる...一言でいえば、やっぱりキワモノ上等、デジタルガジェット好きってことになっちゃうのかもしれませんねぇ(´・ω・`)