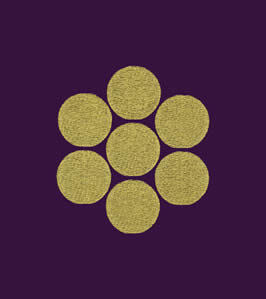☆セラフィーヌの庭(2008年 フランス、ベルギー、ドイツ 126分)
原題 Seraphine
staff 監督/マーティン・プロボスト
脚本/マーティン・プロボスト マルク・アブデルヌール
撮影/ロラン・ブルネ 美術/ティエリー・フランソワ
衣装/マデリーン・フォンテーヌ 音楽/マイケル・ガラッソ
cast ヨランド・モロー ウルトリッヒ・トゥクール アンヌ・ベネント ニコ・ログナー
☆1912年、パリ郊外サンリス
Senlisというのは、パリの北40kmにある古い町だ。
そこにひとりの女性画家がいて、
セラフィーヌ・ルイ(1864-1942)っていうんだけど、
この映画は、彼女が48歳になった頃から晩年までを描いてる。
なんでそんな中途半端な後半生だけを映像化したのかといえば、
彼女を見出したひとりの画商とセラフィーヌの物語だからだ。
画商はドイツ人で、ヴィルヘルム・ウーデという。
ピカソとも親交があって、肖像画も描いてもらった仲らしい。
ウーデは画商というより収集家のようなところがあり、
かれのいうモダン・プリミティブ派すなわち素朴派の絵を愛した。
アンリ・ルソーを見出したのもウーデだ。
ウーデはプロシア生まれなのにドイツに対して好印象は持っていなかったようで、
のちに、第一次世界大戦のときにコレクションを没収されて強制送還されても、
戦後になるや、すぐにフランスへ戻ってきたような男だった。
もちろん、パリにはウーデのようなドイツ人は少なくなくて、
かれらが集っていたのは、カフェ・ドームだったらしい。
懐かしのカフェ・ドームには、ぼくも若い頃に数回だけど、足を運んだ。
ちょっとばかしきどった観光客にはありがちな行動だけど、
なんだか芸術好きな大学生みたいじゃん?
ま、それはそれとして、
結婚はしたけど半年くらいして離婚して、
その妻はロベール・ドローネーの奥さんになった。
映画の中にも描かれてることだけど、どうやら同性愛者だったらしい。
セラフィーヌがウーデの奥さんじゃないかと嫉妬めいた感情を向けるのは、妹だ。
で、やや時は前後するけど、そんなウーデがサンリスに避暑にやってきたとき、
家政婦として雇ったのがセラフィーヌだった。
そこで、当時48歳のセラフィーヌの描いたリンゴの絵に衝撃を受けるわけだけど、
それまでセラフィーヌは絵画の勉強なんてしたこともなく、
パリへ奉公に出たとき、雇われた女学校でデッサンの授業を覗き見したりして、
まったく独学で絵を描いてきたらしい。
故郷のサンリスに戻ってからはサン・ジョゼフ・ドゥ・クリューニ女子修道院に雇われ、
そこで下働きをしながら、デッサンのまねごとをしていたくらいだ。
修道院を出てから10年ほど家政婦の仕事をし、そこで独自の絵を描くようになった。
ただ、この10年というもの、セラフィーヌは極貧の生活をしていて、
とても画材を買えるような身分じゃなかった。
だから、動物の血や、教会で盗んだ蝋燭の蝋や、野原の植物を擂り潰したもので、
自分なりの絵を描くことしかできなかった。
ただし、白色だけは作ることができなかったから、白絵の具だけは画材屋で買った。
そんなセラフィーヌだから独特の絵になるのはきわめて当然なことで、
しかも、修道院にいたとき守護天使から絵を描くように啓示を受けたっていうんだから、
これはもう他のどんな画家とも共通項のない絵になるのは当たり前だったろう。
いいかえれば、
敬虔なセラフィーヌという処女のありのままの絵になるしかなかったろう。
素朴派好みのウーデが心を奪われるのは、これまた当たり前で、
ウーデはドイツへ強制送還されるまで、セラフィーヌを励ました。
戦後、フランスに戻ったウーデは本格的にセラフィーヌのパトロンになり、
つぎつぎに大作を描かせ、好事家に紹介した。
このおかげでセラフィーヌの才能は世の人々の知るところとなって、
一挙に家政婦から画家への道をたどり、生活も豊かなものになった。
ところが、世界恐慌に見舞われたためにウーデの生活も逼迫し、
セラフィーヌへの支援も滞ったんだけど、悲劇はここで起こる。
セラフィーヌは修道院とアトリエと自然しか知らない処女で、
ウーデが金持ちだと心に刷り込まれてしまっているから、
貧乏になったといってもまるで信じない。
世間知らずの無垢な女が、愛人が破産してもそれを信じようとせず、
いつまでも愛人が金持ちだとおもいこんで、
金を入れてくれなくなったときに自分は棄てられたのだと狂乱するのに似ている。
セラフィーヌの心はあまりにも純粋だったけど、同時にあまりにも強情だった。
というより、精神的にどこかアンバランスなところがあった。
たぶん、男を知らないセラフィーヌにとって、ウーデはたったひとりの男性で、
そこには恋愛感情にもにた強烈な感情があったんだろう。
妹を奥さんかと疑い、
資金援助を断たれたときに捨てられたと思い込むのは、痛いほどよくわかる。
結局、セラフィーヌの心は崩壊し、ウェディングドレスをまとって買い物をする。
心の奥にあったウーデとの結婚がそのまま常軌を逸した行動に走らせたんだろうけど、
そんなセラフィーヌを待っていたのは、
「系統的迫害妄想、精神感覚性幻覚、根本的感受性障害」
という冷酷な診断で、クレルモン・ドゥ・ロワーズ精神病院に収容される。
1932年、68歳のときのことだ。
以後10年、彼女は絵を描くことなく病院で生活し、やがて死ぬ。
ウーデが他界したのは1947年のことだけど、その2年前、
つまり、セラフィーヌが亡くなって3年後のことになるんだけど、
みずから提唱し、パリのギャラリー・ド・フランスでセラフィーヌの個展を開いた。
パリが解放されてすぐのことで、セラフィーヌはその成功を理解していたのかどうか。
ともかく、そんなふたりの経緯を、映画は淡々と描いてる。
この描き方が実に見事で、
なにより、セラフィーヌを演じたヨランド・モローの演技は凄まじい。
セラフィーヌがのりうつったんじゃないかってくらい、天才と狂気を演じ切っている。
この映画が賞をとらないはずはないよね。
ただ、セラフィーヌは女性版ゴッホとかいわれるけど、
たしかにふたりの絵は尋常な絵ではなく、生命力の塊のようなところがあるけど、
その筆致はまるで異なる。
ゴッホとおなじような人生を送っているからそう呼ばれるんだろうけど、
セラフィーヌの絵そのものは、きわめて性的だ。
枝に繁る葉の一枚一枚を驚くほどの丹念さで描いてるんだけど、
多分に主観的ながら、ぼくには、その花のような葉すべてが女性器に見える。
陰毛につつまれた、さまざまな色彩をおびた穢れのない性器で、
それはそのままセラフィーヌという処女の自画像のように見えてくる。
こんなふうに書くと「おまえ、おかしいんじゃないか」とかいわれそうだけど、
だって、そう見えるものは仕方ないし、
処女でありつづけたセラフィーヌにとって、
絵を描くこと自体、そのままセックスだったんじゃないかっておもえるんだよね。
同性愛者だったウーデはそういう不思議なセックスを敏感に感じ取り、
セラフィーヌのもっている性的な願望や衝動を、
すべて受け入れ、絶賛したんじゃないかな~と。
ちなみに、セラフィーヌの作品はたった1点だけ、日本にあるらしい。
世田谷美術館の収蔵品だそうだから、今度、実物を観に行かなくちゃ、ね。