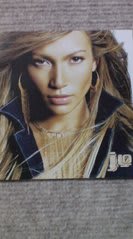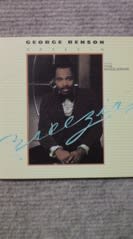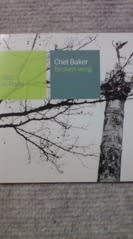いやー閲覧している皆さん、ごめんなさい。
今週は、「上原ひろみ」ウィークになってしまいました。
と言う訳で、今日も「上原」いっちゃいましょう。
ちなみに、CDの帯解説には、「元気が出るピアノ」と書いてありましたが、私の聴いた印象は、全然違います。
このアルバムの「上原」は非常にクラシカルで、知的で、どちらかと言うとオーソドックスな、ピアノ・トリオ演奏に従事しており、「元気なピアノ」と言うよりは、彼女には珍しく?、女性的で繊細なピアノ演奏です。
過去の巨匠で言うと、このアルバムの演奏は「ビル・エヴァンス」や「キース・ジャレット」に近い感じがします。
アルバムタイトル…スパイラル
パーソネル…リーダー;上原ひろみ(p、key)
トニー・グレイ(b)
マーティン・ヴァリホラ(ds)
曲目…1.スパイラル(ミュージック・フォー・スリー・ピース・オーケストラ)、2.オープン・ドア/チューニング/プロローグ、3.デジャ・ヴ、4.リヴァース、5.エッジ、6.古城~川のほとり~深い森の中、7.ラヴ・アンド・ラフター、8.リターン・オブ・カンフー・ワールド・チャンピオン、9.ビッグ・チル
2005年5月28日~31日 ナッシュビルにて録音
原盤…TELARC CDー83631 発売…ユニバーサル・ミュージック
CD番号…UCCTー1145
演奏について…オープニングの1曲目「スパイラル~」は、物静かなシングルトーン、そう、ショパンのノクターンの様な雰囲気で序奏が始まり、あれ?いつもの「上原」と違うぞって、イメージを覆す入り方なんです。
その後、「上原」は、幻想的なアドリブ・ソロに入って、「グレイ」の重厚なベースの伴奏も的を射ていて、夢の中へと誘い、私は、益々幻想空間の渦(スパイラル)へと迷い込む。
淡々と同リズムでドラムを敲く「ヴァリホラ」が、迷いこんだ私の、唯一平常心を保つ支えとなっている。
その後の「上原」は、まんま「ビル・エヴァンス」が憑依した様な、知的でハイセンスのアドリブ・フレーズを弾きまくる。
ここからのソロは、まじに聴き惚れるほどの聴き所です。
1曲目から、いきなりミサイルをぶっぱなされた様な(名)演奏が来たっああ!!
2曲目「オープン・ドア~」では、ここでも曲の入り方が、ショパンの幻想曲の様で、とても美しい。
静寂の?ピアノ・トリオ演奏が、モノクローム映画の回想シーンの様に、心を揺さぶる。
「上原」のソロは、哀愁を帯びたロマンス溢れる名旋律を紡いで、私の魂を浄化させる。
中途から曲調が、メジャーへと移ると、そこから見えるのは明るい未来と希望か?
ここからのソロでは、「キース・ジャレット」が「上原」に憑依した様に、高音域を流麗に、品良く駆け巡る指先が奏でる音に、身も心も溶けそうだ。
1曲目と双璧の名演奏です。
このアルバム…全て「上原」のオリジナル曲で、スタート2曲で、正直タップしそうなくらいに、やられちまってる。
この女性(ヒト)恐るべきコンポーザーでも有る…。。
6曲目「古城~」…正しく題名通り、とても絵画的な1曲だが、非常にメロディアスながらも、テンポがミドル・ハイでかなり推進力が効いている。
やや、ラテン調のリズムも「上原」の推進力を煽り、ピアノ・トリオが疾走を始める。
3人とも、テクニック出しまくりの演奏には、もはやKO寸前です。
中間…多分題名からすると「川のほとり」のパートか?
流麗でスケールの大きいフォルテシモの「上原」と、非常に繊細で女性美煌めくピアニシモの「上原」の二面性アドリブ・ソロに圧倒される。
1&2曲目と御三家を形成する名演です。
3曲目「デジャ・ヴ」も静けさを活かした、ピアノ・トリオ演奏です。
ゲスト参加?のエレキ・ギターもうつろな夢空間を上手に演出している。
デジャ・ヴの記憶を呼び戻すのには、何が必要なのか?
「上原」のピアノがそれを模索して、記憶の間を行き来しているようだ。
題名に相応しい、不可思議な気持ちにさせられる1曲です。
4曲目「リヴァース」は、低音域を活かした重厚な作品で、音のマトリックスを見るようで、5曲目「エッジ」も同じく低音域を活かし、魂を揺さぶるハード・ボイルド・タッチの曲。
この2曲は、いつものぶっ飛び「上原」がリターンして来て、「上原」ファンにはスカッとする曲だろう。
「ヴァリホラ」のすごテクドラムの迫力も必聴物です。
8曲目「リターン~」は、「上原」のシンセ演奏で、4&5曲目同様、普段の彼女の得意なぶっ飛び演奏に戻るんです。
カンフーをイメージした、とても東洋的なメロディだが、この曲には確かに「上原」の「元気パワー」が全面に宿っている。
タイトなドラムスを演る「ヴァリホラ」が、宇宙空間的な「上原」ワールドと、現実の世界、つまり地上を唯一結んでいる。
宇宙まで飛んで行く蝶が、「ヴァリホラ」の花に最後は戻って来るんですよ。
日本盤CDのボーナス・トラックの9曲目「ビッグ・チル」は、正統的なブルーズ風ピアノ・トリオ演奏。
しかし、「上原」のピアノ(シンセ)の素晴らしさには、もはや解説は入らないと思うが、バックの二人も「上原」の意図を完全に理解していて、トリオが完璧に機能した演奏をしている所に感心させられる。
「グレイ」と「ヴァリホラ」は、もはや「上原・トリオ」に欠かせない、ベスト・マッチ・プレイヤーになっている。
今週は、「上原ひろみ」ウィークになってしまいました。
と言う訳で、今日も「上原」いっちゃいましょう。
ちなみに、CDの帯解説には、「元気が出るピアノ」と書いてありましたが、私の聴いた印象は、全然違います。
このアルバムの「上原」は非常にクラシカルで、知的で、どちらかと言うとオーソドックスな、ピアノ・トリオ演奏に従事しており、「元気なピアノ」と言うよりは、彼女には珍しく?、女性的で繊細なピアノ演奏です。
過去の巨匠で言うと、このアルバムの演奏は「ビル・エヴァンス」や「キース・ジャレット」に近い感じがします。
アルバムタイトル…スパイラル
パーソネル…リーダー;上原ひろみ(p、key)
トニー・グレイ(b)
マーティン・ヴァリホラ(ds)
曲目…1.スパイラル(ミュージック・フォー・スリー・ピース・オーケストラ)、2.オープン・ドア/チューニング/プロローグ、3.デジャ・ヴ、4.リヴァース、5.エッジ、6.古城~川のほとり~深い森の中、7.ラヴ・アンド・ラフター、8.リターン・オブ・カンフー・ワールド・チャンピオン、9.ビッグ・チル
2005年5月28日~31日 ナッシュビルにて録音
原盤…TELARC CDー83631 発売…ユニバーサル・ミュージック
CD番号…UCCTー1145
演奏について…オープニングの1曲目「スパイラル~」は、物静かなシングルトーン、そう、ショパンのノクターンの様な雰囲気で序奏が始まり、あれ?いつもの「上原」と違うぞって、イメージを覆す入り方なんです。
その後、「上原」は、幻想的なアドリブ・ソロに入って、「グレイ」の重厚なベースの伴奏も的を射ていて、夢の中へと誘い、私は、益々幻想空間の渦(スパイラル)へと迷い込む。
淡々と同リズムでドラムを敲く「ヴァリホラ」が、迷いこんだ私の、唯一平常心を保つ支えとなっている。
その後の「上原」は、まんま「ビル・エヴァンス」が憑依した様な、知的でハイセンスのアドリブ・フレーズを弾きまくる。
ここからのソロは、まじに聴き惚れるほどの聴き所です。
1曲目から、いきなりミサイルをぶっぱなされた様な(名)演奏が来たっああ!!
2曲目「オープン・ドア~」では、ここでも曲の入り方が、ショパンの幻想曲の様で、とても美しい。
静寂の?ピアノ・トリオ演奏が、モノクローム映画の回想シーンの様に、心を揺さぶる。
「上原」のソロは、哀愁を帯びたロマンス溢れる名旋律を紡いで、私の魂を浄化させる。
中途から曲調が、メジャーへと移ると、そこから見えるのは明るい未来と希望か?
ここからのソロでは、「キース・ジャレット」が「上原」に憑依した様に、高音域を流麗に、品良く駆け巡る指先が奏でる音に、身も心も溶けそうだ。
1曲目と双璧の名演奏です。
このアルバム…全て「上原」のオリジナル曲で、スタート2曲で、正直タップしそうなくらいに、やられちまってる。
この女性(ヒト)恐るべきコンポーザーでも有る…。。
6曲目「古城~」…正しく題名通り、とても絵画的な1曲だが、非常にメロディアスながらも、テンポがミドル・ハイでかなり推進力が効いている。
やや、ラテン調のリズムも「上原」の推進力を煽り、ピアノ・トリオが疾走を始める。
3人とも、テクニック出しまくりの演奏には、もはやKO寸前です。
中間…多分題名からすると「川のほとり」のパートか?
流麗でスケールの大きいフォルテシモの「上原」と、非常に繊細で女性美煌めくピアニシモの「上原」の二面性アドリブ・ソロに圧倒される。
1&2曲目と御三家を形成する名演です。
3曲目「デジャ・ヴ」も静けさを活かした、ピアノ・トリオ演奏です。
ゲスト参加?のエレキ・ギターもうつろな夢空間を上手に演出している。
デジャ・ヴの記憶を呼び戻すのには、何が必要なのか?
「上原」のピアノがそれを模索して、記憶の間を行き来しているようだ。
題名に相応しい、不可思議な気持ちにさせられる1曲です。
4曲目「リヴァース」は、低音域を活かした重厚な作品で、音のマトリックスを見るようで、5曲目「エッジ」も同じく低音域を活かし、魂を揺さぶるハード・ボイルド・タッチの曲。
この2曲は、いつものぶっ飛び「上原」がリターンして来て、「上原」ファンにはスカッとする曲だろう。
「ヴァリホラ」のすごテクドラムの迫力も必聴物です。
8曲目「リターン~」は、「上原」のシンセ演奏で、4&5曲目同様、普段の彼女の得意なぶっ飛び演奏に戻るんです。
カンフーをイメージした、とても東洋的なメロディだが、この曲には確かに「上原」の「元気パワー」が全面に宿っている。
タイトなドラムスを演る「ヴァリホラ」が、宇宙空間的な「上原」ワールドと、現実の世界、つまり地上を唯一結んでいる。
宇宙まで飛んで行く蝶が、「ヴァリホラ」の花に最後は戻って来るんですよ。
日本盤CDのボーナス・トラックの9曲目「ビッグ・チル」は、正統的なブルーズ風ピアノ・トリオ演奏。
しかし、「上原」のピアノ(シンセ)の素晴らしさには、もはや解説は入らないと思うが、バックの二人も「上原」の意図を完全に理解していて、トリオが完璧に機能した演奏をしている所に感心させられる。
「グレイ」と「ヴァリホラ」は、もはや「上原・トリオ」に欠かせない、ベスト・マッチ・プレイヤーになっている。