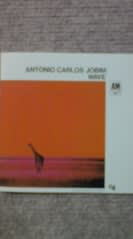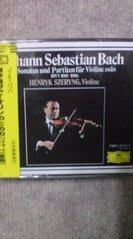ここの所、「夏のラテン」を数多く紹介して来ましたが、大分涼しくなってきたので、今日は「秋のジャズ・ヴォーカル」を紹介しましょう。
それも夜、じっくりと耳を傾けて聴く、ちょっとハスキー・ヴォイスが良いんじゃないかな。
ジャケットも飛切り美人じゃなくても、お洒落で「素敵」なのが良い。
てな、訳で今日はこのアルバムをチョイスしちゃいましょう。
アルバムタイトル…アフター・ミッドナイト
パーソネル…ヘレン・グレイコ(vo)
ジャド・コンロン(指揮) オーケストラ 他
曲目…1.テイク・ミー・イン・ユア・アームス、2.ムード・インディゴ、3.グラッド・トゥ・ビー・アンハッピー、4.いつもさよならを、5.ホワイル・ウィ・アー・ヤング、6.ブラック・コーヒー、7.ユー・アー・マイ・スリル、8.グッド・モーニング・ハートエイク、9.また会う日まで、10.ラスト・ナイト・ホエン・ウィ・ワー・ヤング、11.ミッドナイト・サン、12.ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ
原盤…VIK LX1066 発売…BMGビクター
CD番号…BVCJ-7362
演奏(歌)について…まず、一番良いと思うのは、1曲目「テイク・ミー~」は、オープニングから、スペードのエースを投入した、言うなれば「切り札」を使用した名歌唱。
ギターの調べと「グレイコ」のハスキー・ヴォイスが、そしてストリングス、ホーンが美しく溶け合って、素晴らしい絵画的な1曲を描いた。
正しく、総天然色に彩られた、黄金の50年代の絵画であり、「グレイコ」入魂の歌です。
2曲目…名曲「ムード・インディゴ」は、ハスキー・ヴォイスだが、甘ったるさ色香はあまり感じず、「グレイコ」は、比較的淡々と歌っていく。
バック陣では、ラグタイム調のピアノが、曲にアクセントをつけている。
3曲目「グラッド・トゥ~」は、アルバムにアクセントを付ける、ミュージカルの語り部的な序奏(序唱)から始まり、中途からはベースとピアノ、ヴァイブの小編成のコンボをバックに「グレイコ」が気だるく歌い込む。
4曲目「いつもさよならを」では、ストリングスをバックに、ここでも、語り部的に歌う。
その後、4ビートに変わりギター伴奏を中心として、「グレイコ」は歌の感情移入を見事に表現する。
5曲目「ホワイル~」…この曲ではとても女性らしい、可憐で可愛らしい優しい口調で歌って、「グレイコ」の別の魅力を出している。
そして、この曲では伴奏はピアノ一本で、題名通り「アフター・ミッドナイト」にぴったりの名唱、個人的にはベスト2に推薦したいです。
6曲目「ブラック・コーヒー」…何と言っても、そのものズバリの「ペギー・リー」の超絶的な名唱があるので、それと比べて…ってなってしまいそうになるが、あの名盤は置いといて、この歌唱も決して悪くはない。
アルバム随一「グレイコ」がフルヴォリュームで歌う箇所もあって、只の白人美人歌手ではなく、実力充分である事を再認識させられる。
7曲目「ユー・アー~」…この歌もとても良い。
非常に「わび・さび」の「曲間」が活かされた、歌とバックのセンスに脱帽する。
この様に、静かに歌うヴォーカルは、ジャズの女性物に良く合うねぇ。
9曲目「また会う日まで」…この曲もピアノ伴奏一本で序唱がなされて、その後ピアノ、ベース、ヴァイブがバランス良く絡み合う、編曲によりお洒落に仕上がっています。
10曲目「ラスト・ナイト~」…この曲も映画の挿入歌の様な、甘いメロディが「売り」の曲で、聴いた我々は「買い」の1曲と言えよう。
この歌での「グレイコ」は、渋さを出した助演女優賞が似合う。
11曲目「ミッドナイト・サン」では、ヴァイブが「ミルト」が敲いている様に、思える程、良い味を出している。
とてもジャジーな伴奏で「グレイコ」をケアーする、ギター&ピアノもgood。
ラスト「ユー・ドント~」…この曲は「コルトレーン」「ロリンズ」等、ホーンアルバムにも、半端じゃない超絶名演があるので、果たして「グレイコ」の唱はどうか?と思ったが、ベースをメインとした骨太のバックに「グレイコ」が渋く歌う。
女性の渋系ヴォーカルも良いもんだなぁ。
とにかく、名曲、名唱の、オン・パレードの様なアルバムをどうぞ…。。。
それも夜、じっくりと耳を傾けて聴く、ちょっとハスキー・ヴォイスが良いんじゃないかな。
ジャケットも飛切り美人じゃなくても、お洒落で「素敵」なのが良い。
てな、訳で今日はこのアルバムをチョイスしちゃいましょう。
アルバムタイトル…アフター・ミッドナイト
パーソネル…ヘレン・グレイコ(vo)
ジャド・コンロン(指揮) オーケストラ 他
曲目…1.テイク・ミー・イン・ユア・アームス、2.ムード・インディゴ、3.グラッド・トゥ・ビー・アンハッピー、4.いつもさよならを、5.ホワイル・ウィ・アー・ヤング、6.ブラック・コーヒー、7.ユー・アー・マイ・スリル、8.グッド・モーニング・ハートエイク、9.また会う日まで、10.ラスト・ナイト・ホエン・ウィ・ワー・ヤング、11.ミッドナイト・サン、12.ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ
原盤…VIK LX1066 発売…BMGビクター
CD番号…BVCJ-7362
演奏(歌)について…まず、一番良いと思うのは、1曲目「テイク・ミー~」は、オープニングから、スペードのエースを投入した、言うなれば「切り札」を使用した名歌唱。
ギターの調べと「グレイコ」のハスキー・ヴォイスが、そしてストリングス、ホーンが美しく溶け合って、素晴らしい絵画的な1曲を描いた。
正しく、総天然色に彩られた、黄金の50年代の絵画であり、「グレイコ」入魂の歌です。
2曲目…名曲「ムード・インディゴ」は、ハスキー・ヴォイスだが、甘ったるさ色香はあまり感じず、「グレイコ」は、比較的淡々と歌っていく。
バック陣では、ラグタイム調のピアノが、曲にアクセントをつけている。
3曲目「グラッド・トゥ~」は、アルバムにアクセントを付ける、ミュージカルの語り部的な序奏(序唱)から始まり、中途からはベースとピアノ、ヴァイブの小編成のコンボをバックに「グレイコ」が気だるく歌い込む。
4曲目「いつもさよならを」では、ストリングスをバックに、ここでも、語り部的に歌う。
その後、4ビートに変わりギター伴奏を中心として、「グレイコ」は歌の感情移入を見事に表現する。
5曲目「ホワイル~」…この曲ではとても女性らしい、可憐で可愛らしい優しい口調で歌って、「グレイコ」の別の魅力を出している。
そして、この曲では伴奏はピアノ一本で、題名通り「アフター・ミッドナイト」にぴったりの名唱、個人的にはベスト2に推薦したいです。
6曲目「ブラック・コーヒー」…何と言っても、そのものズバリの「ペギー・リー」の超絶的な名唱があるので、それと比べて…ってなってしまいそうになるが、あの名盤は置いといて、この歌唱も決して悪くはない。
アルバム随一「グレイコ」がフルヴォリュームで歌う箇所もあって、只の白人美人歌手ではなく、実力充分である事を再認識させられる。
7曲目「ユー・アー~」…この歌もとても良い。
非常に「わび・さび」の「曲間」が活かされた、歌とバックのセンスに脱帽する。
この様に、静かに歌うヴォーカルは、ジャズの女性物に良く合うねぇ。
9曲目「また会う日まで」…この曲もピアノ伴奏一本で序唱がなされて、その後ピアノ、ベース、ヴァイブがバランス良く絡み合う、編曲によりお洒落に仕上がっています。
10曲目「ラスト・ナイト~」…この曲も映画の挿入歌の様な、甘いメロディが「売り」の曲で、聴いた我々は「買い」の1曲と言えよう。
この歌での「グレイコ」は、渋さを出した助演女優賞が似合う。
11曲目「ミッドナイト・サン」では、ヴァイブが「ミルト」が敲いている様に、思える程、良い味を出している。
とてもジャジーな伴奏で「グレイコ」をケアーする、ギター&ピアノもgood。
ラスト「ユー・ドント~」…この曲は「コルトレーン」「ロリンズ」等、ホーンアルバムにも、半端じゃない超絶名演があるので、果たして「グレイコ」の唱はどうか?と思ったが、ベースをメインとした骨太のバックに「グレイコ」が渋く歌う。
女性の渋系ヴォーカルも良いもんだなぁ。
とにかく、名曲、名唱の、オン・パレードの様なアルバムをどうぞ…。。。