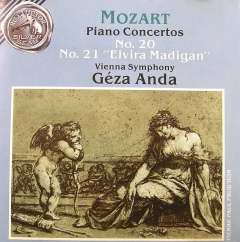モーツアルト:ピアノ協奏曲第23番
ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番
ピアノ:クララ・ハスキル
指揮:シャルル・ミュンシュ
管弦楽:French Radio Symphony Orchestra(モーツアルト)
ボストン交響楽団(ベートーベン)
CD:米MADRIGAL MADR-203
このCDは、ピアノのクララ・ハスキルと指揮のシャルル・ミュンシュの共演のライブ録音を1枚のCDに収録した歴史的録音盤だ。モーツアルトのピアノ協奏曲第23番が1959年9月15日、ベートーベンのピアノ協奏曲第3番が1956年11月3日と、今から50年前の録音にもかかわらず、そう古めかしくない録音であり、聴いていて楽しめるのがいい。
演奏は、モーツアルトのピアノ協奏曲の方は、ハスキルが相変わらず天上の音楽のような天衣無縫で、流れるようなモーツアルトを聴かせてくれる。ハスキルの死は1960年12月なので、死の1年前の録音ということになるが、この演奏は精気に満ちており死の影などは見当たらない。多分演奏会当日の体調が良かったのかもしれない。一方、ミュンシュはというと、いつもの情熱的な演奏は影を潜め、あくまでハスキルの伴奏に徹しているところが返って面白い。死の1年前のハスキルはピアニストとして最高の地位にあったはずで、ミュンシュもハスキルに敬意を表して裏方に徹したということかもしれないとも思えるほどだ。
これに対して、ベートーベンのピアノ協奏曲第3番は、ミュンシュが世界一流にまで育て上げたボストン交響楽団との共演だけに、ミュンシュの情熱的な指揮ぶりが前面に出て、聴いていて、“これぞミュンシュ”と思わず、聴いていても力が自然に入ってしまうほどの熱演を聴かせる。ハスキルの方はというと、ベートーベンであろうとお構いなしに、誠に優美なピアニズムに徹している。あの闘争的なベートーベンが天使の顔に見えてくるのだから不思議な体験だ。それでもベートーベンの音楽は十分に吸収してしまい、これもベートーベンだと納得してしまう。やはりハスキルという人は不世出のピアニストとであることを改めて実感させられる。
このベートベンのピアノ協奏曲第3番の録音は、ハスキルの優美さとミュンシュの情熱ががっぷり絡み合った類まれなものであり、後世に長く伝えたい1枚ではある。それが証拠に第1楽章が終わると聴衆が思わず熱烈な拍手を惜しみなくしている(ところで最近のコンサートは、例え良い演奏でも一つの楽章が終わったところで聴衆が沈黙しているのは何故か?。クラシック音楽の会場がロックコンサートのようになれとは言わないが、良い演奏だったら一つの楽章が終わったら拍手をしてもいいのではないか。それともつまらない演奏のとき拍手がないとその演奏家に失礼だから、すべてしないのか?)。(蔵 志津久)