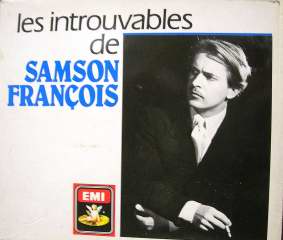モーツアルト:ピアノ協奏第9番/第23番
ピアノ:遠山慶子
カルロ・ゼッキ指揮/群馬交響楽団
CD:カメラータ・トウキョウ 32CM-3
出逢いとは不思議なものである。いい出逢いもあれば悪い出逢いもある。今回のCD、遠山、ゼッキ、群響の出逢いは最高の出逢いといえる。遠山のゆっくりとした、心の中からモーツアルトが溢れんばかりの情緒たっぷりの弾きっぷり。生前のクララ・ハスキルとも親交があったという遠山に、ハスキルが乗り移ったような感すらある名演だ。カルロ・ゼッキの指揮は、モーツアルトの心の内面を吐露するような優雅な指揮しきぶりに惚れ惚れする。そしてこのCDで最高の演奏を聴かせるのが群馬交響楽団、群響である。日本のオーケストラがこんなにうまくモーツアルトを演奏するのを聴いたことがないし、果してこれからも出てくるのか分からないほどの絶妙の演奏を聴かせる。ライナーノートで富永壮彦氏は「『あれほんとに群響?』と井坂綋氏に電話すると『ああ、やっぱりそう思った?ウィーン・フィルの人にテープを聴かせたら、ウィーン・フィルよりうまいと言われましたよ』」という話を載せているほどの出来栄えだ。
この録音が行われたのが今から20年以上の前だ。最近のコンサートや海外のコンクールで優勝した演奏を聴くと、ちょっと首を傾げたくなることがある。たしかに最近の日本人の演奏は技術的には優れているのだろう。でも、ほんとに、心の奥底から演奏しているのか疑問に思えることもしばしばだ。エネルギッシュに熱演をしさえあれば、ことたりるといった感じがする。このCDはそのまったく逆で、静かに、ゆっくりと、モーツアルトが作曲した心情を探り出し、それを共感をもって表現をしている。最近、海外の著名なコンクールで優勝した若い日本の演奏家たちがマスコミで絶賛され、紹介されている。でも、よくそれらの演奏を聴いてほしい。コンクールというのは、技術やコンクール独特の雰囲気に合った演奏家が勝つのであって、心は採点されない。最近の若い日本人は、昔の日本人のようにものおじしないし、自己主張が強いから、コンクールでは有利だ。これをもって、日本人のクラシック音楽のレベルが上がったかというと、はなはだ疑問だ。私は逆に下がっていると思う。その原因の一つは厳しい音楽評論家が少なくなったことがある。昔の音楽評論家はよく勉強をし、厳しい評論活動を展開していた。今の音楽評論家の多くは海外のコンクールで入賞した演奏家だけを褒め、そうでない人を無視する。リスナーも同じだ。これでは日本のクラシック音楽界のお先は真っ暗だ。
このCDで演奏している群響は世界的に見れば無名な存在だろう。日本国内でも怪しいものだ。しかしである。このCDの群響はウィーンフィルに匹敵する演奏を聴かせる。その原因は何か。モーツアルトへの共感とクラシック音楽へ愛情ではなかったのか。当時の群響のメンバー一人一人に敬意を表したい。(蔵 志津久)