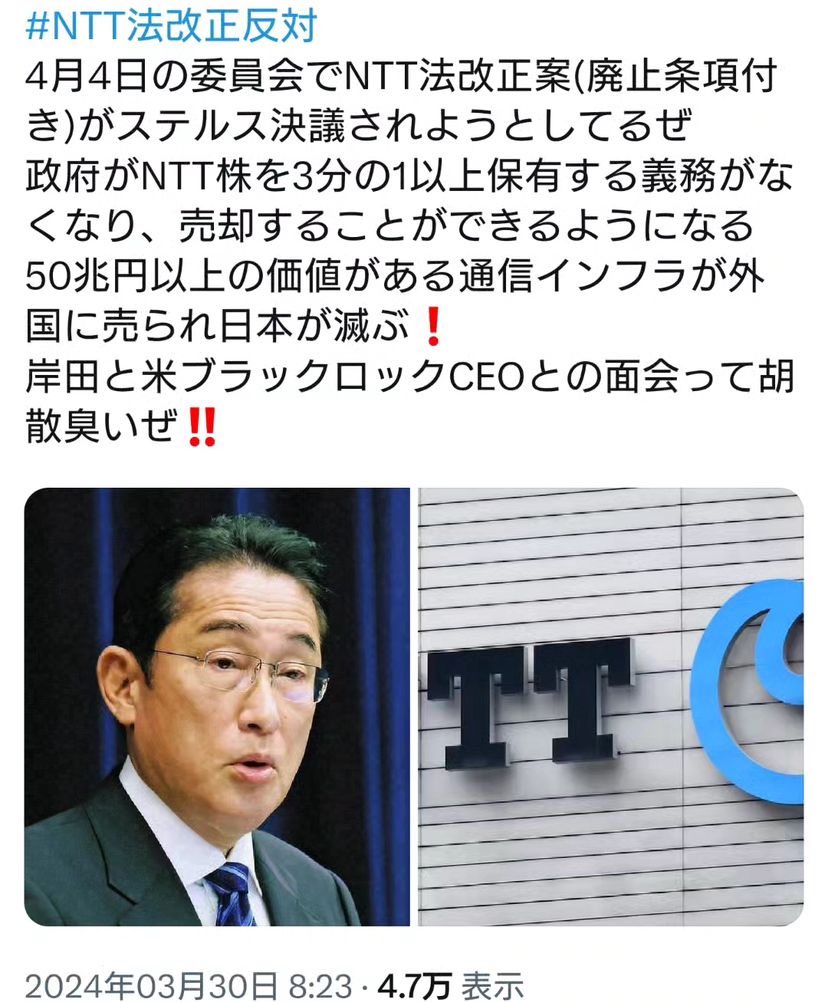【海外が注目!】日本を没落させた真犯人の正体#財務省#石破総理(1月5日まで公開) 三橋貴明
XユーザーのNewsSharingさん:
「れいわ新選組「1997年から2022年までの25年間の各国政府総支出の伸び率は、韓国は約700%、日本は37%…日本が経済成長出来なかった理由は、人口減少などではなく、政府が財政出動しなかったからです」
https://t.co/YlYWaLe6SR」 / X
れいわ新選組「1997年から2022年までの25年間の各国政府総支出の伸び率は、韓国は約700%、日本は37%…日本が経済成長出来なかった理由は、人口減少などではなく、政府が財政出動しなかったからです」
https://newssharing.net/seifusishutsu37
森永卓郎氏「日本政府が普通の経済政策をしていればGDPは今頃2倍3倍になっていた。社会保障や教育を叩き切って増税増負担だけはどんどん進めるバカげた政府」
via ジョージ 積極財政
ジム・ロジャーズ「日本経済は歴史的に見て異常」 人口減少と負債増加が同時に起きているのはヤバい(東洋経済オンライン) - Yahoo!ニュース
ジム・ロジャーズ「日本経済は歴史的に見て異常」 人口減少と負債増加が同時に起きているのはヤバい
「日銀の金融政策は間違いだった」とジム・ロジャーズ氏は説く(写真:アフロ/2018年撮影)
「日本は人口減少と負債増加が同時に起こっており、今適切な対処をしなければ、日本の存在自体が危ぶまれるかもしれない」と、世界三大投資家のひとり、ジム・ロジャーズ氏は警鐘を鳴らします。
同氏の最新著書『「日銀」が日本を滅ぼす』より、危機の正体を解説します。
【グラフを見る】日本は合計特殊出生率が急速に低下している
■長期にわたる低金利政策は世界的に見ても“異常”
日本の低金利政策の影響について考えたい。金利が正しくないというのは、歴史上よくあることだ。しかし、日銀の金融政策が間違っていたのは、長期間にわたって続けてきた点である。
日本のように、低金利政策が35年近くもの長年にわたって続くという状況は、世界的に見てもこれまでに例がなく、間違いなく“異常”な状況、政策だと断言できる。
言い方を変えると日銀は、他国の中央銀行とは異なるアプローチを取ってきたのである。災害後など特別な状況に、短期的に低金利政策を実施し、良い結果をもたらすことはある。しかし、長期的な低金利政策が繁栄と成功につながった例を、私は知らない。
さらに問題なのは、あまりに長い期間、低金利政策を続けてきたため、今の若い日本人の多くは低金利がふつう、当たり前だと捉えていることだ。大きな間違いであるにもかかわらず、である。
ぜひとも日本の今の若い人たちには、歴史を勉強してもらいたい。日本国内の状況だけに目を向けるのではなく、経済史や世界史を読めば、35年もの間続いた低金利政策が、ふつうではなかった、というより明らかに“異常”であることに気づくからだ。
■人口減少と負債増加が同時に起こるのは致命的
長期的なゼロ金利政策は、特に人口減少と負債増加という悪影響を及ぼす。そして今の日本ではこれらの悪影響を相殺するほどの繁栄は見られない。何かが変わらない限り、状況はさらに悪化する可能性があるだろう。
ゼロ金利政策が、日本経済ならびに日本人にどのような悪影響を及ぼしているのか、具体的に見ていこう。
まずは、これまで私が日本について言及する際にたびたび触れてきた問題、人口減少だ。日本の人口は20年間減少し続けている。15年以上も人口が減少し続けている国は、歴史的に見ても珍しい。
特に、世界的に先進国と呼ばれ、繁栄している国で、このような現象が起きているのは異例だ。
同時に、急速なスピードで高齢化が進んでいるのも問題だ。合計特殊出生率も下がり続け、2023(令和5)年には1.20にまで落ち込んでおり、労働人口の減少も同じく継続的に起きている(下図参照)。
合計特殊出生率とは、15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したものであり、一人の女性が一生の間に産む子どもの数と考えていい。なおアメリカの合計特殊出生率は「1.7」の近辺をここ数十年推移しており、フランスやイギリスも近しい数値だ。
このままの状態が今後も続けば、日本の人口は21世紀末ごろには半数近くにまで減ることは明らかだ。
社会保障の問題も非常に深刻だ。人口が減少するということは、税金や社会保険の担い手が減る、ということでもあるからだ。そして当然だが逆に高齢者が増えていけばいくほど、彼らの生活や社会福祉を賄うために、多くの労働者が必要になる。
このように日本では、高齢者をサポートする年金など、各種社会保障サービスの原資を生み出す人が圧倒的に足りていない。そしてここからがより深刻な問題だが、この先も悪化の一途をたどっていくことが、データとして出ている。
さらに日本は巨額の財政赤字を抱えている。この赤字を、誰が返すのか。こちらも各種社会保障と同じく、現役世代の労働者だ。つまり人口減少、特にお金を生み出す生産年齢が減っていることに加え、負債は増え続けている。この2つが同時に起きている日本は、致命的としか言いようがない。
また、いくら海外からの投資を呼び込んだとしても、それを活用する人材がいなければ長続きしない。このように日本は非常に深刻な問題を抱えており、適切に対処しなければ、40年後、50年後には日本の存在自体が危ぶまれると私は危惧している。
■英国病とまで言われたイギリス
このように国が衰退していく状況も、歴史を学べばわかる。ポンドが急落したイギリスの事例だ。イギリスは産業革命を最初に達成した国であり、かつては世界の工場と言われ大繁栄した。
だが、第2次世界大戦後の1960~1970年代にかけて、長きにわたり経済が停滞。フランス、ドイツ、そして日本と次々と他国に抜かれていき、そのような状況を揶揄してヨーロッパからは「英国病」とまで言われた。
工業生産力の減退、輸出の減少、国民の勤労意識の低下、慢性的なインフレ、階級制度、保守的な教育、労働組合のスト頻発など、経済停滞の要因はいろいろと議論され、どれも関係していたと思われる。
中でも私が注目している、日本の状況と似ていると思うのが、労働者が不足しているにもかかわらず、ゆりかごから墓場までと言われるほどの、高度な社会保障制度が整備されていた点だ。
当時のイギリスは石炭や電気、ガス、鉄道や運輸、自動車といった基幹産業を国有化することで産業を保護しようとの政策を行った。ところが、国有化したことで企業は経営努力を怠るようになってしまう。
設備投資を積極的に行わなくなり、他の企業と競争することもなくなった。結果、イギリスの工業製品の品質や魅力は低下していき、国際的競争力を失い、貿易収支は悪化していった。
加えて、国民全員が健康保険に加入し、全員が無料で医療サービスを受けることのできる、社会福祉政策ならびに制度の整備を進めていた。
先の日本の社会保障制度でも述べたように、このような制度を維持するには、膨大な資金が必要だ。ところがイギリスは、第2次世界大戦のときに行った膨大な支出による財政状況の悪化から回復しておらず、イギリス政府にはそのような制度を推し進める資金が足りなかった。
ついにイギリスは1976年、国際金融の安定化や各国中央銀行の取りまとめなどを行うIMF(International Monetary Fund/国際通貨基金)から、融資を受ける事態にまで追い込まれる。
■イギリスが復活できて、日本にできない理由
ただイギリスは、そのまま沈没することはなかった。1979年に首相に就任したマーガレット・サッチャーが、政策を転換。「小さな政府」を掲げ、国営企業を民営化するなどして歳出を削減。さらには、北海油田の開発を進めるなどして復活を遂げていく。
北海油田とはイギリス、ドイツ、ノルウェーなどの国に囲まれた、ヨーロッパ大陸の北、スカンジナビア半島の西あたりに位置する北海と呼ばれる海の海底に点在する、大規模な海底油田である。
発見されたのは1960年。現在では周辺の多くの国が開発に携わっているが、最初に乗り出したのが、イギリスだった。そうしてイギリスは、石油の自給と輸出という事業を手に入れることになったのである。
だが日本には、イギリスにとっての救世主であった世界最大の油田を発見するようなことは起こりそうにない。北海油田の発見ならびに開発は、宝くじに当たるようなものであり、奇跡的な出来事だからだ。
さらに言えば、仮に北海油田のような宝くじを日本が当てたとしても、1度や2度では現在の状況を根本的に改善することは難しいだろう。日本が現状抱えている課題、日銀が35年近くにわたり行ってきた金融緩和政策は、それほどの大きな負債を、日本に背負わせたと私は考えている。
ジム・ロジャーズ :投資家、ロジャーズホールディングス会長
室温で稼働可能な国内初「光量子コンピューター」、年内稼働へ…ニューラルネットワークへの応用にも期待(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
室温で稼働可能な国内初「光量子コンピューター」、年内稼働へ…ニューラルネットワークへの応用にも期待
理化学研究所とNTTなどのチームは8日、次世代の計算機「光量子コンピューター」の稼働を年内にも始めると発表した。
インターネットのクラウドを介して、ほかの大学や研究機関も利用できる国内初の光量子コンピューターという。
量子コンピューターは、原子や電子など極微の世界を支配する物理法則「量子力学」を利用して計算を行う。
日本では昨年、理研や富士通、大阪大などが相次いで国産量子コンピューターを稼働させた。
ただ、いずれも中枢部の素子「量子ビット」に超伝導回路を使う方式で、極低温の冷凍機内で稼働させる必要があった。
チームによると、今回、開発に成功した光量子コンピューターは、室温で稼働可能なため、消費電力を抑えることができる。
また、インターネットなどでも活用される「光」を使うため、高度な計算処理ができる。
AI(人工知能)の基盤技術でもある、脳の神経回路を模した計算モデル「ニューラルネットワーク」への応用も期待されるという。
チームは今回、光量子コンピューターを操作するソフトウェアを簡単に開発できる専用プログラムなども作成。
専門知識がなくても、光量子コンピューターを広く利用できる社会を目指す。
同日、文部科学省で記者会見した理研の古澤明チームリーダーは「大量のエネルギーを使わずにAIを活用できる光量子コンピューターの開発につなげていきたい」と話した。
【日本の危機】岸田政権の棄民政策で急速に貧困国に転落する日本”ドルと原油と世界経済”(原口一博×石田和靖)@kharaguchi
【30年間国民をだまし続ける消費税。改めて消費税法から「益税が存在しない」ことを解説】#消費税 #インボイス
【衝撃の事実】消費税は直接税だった | 【底地・借地の専門】株式会社アバンダンス (abundance-life.com)
【衝撃の事実】消費税は直接税だった

税金の種類は、大きく直接税と間接税の2つに分けられます。
また、私たちの生活にも馴染み深い“消費税”は、代表的な間接税として有名ですが、実はこちらは直接税に該当するものだと言われています。
今回は、なぜこのように言われているのかについて、詳しく解説したいと思います。
直接税と間接税の違い
まず、直接税と間接税の違いについて簡単に解説します。
直接税とは、税を納めるべき人と負担する人が同じ税金を指します。
例えば、所得税は個人の所得を10種類に分け、それぞれの所得を計算し、その結果をもとにして税額を求め、本人がその金額を納税します。
一方、間接税とは、税を納めるべき人と負担する人が異なる税金のことをいい、消費税はこれまで代表的な間接税の1つとされていました。
消費税を負担するのは消費者であるものの、実際に消費税の申告や支払いをするのは、消費者に商品を販売したり、サービスを提供したりした事業者となります。
間接税は“消費者または利用者”に課される税金
代表的な間接税の1つに、入湯税というものがあります。
こちらは、消費者が事業者の提供する温泉に入った場合に支払いを求められる間接税であり、金額は大体150円程度となっています。
また、入湯税法には、「鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課すものとする」という記載があります。
つまり、入湯税の実際の負担者は消費者であることが、明確に記載されているということです。
その他でいうと、ゴルフ場利用税も同じ仕組みです。
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の所在する都道府県が、ゴルフ場を利用するプレイヤーに課す税金です。
法律には、入湯税と同じように、「ゴルフ場の利用に対し、その利用者に課する」と記載されています。
なぜ消費税は直接税なのか?
先ほども少し触れたように、間接税としての消費税は、商品を購入したり、サービスを受けたりする消費者が負担し、事業者はその申告、支払いを行います。
しかし、消費税法には、消費税の納税義務者について、「事業者は国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により消費税を納める義務がある」としか記載されていません。
ここで注目したいのは、入湯税やゴルフ場利用税などと違い、「実際の負担者は消費者である」と明記されていない点です。
つまり、消費税は消費者に納税義務があるわけではないということです。
法律により、納税義務者が事業者であることのみが明確にされている以上、他の間接税とは仕組みが異なるため、消費税は事業者が直接納める税金、つまり直接税に当てはまるということになります。
国税庁が定義する消費税の納税義務者
国税庁のホームページに記載されている“タックスアンサー(よくある税の質問)”における消費税の定義には、納税義務者について以下のように記載されています。
「国内取引の場合には、事業者は非課税取引を除き、事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付、役務の提供について消費税の納税義務を負うことになっています。」
先ほども解説したように、やはり納税義務者は事業者だということしか記載されていません。
そればかりか、上記の文章の下には念を押すように、「このように、国内取引の消費税の納税義務者は事業者ですから、事業者でない者に納税義務はありません」と続けられています。
つまり、消費税=直接税という認識は、正式な定義をもって認められる事実であるということです。
過去の裁判では“消費税=預り金”ではないことが証明されている
間接税としての消費税は、消費者がその金額を負担し、事業者はそれを預かって納税しているという認識です。
こちらの理論でいうと、消費税は消費者からの預り金に近い性格を持っているように思いますが、実際はそうではありません。
1989年の消費税導入時に、とある裁判がありました。
その内容は、年商3,000万円以下の事業者は免税事業者ということで、消費税を免除されているのに対し、「それは消費者から預かった消費税を事業者がネコババしていることになるから横領だ、益税だ」という考えを持ったサラリーマンが、東京と大阪で裁判を起こしたというものです。
また、裁判の結果は原告の敗訴であり、判決理由としては、「消費者は消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底言えない」「消費税の徴収義務者が事業者であるとは解されないため、消費者が事業者に対して支払う消費税分は、あくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有さない」とされています。
つまり、事業者は預り金として消費者から消費税分を預かっているわけではなく、あくまで商品やサービスの付加価値として、ある程度の金額を受け取っているということになります。
まとめ
ここまで、消費税=直接税と言われている理由について詳しく解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
間接税は、納税義務者とその負担者が同一であり、なおかつそれぞれ明確に法律で定義されているものです。
一方、消費税は納税義務者しか明確になっていない以上直接税であり、こちらを消費者が負担し続けているという現実は、不透明であり非常に闇が深いと言えます。
財務金融委員会 原口一博質疑 2024/02/20 所得税法等の一部を改正する法律案 13:50~
財務金融委員会 原口一博質疑 2024/03/12
6:00~ 消費税について
27:00~ パンデミック条約について
【空白の30年】国民がどうなろうと自分らが良ければそれでよし!触れられない特別会計に触れる!【国会中継】【原口一博】
“半導体バブル”に沸く熊本・菊陽町 無人駅で通勤ラッシュも 「TSMC」新工場開所【めざまし8ニュース】
セルフレジで「客は労働」、有人レジと同じ代金はおかしくない? 誰のための便利なのか考える (msn.com)
セルフレジで「客は労働」、有人レジと同じ代金はおかしくない? 誰のための便利なのか考える
スーパーやコンビニへの導入が進むセルフレジ。歓迎する人がいる一方で 店ごとに微妙に違うルールに戸惑ったり、客が労働を提供するにもかかわらず、有人レジと値段が同じことを疑問視する人も。あなたはどう考えますか? AERA 2024年2月26日号より。
* * *
「並ばずに支払いが早くできて便利。導入はうれしいですね」
愛知県に住む女性(60)がいつも買い物をするスーパーでは3カ月前、客が商品バーコードの読み取りから支払いまで自ら行う「セルフレジ」が導入された。
「レジが6列あって、二つがお金のやりとりも店員さんとする有人レジ。残りが支払いだけは客がやる『セミセルフレジ』。その傍らにセルフレジが六つ新設されました。私は必ずセルフレジを選びます」
なぜか。女性には「早くて便利」以外にも理由がある。
「レジには近所の知り合いがパートで入っていることも多い。買った商品を見られたくない気持ちもあるので、セルフレジはありがたいです」
■取り残される悲しさ
人手不足の解消や業務の省力化を目的に導入が進むセルフレジ。2023年のスーパーマーケット年次統計調査によると、回答があった283社のうち、セルフレジを設置している店舗があると回答した企業は31.1%。年々増加傾向にある。
またコンサルティング会社「MS&Consulting」が20代から50代を対象に昨年行った調査では、スーパーでふだん使うレジの形式について「セルフレジ」と答えた人が6割を超えた。
作家で生活史研究家の阿古真理(あこまり)さん(55)も広がりを実感している一人だ。セルフレジが併設されているスーパーでは使うことも多いという。
「たしかに便利です。ただ、東京23区内の某大手スーパーの店舗が『セルフレジのみ』だったのには驚きました。高齢者も多い土地柄。困っている人も多いのではと心配になりました」
東京都内で一人暮らしをする88歳の女性は最近、近所のスーパーに買い物に行くのが憂鬱(ゆううつ)になってきたという。
「セルフレジが導入されたんです。セミセルフレジにもなかなか慣れずただでさえ自信がなくなっているのに、社会から取り残されていく悲しさを感じます」
お年寄りも時間がたてば慣れるはず。そんな声もある。しかし、先述のコンサル会社の調査では、セルフレジに「若干抵抗がある」と答えた人は年代を問わず一定数存在し、年齢が上がるほど増えている。阿古さんは言う。
「常にその時点での初心者やITが苦手な人は存在します。ITの進化があまりに速く、想定外のところでつまずく人たちに対するシステム開発側や導入する企業側の想像力が、追いついていないのではないか。誰もが対応できる前提で『お年寄りが困ろうが、お構いなし』で進むセルフレジ導入を見ていると、そんなことも気になります」
別の面から、セルフレジ導入に疑問を持つ人もいる。熊本県の司法書士、松山洋さん(74)は「客が自分でレジの作業をしながら、代金は有人レジと同じなのはおかしい」と指摘する。
「ガソリンスタンドでも、セルフで給油すれば1リットルあたり数円安くなりますよね。客が労働を提供するのであれば、価格に反映されるべき。でなければ客は店の労働力の一部にただ利用されていることになる」
■「店側の態度が不遜」
松山さんはセミセルフレジの支払い方、つまり「お金を機械に対して支払う」ことにはまったく異存がないのだと言う。
「請求金額が確定してしまえば、支払いは買い主側の義務になりますから支払う先が人間でも機械でも関係ありません。自らバーコードを読み取るという形で『自分で請求し、自分で支払総額を確定させる』というその行為が、不合理なんです。そんなことを客に求める店側の態度は不遜だと、私は思います」
この声を、店で働く人はどうとらえるのか。大手100円ショップなどで約10年のレジ打ち経験があり、漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』の著書もある狸谷(たぬきや)さん(40代)は、昨年秋に勤務先の店舗でセルフレジが導入され、「ありがたかった」と言う。
「私が勤める店舗は従業員4人でまわしていましたが、有人だとレジに3人とられるんです。忙しすぎて品出しが追いつかず、倉庫に品物はあるのに棚がスカスカでお客さまにお叱りを受けることもありました」
導入後は、そのアテンド担当が1人で、サブアテンドが1人。かなり余裕ができたという。
「お客さまの買いたいものが売り場にない、という状況がなくなりました。たしかにお客さまにレジ行為を負担していただいている形ですが、その分、お買い物の環境をきちんと整えられた。そことの『引き換え』になっているのかなと思います」
とはいえ店員には、導入したからこその「苦労」もある。
「60代くらいの男性がセルフレジに曲がった硬貨をたくさん入れてシステムにエラーが出てしまい、回復作業に戸惑っていたら『もっと勉強しとけ!』と怒鳴られたこともあります」
狸谷さんの店舗は大手スーパー内にあり、スーパー専用の電子マネーを使いたい客も少なくないため、それ専用の有人レジを一つだけ残してある。ある日、50代くらいの女性が「電子マネーで払いたい」というので有人レジに誘導すると、実は現金での支払いだったという。
「指摘すると、『セルフレジだとわかってたら来なかった!』とキレられました。どうやらセルフレジが嫌だったみたいで(笑)。うそをついてまで有人レジに並ぶ人、多いです。バーコードの読み取りがうまくいかず時間がかかり、イライラをぶつけてくるお客さんもよくいました」
(編集部・小長光哲郎)
※AERA 2024年2月26日号より抜粋











 </picture>
</picture> </picture>
</picture>