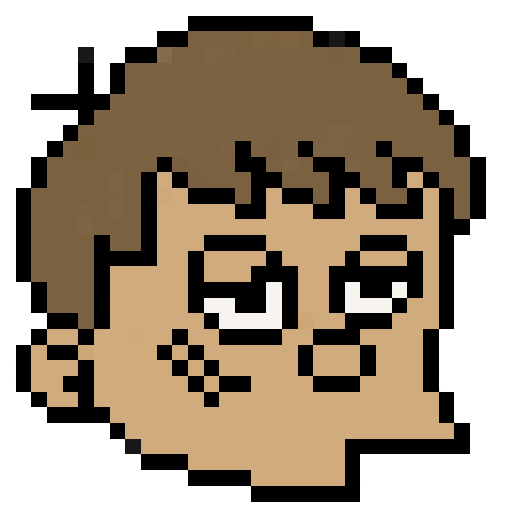70年安保を「学生運動」として捉えるなら、もっとも象徴的なのは東大安田砦の攻防が想起される。しかし一方で、市民目線というか、街頭目線に立った見地で捉えるなら、もっとも激しく象徴的なのは1968年10・21国際反戦デーのいわゆる「新宿騒乱事件」だと思う。
実に二万人もの市民、学生、労働者が新宿駅構内外での実力闘争を闘い抜いた。翌22日の午前0時過ぎに騒乱罪が適用され、734人の人々が検挙された。
映画『怒りをうたえ』の冒頭はこの日の生々しい記録から始まる。
さて、現在に目を移すと、このデモが当時の意志を受け継がれ、いまだ行われていることが判明した。といっても去年から。
それで二回目の今年は、10・21を京都でやり、東京では前日の10・20に行われるらしい。
「意志」の今と昔を見比べるのに、これほどの好材料もなかなかない。取材に行ってみた。
当日。
もし機動隊が出ててもみくちゃになったりして、足を踏まれたりしたらヤなので、登山靴を履いていく。走り回るのでジャケットの下にはTシャツ1枚といういでたち。それにカメラはもちろん、相棒のDVX100。約2年ぶりにアナモフィックレンズを装着し、ショルダーベルトを通す。これに上から薄手のバッグを被せ、ベルトを直接肩にかける。
一眼レフカメラとかならオシャレに見えもするが、さすがにデカいビデオカメラを、裸で堂々と持ち歩けない。街頭ならまだしも、電車とかでややうしろめたい気持ちとなる。
あとは私物や予備バッテリー、テープなどを鞄につめこむ。とにかく軽装をこころがけた。
昼過ぎ、新宿到着。
牛丼をささっと食い、集合場所の大久保公園に急ぐ。早く着いたが、すでにチラホラと集まっていた。周辺には野次馬なのか、参加者なのか、何人かの人が突っ立っていた。おそらく多くは出入り口や周辺を警備しているおまわりさんにつられているのだろう。
公園の半分は、サッカーなどの練習に興じる若者たちで使用されており、集まりつつある高年の人々と好対照を成していた。本来ならこの、サッカーに興じる彼らが担うべきものを、すでに社会の中枢から離れかけた人々が行うというのは、なんとも皮肉なことだ。しかしそれは、彼らがやってきたことへのツケ以外の、なにものでもないと思う。この温度差こそ、彼らの敗北なんじゃないだろうか。
このデモへの呼びかけをネット上で見たが、どうも形容しがたいもどかしさを感じた。「君の得意な楽器や、ヨサコイ祭りのような衣装で参加を!!」というのだ。
こういった文で若者を動員しようと思ったのだろうか。何年か前、勉強のためにある大規模なデモに参加した。それこそ機動隊が何百人単位で出動するようなデモ。しかしこれも、若者が参加しているとはいえ、しょせん楽器を鳴らすだけに終わった。
機動隊に向かって「お前らに何ができるってんだ!何かやってみろよほら!上の命令がねえと何もできねんだろ!!」と飛ばしていたが、実際、その人自身、何もできてなかった。それだけのエネルギーがあって、目の前の機動隊員の盾すら蹴れない。これのどこが反権力なんだろう・・・
忘れてしまったのかもしれないが、じっくりと思い出して欲しい。
当時も、そして今も、若い人々が闘おうとするのは、そこにロマンがあるからだと思う。チンドン屋の真似事をしたって、それで何かが起こせると考える若者は、今はいない。
その後、案内して下さるMさんと合流する。
あんまり人が少ないので「これって、集まりいい方なんですか?」と聞いたら「いや、悪いね」と。
やがて時間になり、デモが始まる。しかしそれでも出発すると、どこから合流したのか、200人近い行列となっていた。
そしてそれこそどこから現れたのか、百何十人だかのおまわりさんまで規制に現れ・・・・
つづく
実に二万人もの市民、学生、労働者が新宿駅構内外での実力闘争を闘い抜いた。翌22日の午前0時過ぎに騒乱罪が適用され、734人の人々が検挙された。
映画『怒りをうたえ』の冒頭はこの日の生々しい記録から始まる。
さて、現在に目を移すと、このデモが当時の意志を受け継がれ、いまだ行われていることが判明した。といっても去年から。
それで二回目の今年は、10・21を京都でやり、東京では前日の10・20に行われるらしい。
「意志」の今と昔を見比べるのに、これほどの好材料もなかなかない。取材に行ってみた。
当日。
もし機動隊が出ててもみくちゃになったりして、足を踏まれたりしたらヤなので、登山靴を履いていく。走り回るのでジャケットの下にはTシャツ1枚といういでたち。それにカメラはもちろん、相棒のDVX100。約2年ぶりにアナモフィックレンズを装着し、ショルダーベルトを通す。これに上から薄手のバッグを被せ、ベルトを直接肩にかける。
一眼レフカメラとかならオシャレに見えもするが、さすがにデカいビデオカメラを、裸で堂々と持ち歩けない。街頭ならまだしも、電車とかでややうしろめたい気持ちとなる。
あとは私物や予備バッテリー、テープなどを鞄につめこむ。とにかく軽装をこころがけた。
昼過ぎ、新宿到着。
牛丼をささっと食い、集合場所の大久保公園に急ぐ。早く着いたが、すでにチラホラと集まっていた。周辺には野次馬なのか、参加者なのか、何人かの人が突っ立っていた。おそらく多くは出入り口や周辺を警備しているおまわりさんにつられているのだろう。
公園の半分は、サッカーなどの練習に興じる若者たちで使用されており、集まりつつある高年の人々と好対照を成していた。本来ならこの、サッカーに興じる彼らが担うべきものを、すでに社会の中枢から離れかけた人々が行うというのは、なんとも皮肉なことだ。しかしそれは、彼らがやってきたことへのツケ以外の、なにものでもないと思う。この温度差こそ、彼らの敗北なんじゃないだろうか。
このデモへの呼びかけをネット上で見たが、どうも形容しがたいもどかしさを感じた。「君の得意な楽器や、ヨサコイ祭りのような衣装で参加を!!」というのだ。
こういった文で若者を動員しようと思ったのだろうか。何年か前、勉強のためにある大規模なデモに参加した。それこそ機動隊が何百人単位で出動するようなデモ。しかしこれも、若者が参加しているとはいえ、しょせん楽器を鳴らすだけに終わった。
機動隊に向かって「お前らに何ができるってんだ!何かやってみろよほら!上の命令がねえと何もできねんだろ!!」と飛ばしていたが、実際、その人自身、何もできてなかった。それだけのエネルギーがあって、目の前の機動隊員の盾すら蹴れない。これのどこが反権力なんだろう・・・
忘れてしまったのかもしれないが、じっくりと思い出して欲しい。
当時も、そして今も、若い人々が闘おうとするのは、そこにロマンがあるからだと思う。チンドン屋の真似事をしたって、それで何かが起こせると考える若者は、今はいない。
その後、案内して下さるMさんと合流する。
あんまり人が少ないので「これって、集まりいい方なんですか?」と聞いたら「いや、悪いね」と。
やがて時間になり、デモが始まる。しかしそれでも出発すると、どこから合流したのか、200人近い行列となっていた。
そしてそれこそどこから現れたのか、百何十人だかのおまわりさんまで規制に現れ・・・・
つづく