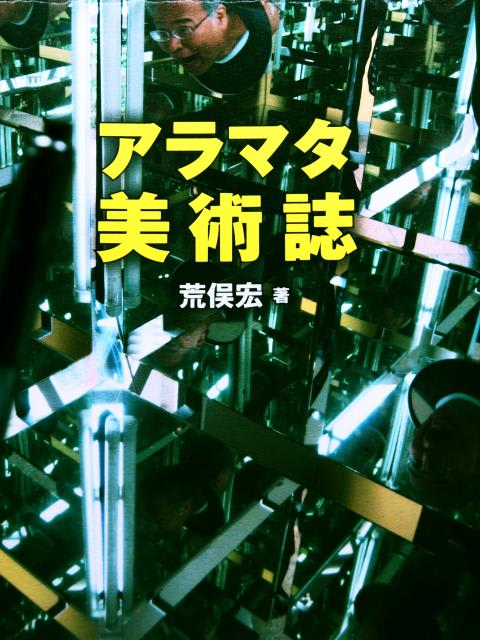友人N氏からお借りした 漫画 「へうげもの」
これがまぁ大傑作で大笑いさせられました。
戦国時代を出世と物欲で駆け抜けた古田織部の物語で、たくましいというか飄々としているというか、とにかくスゲーのです。
寝る前に読み出すと止まらなくなってついつい夜更かしする毎日でした。
ところで、石川県にゆかりのあるところとして前田利家も脇役の一人として登場します。 前田家といえば加賀百万石の大大名ですが、とんでもなくいい加減というか、何も考えちゃいない、まるでわけの分からない性格に描かれています。 死の間際にも息子たちから徳川・豊臣どちらにつけばいいかと問われたときも、どっちつかずの返事で、なんでこの人が大名になれたのか不思議に思える描き方。そもそも 「へうげもの」 の登場人物たちは、みな濃~い性格の人たちばかりで、まさに過剰な人々的なんですね。 戦に明け暮れた激しい時代には、登場人物も激しくなきゃ吊り合わないってもんですね。それだから異様なほどのいい加減さが、よけいに面白かったりする利家でした。
それはそうと、戦続きの中にあっても安土桃山文化が花開いたのは、戦以外にまわせる金があったからで、そういう資源に恵まれていたからかもですね。
ところで、利家の後を継いだのが利常です。利常の三男が初代大聖寺藩主、利治です。
利治が藩主に就いたのはまだ22歳(1639年)のときで、当時は金や銀の鉱山開発にあたっていたそうですが、見込みがないこと、陶石が発見されたことから、磁器製品の開発に方針転換し、あの九谷焼ブランドを興したといわれています。
九谷焼は殖産政策の一環として始められたともいわれていますが、利治は小堀政一(遠州)から手ほどきを受けた茶人だったそうなので、大いなる数奇者の一人だったと思います。
で、嫁が鍋島勝茂の外孫の徳姫だったものだから、その伝手でもって有田焼の陶工なども雇って作らせたのが始まりかもしれません・・・。
九谷焼(古九谷)については謎が多く、ほとんどが有田で焼かれたものだというのが定説だそうですが、それを覆す証拠なども見つかっているそうで、様々な説がいわれているそうです。
そういう謎を巡って想像を膨らませるのも面白いもんです。そのきっかけになった「へうげもの」でした。