また巡りきた薬師如来の縁日です。今月は埼玉県の伊奈町から蓮田市にかけて歩きました。
いつもどおり地元の慶林寺にお賽銭をあげて参拝したあと、小旅行に出発します。
北小金~新松戸~南浦和~大宮と乗り継いで、ニューシャトルに乗り換えます。東京駅の京葉線ホームほどではありませんが、同じ大宮駅といっても、JRの大宮駅の改札を出てから入場するまで五分もかかりました。
モノレールというのはメカニズムがどうなっているのかよくわかりませんが、走り出すと、一昨年七月の薬師詣でのときに乗って、肝を冷やすような思いを味わった、舎人ライナーと同じように、ゴロゴロと揺れる不愉快な乗り心地です。
走る高さも、高所恐怖症を持つ私には致命的な高さで、建ち並ぶビルやマンションでいうと、四階か五階という高さを走って行きます。
ただ、舎人ライナーと違って救われたのは、座席がボックス席ではなく、山手線や常磐緩行線などと同じロングシートだったことです。フェンスなど目隠しになるものが何もないのは同じですが、立ち上がらない限り、直下は見えないので、半分安心して乗っていられる感じ。ただ、ゴロゴロと揺れる感覚は乗っている限り治まらないので、尻のあたりのこそばゆさは消えません。
九つ目の駅・志久で下車しました。乗ってきたのはこんな電車(?)でした。大宮からの所要時間は十八分、料金はスイカ利用で¥325也。
駅のまわりには何もありません。駅事務所を兼ねた小さな売店があっただけです。
志久駅から十分で無量寺に着きました。
今日、最初に訪ねる予定の薬王寺は地区の公民館の敷地内にあって、無住だということがわかっています。「新編武蔵風土記稿」には、この無量寺が管理しているようなことが記されていたので、表敬訪問のつもりで寄ってみたのですが、「西光山」という山号が掲げられた御堂がポツンと建っているだけで、こちらも無住でした。
「新編武蔵風土記稿」に記されていた、といってみても、いまから二百年も前の記録なのですから、様変わりしていても不思議ではありません。
御堂の左手には石仏の並んでいる区域がありましたが、無住のわりには掃除が行き届いていました。
無量寺から十二分で薬王寺に着きました。道路(埼玉県道上尾環状線)に面していて、左は金刀比羅社。右はどうやら下の画像に見える神輿と山車の保管庫のようです。
金刀比羅社の壁面。
金刀比羅社の後ろに薬師堂がありました。これが薬王寺。祀られているのは薬師如来です。寅年だけに御開帳があるそうです。
薬王寺から十二分で曹洞宗・建正寺に着きました。嘉永七年(1854年)に建立された山門です。
古記録によると、平安時代末期の寿永年間(1182年-84年)、岩崎将監という人が丸山というところに堂宇を建てたのが始まりです。四百年後の慶長年間(1596年-1615年)、伊奈備前守忠次(1550年-1610年)が陣屋を築くのにあたって現在の地に移されました。それまでは臨済宗の寺院でしたが、曹洞宗に改められました。 
薬師堂です。
画像ではハッキリしませんが、掲げられている扁額には間違いなく「薬師堂」とありました。掲示板には薬師如来の鉄仏像(伊奈町指定文化財)が安置されているとありますが、伊奈町のホームページを視ると、祀られているのは同じ鉄仏像でも、阿弥陀如来立像とあるのです。画像も載っていますが、どのような印を結んでおられるのか、小さ過ぎてよくわかりません。
画像に見える光背は舟形光背で、阿弥陀如来の象徴的な光背ではありますが、阿弥陀如来を祀っているのに薬師堂とは、これいかに、です。
腑に落ちないところを訊ねてみようと思った矢先に、本堂では木魚を叩く音がし始めました。
我が宗門のお寺ですから、木魚の音が熄むのを待ち方々、まずは歴住の墓所を捜しに墓域に入ります。
由来を記したものはないので、樹齢がいかほどかわかりませんが、本堂左にある枝垂れ桜です。
歴住の墓所に参拝したあと、本堂前に戻りましたが、ポクポクという木魚の音だけが聴こえて、読経の声は聴こえません。しばらく待ったのですが、木魚の音は熄みそうにありません。
今日はまだこの先があります。帰ったらゆっくり調べてみようと思い、疑念が残ったままでしたが、立ち去ることにしました。
建正寺から十三分歩いて清光寺に着きました。参道の延命地蔵尊。
長い参道の奥に真新しい観音堂がありました。通称・小室観音堂。
先の観音堂の由来を説明する掲示板には、本尊は薬師如来と記されており、墓所には墓参する前に本尊にお参りするよう注記が掲げられていましたが、観音堂以外にお寺らしき建物がありません。
念のため観音堂の左を抜けて進むと、大きな民家があると思ったところにこんな表札がありました。しかし鉄扉はガッシリと閉ざされています。お寺だとしても、塀の奥には庫裡かと思われる建物が見えるだけで、本堂と思われるような伽藍は見当たりません。
塀に沿って進むと、小貝戸貝塚の石碑がありました。約六千年前、縄文時代前期の貝塚です。ヤマトシジミを主として、アサリ、ハマグリ、ハイガイなどの貝殻が出土しています。
左に屋根の庇がちょっとだけ写っているのは不動堂。ここにも門はあるのですが、ガッシリと鍵が下ろされていました。
建正寺、清光寺と、野球に例えるなら、2打席連続の三振。それも不本意なハーフスウィングの三振に切ってとられたような気分です。
清光寺をあとにすると、一面の田園地帯が拡がっていました。
十分ほど歩いたところの小貝戸堰橋で渡るのは綾瀬川です。
東京・葛飾区で中川と合流する綾瀬川は満々と水をたたえていますが、このあたりでは用水路のような細々とした流れです。
この川を渡ると、伊奈町から蓮田市に入ります。
さらに小右ェ門橋で見沼代用水を渡ります。
先の田園地帯を通り抜けて綾瀬川に突き当たったとき、右に曲がって、川沿いを南下しなければならなかったところを、誤って北上してしまったので、遠廻りを強いられています。
おまけに、依然として使い勝手のよくないスマートフォンの地図は、画面の自動回転をオフにしていたのにもかかわらず、使用者である私の許可を得ることなくオンに変わっていて、横になったり縦に戻ったり……。
見沼代用水の左岸を歩いて行くと、神社の背面を思わせる建物が見えたので、抜けられるかどうかはわからずに足を踏み入れてみたら、閏戸(うるいど)の久伊豆神社でした。実際は抜けることができたのですが、地図上では径はありません。
久伊豆神社の鳥居を抜けたところが蓮田北小学校の校門前。そのすぐ先に閏戸の薬師堂がありました。
この日最後の目的地です。パッと見たところ、間口は七間から八間ありそうな、大きな御堂でした。
この薬師堂は秀源寺というお寺が管理しているようです。 秀源寺はここから歩くと十四~五分の距離であり、我が宗門のお寺であるようなのですが、そこから西北に進むと薬照院という、薬師如来をお祀りするお寺もあるので、いつかの薬師詣での日に訪れることを誓って、今日は行くのを割愛することにしました。
薬師堂をあとにさらに進むと、国道122号・蓮田岩槻バイパスに出ました。中閏戸という停留所でバスを待とうと思っていましたが、バス停に着いたときはバスがくるまで十六分もあったので、一つ先の停留所(吹上)まで歩きます。
一昨日六日、昨七日と今季最強といわれる寒気に見舞われました。今日も最低気温こそ氷点下を記録しましたが、日中は暖かい日和に恵まれて、気温は三日ぶりに10度を超えました。この日は夜になると雪が降るかもしれないという予報で、明日からまた寒さが戻ってくるようです。一日だけポッカリと空いた暖かさのようです。
この蓮田駅でも疲労困憊した脚を引きずりながらプラットホームに降りたところに、沼津行の電車が走り込んできたので、待つことなく帰路に着くことができました。やはり薬師詣でをすると、ほんのちょっぴりですが、佳きことがあります。
最新の画像[もっと見る]
-
 2024年六月の薬師詣で・中野区
2週間前
2024年六月の薬師詣で・中野区
2週間前
-
 2024年六月の薬師詣で・中野区
2週間前
2024年六月の薬師詣で・中野区
2週間前
-
 2024年六月の薬師詣で・中野区
2週間前
2024年六月の薬師詣で・中野区
2週間前
-
 2024年六月の薬師詣で・中野区
2週間前
2024年六月の薬師詣で・中野区
2週間前
-
 2024年六月の薬師詣で・中野区
2週間前
2024年六月の薬師詣で・中野区
2週間前
-
 2024年六月の薬師詣で・中野区
2週間前
2024年六月の薬師詣で・中野区
2週間前
-
 2024年六月の薬師詣で・中野区
2週間前
2024年六月の薬師詣で・中野区
2週間前
-
 2024年五月の薬師詣で・豊島区
1ヶ月前
2024年五月の薬師詣で・豊島区
1ヶ月前
-
 2024年五月の薬師詣で・豊島区
1ヶ月前
2024年五月の薬師詣で・豊島区
1ヶ月前
-
 2024年五月の薬師詣で・豊島区
1ヶ月前
2024年五月の薬師詣で・豊島区
1ヶ月前










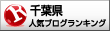







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます