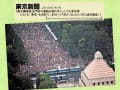[※ ↑ 闘う主張、現場の声支えに 経済評論家・内橋克人さんを悼む (金子勝さん) (朝日新聞 2021年09月08日(水))] /
/ (2021年10月01日[金])
(2021年10月01日[金])
『クローズアップ現代+』の記事【追悼 経済評論家 内橋克人 未来への遺言】(https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/WV5PLY8R43/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/pPLoJBZn8D/)。
《あらためて過去の番組での発言を見ますと、まさに今の時代を予見していたような鋭い洞察に驚かされます。内橋さんは、今も進行中の格差の拡大、すなわち、豊かな者がより豊かになり、貧しい者がより貧しくなるような経済のあり方に警鐘を鳴らし続けました。これを内橋さんは<市場原理至上主義>と呼び、一貫して批判し続けました。そして内橋さんが訴え続けたのは、人間の幸せを中心に据えた「もう一つの経済」は、可能だということです。それは、いったいどういう経済なのでしょうか。》
『●内橋克人さん ―――《今は社会問題と正面から向き合う経済ジャーナ
リストがどんどん減る中で、また優れた知性を一人失った》(金子勝さん)』
『●内橋克人さん《「新自由主義」に代えて…F(フーズ)、E(エネルギー)、
C(ケア) を軸にして地域で雇用を創る新しい経済政策を打ち出した》』
《市場原理至上主義》ではない、《人間の幸せを中心に据えた「もう一つの経済」は、可能だ》。
FEC自給圏、《原発は『プルトニウムをつくる装置』》…本当に尊敬できる経済評論家でした。(宇沢弘文さんが蛇蝎のごとく嫌った)トリクルダウン教祖・竹中平蔵氏などとは全く違う、真の意味での経済ジャーナリストだった内橋克人さん。まだまだお話を聞きたかった《優れた知性》でした。お亡くなりになったこと、とても残念です。
=====================================================
【https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/WV5PLY8R43/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/pPLoJBZn8D/】
追悼 経済評論家 内橋克人 未来への遺言
NHK 2021年9月22日 午後4:35 公開
2021年9月1日、経済評論家で、ジャーナリストの内橋克人さんが亡くなりました。権力におもねらず、弱い人たちの側に立ち続けた、89年の生涯でした。
内橋さんは「クローズアップ現代」に50回出演いただいており、ほかにも「NHKスペシャル」など、多くの番組にご登場いただきました。
あらためて過去の番組での発言を見ますと、まさに今の時代を予見していたような鋭い洞察に驚かされます。内橋さんは、今も進行中の格差の拡大、すなわち、豊かな者がより豊かになり、貧しい者がより貧しくなるような経済のあり方に警鐘を鳴らし続けました。これを内橋さんは<市場原理至上主義>と呼び、一貫して批判し続けました。
そして内橋さんが訴え続けたのは、人間の幸せを中心に据えた「もう一つの経済」は、可能だということです。それは、いったいどういう経済なのでしょうか。
今回は、内橋さんが時代とどう向き合い、どんなメッセージを発信されてきたのかをご紹介します。
(制作局 窪田栄一)
「人間のための経済」を求めて
まず、内橋さんの生い立ちからみていきましょう。
・昭和7年(1932)、神戸市生まれ。
・昭和20年(1945)、13歳の時、神戸空襲を体験。
(太平洋戦争末期の空襲)
・昭和32年(1957)、大学卒業後、神戸新聞に入社。
のちに、フリージャーナリストに転身。
(神戸新聞時代の内橋さん)
・昭和53年(1978) 「匠の時代」を発表。
日本の製造業を担う技術者・技能者の骨身を削る姿を描く。
(匠の時代)
1980年代後半から、日本社会は「バブル経済」に踊り、「マネー資本主義」が台頭し始めました。
そして、1990年代初頭、バブルが崩壊すると、長引く不況から脱出する手立てとして叫ばれ始めたのが「規制緩和」「民営化」「金融の自由化」などでした。
・平成6年(1994) スーパーの出店を容易にする、大規模小売店舗法の規制緩和
・平成8年(1996) 派遣労働者が働くことのできる業種を拡大する、労働規制の緩和
こうした規制緩和の動きに、多くの論者が賛同する中、内橋さんは、時流に流されず、「その改革は本当に人を幸せにするのか?」という観点から、独自の論を展開します。こうした改革はマネーの動きを活発にさせるかもしれないが、働く一般の人びとの利益にはつながらないのではないか、と問題提起したのです。
特に、内橋さんが気にかけたのは、若者たちの未来でした。当時、増えつつあったのが、携帯電話を使って仕事を探し、一日単位で契約して働く、新しい働き方でした。
(携帯電話 画面up)
外食産業や運送業など、さまざまな企業が、人材サービス会社と契約を結んで、必要な時に必要な数だけ一日契約で人を確保することで、コスト削減をはかっていました。
内橋さんは、若者の働き方について、警鐘を鳴らし続けました。
「技能とか技術というのは、ある程度の期間ですね、その仕事に習熟していく。そして習熟をして、自分のものに完全にしてしまってから、そこに能力、あるいは独創力、創造力、そういうものを発揮していく余地が生まれてくるわけですよ。ただそれを細切れにしてしまってね。それだけの創造力、競争力が出てくるかという、そこが一番大きな問題ですね」
Q:こうした働き方が増える中で何が問われているんでしょうか?
「結局、厳しい経済状況の中で、働く側の権利、というものがね。どんどん譲歩させられていると思うんですよ。それはある程度、やむを得ないかもしれないけど、いったいどこで立ち止まるのか。その基準をね、社会全体で、考えるときが来てると思う。その基準は何かといえば、『働く』というのは、人間の尊厳を守る、ということなんですね。ですから、尊厳ある労働、ということは、国際的にも叫ばれているわけですけど、それを割り込まない、そこは、国民的な議論の場にやっぱり持ち出す必要がある、そういう時期に来ている、分かれ道に来ている、といってよろしいんじゃないかと思いますけどね。」
(クローズアップ現代「急増 一日契約で働く若者たち」 2002年1月21日放送より)
(「クローズアップ現代」出演中の内橋さん)
この頃、派遣やパートで働く非正規労働者が急増しました。内橋さんは、労働規制の緩和などによって、正社員が減り、非正規労働者が増えていくことが、未来に与える影響に危機感を抱いていました。
(グラフ:正規雇用と非正規雇用の推移)
Q:パートタイマーが増えてくることを大きく捉えてみますとどういうことになりますか。
「これで行きますと所得が少なくなる、そうすると賃金が減るからマイホームを持てなくなるし、消費もなかなか回すことが出来ない。そうすると景気が悪くなってくる、ということになりますね。あるいは厚生年金一つ見ても、こういう風に所得が低いとですね、自ら負担するということはなかなかできませんね。マクロで見れば日本経済全体として放置していいかと、こういう問題が出てくるんじゃないでしょうか」
(クローズアップ現代「さらば正社員・主役はパート」 2001年10月24日放送より)
2008年に起きたリーマンショック。このとき、内橋さんが心配した通り、日本企業は一斉に派遣切りに踏み切ります。年末の東京・日比谷公園に開かれた年越し派遣村には、仕事も住まいも失った人々が押し寄せました。
内橋さんはこの頃、マネー資本主義が猛威をふるう中で、日本に新たな貧困が広がっていると指摘しました。働いても働いても貧困から抜け出すことの出来ない、「ワーキングプア」の存在です。
「結局、勤労、働くということにね、どう報いるかというのが、その国のね、本質を物語るわけです。このままいきますとね、やっぱり生活するのに必要な最低の収入さえ得ることのできない勤労者、働く人ですね、マジョリティになる、多数派になる。貧困マジョリティ、少数派ではない、貧困者は多数派になりますよ。そんな国がどうして豊かな国だといえますか?」
(NHKスペシャル「ワーキングプアⅡ 努力すれば抜け出せますか」2006年12月10日放送より)
内橋さんは、人の幸せにつながる新しい「人間のための経済」を提唱していました。
未来への遺言 FEC自給圏とは?
(「クローズアップ現代」出演中の内橋さん)
内橋さんは、批判するだけでなく、「人間のための経済」を実現するための、具体的な構想も提唱し続けていました。「FEC自給圏」という、未来の持続可能な社会のデザインです。それはいったいどういうものなのでしょうか? 本人への詳しいインタビューを下記のサイトで読むことができます。
地域づくりアーカイブス インタビュー・地域づくりへの提言 いまこそ人と人とが共生する経済への転換を
地域づくりアーカイブス インタビュー・地域づくりへの提言 グローバル資本主義を超える「もう一つの経済」とは
内橋さんの「未来への遺言」は、コロナ後の世界のあり方や私達の生き方を考える上で、大切な指針になるのではないでしょうか。
内橋さんが出演したクローズアップ現代リスト
1993年 4月14日 査定導入で生き残れ 町工場の雇用改革
1993年 6月23日 新党結成・羽田代表の本音に迫る
1993年 7月29日 政権交代へ ~非自民7党党首に聞く~
1993年10月 5日 対論・どうする所得税減税
1994年 1月13日 零細経営者はなぜ死を選んだのか ~丹後ちりめんの里~
1994年 3月 1日 さらば東京 ~不況で増えるIターン志願~
1994年 3月 2日 ホワイトカラーの合理化が始まった ~組織改革の舞台裏~
1994年 3月 3日 “半値”で生き残れ ~これがスーパーの生き残り戦略だ~
1994年 5月11日 町工場に技あり ~格闘・ポテトフライ製造器開発~
1994年 6月16日 ロボットから人手へ ~トヨタ・主力工場の大変身~
1994年 7月11日 負債5000億円からの再建 ~追跡・戦後最大の倒産~
1994年 7月12日 戦後初!信用組合解散の内幕
1995年 2月 9日 焼け跡からの再建 ~地場産業壊滅の中で~
1995年 3月13日 職人技が消えていく ~国産技術が危ない~
1995年 5月10日 円高・それでも海外移転せず
1995年 8月31日 海外移転はしたけれど ~人件費高騰・増える工場撤退~
1995年10月24日 損失1100億円はこう隠された ~大和銀行事件の構図~
1995年12月 4日 急増する住宅ローン破産 ~賃金下落・返済計画の危機~
1996年 1月29日 給料は上がらないのか ~ベア・定昇廃止宣言の衝撃~
1996年 5月14日 継続か見直しか? ~臨海副都心開発・迫られる決断~
1996年 6月21日 負債136兆円 ~岐路に立つ自治体~
1996年12月 5日 負債は誰が背負うか ~急増・第3セクターの破たん~
1997年 2月26日 部品ひとつが自動車産業を止めた ~検証・ブレーキ部品工場火災~
1998年 1月13日 商店街が消えていく ~スーパー撤退の波紋~
1998年 4月 1日 3社長はなぜ自殺したのか
1998年 8月26日 逆流する自動車部品 ~アジア進出企業 生き残り戦略~
1998年12月 1日 「貸し渋り」解消になるか ~中小企業40兆円融資の行方~
1999年 1月21日 就職先が決まらない ~変革迫られる職業高校~
1999年 2月23日 厚生年金 相次ぐ企業の脱退
1999年 9月 8日 問われる二重価格 ~検証・安売り商品の値段~
2000年 1月12日 阪神大震災から5年 苦境に立つ中小企業
2000年 7月27日 中小企業を救えるか ~検証・民事再生法~
2001年 8月 2日 タクシー運転手が足りない
2001年10月24日 さらば正社員 主役はパート
2002年 1月21日 急増一日契約で働く若者たち
2002年 5月14日 会社の中で独立します ~広がる個人事業主~
2002年12月 4日 高速を走る“過労トラック”
2005年 6月23日 街中に人は呼び戻せるか ~高齢化時代の都市再生~
2005年12月15日 故郷が消えていく ~相次ぐ集落崩壊~
2006年 6月 6日 割りばしに異変あり
2006年11月21日 隠される“労災” ~製造業の現場で何が~
2007年 4月26日 作家・城山三郎がくれたメッセージ
2008年 3月12日 正社員化が加速する
2008年11月20日 急増する“荒廃”マンション
2009年 4月23日 シリーズ オバマの100日② 医療保険制度改革のゆくえ
2010年 1月27日 正社員の雇用が危ない
2011年 3月30日 連鎖する震災ダメージ どうする日本経済
2011年10月17日 “自給力” ~食とエネルギーを自給する暮らしの可能性~
2012年 3月 1日 震災データマップ 記録が語る新事実
2014年10月30日 人間のための経済学 宇沢弘文 ~格差・貧困社会への処方箋~
番組情報
「追悼 経済評論家 内橋克人 未来への遺言」
放送 9月23日(木)NHK総合 10:05~10:30
(再放送) 9月30日(木)NHK総合 00:24~00:49 ※水曜の深夜
=====================================================
『●『もうひとつの日本は可能だ』読了』
「グローバリゼーション (「市場化」・「民営化」) のオルタナティブ
として、FECの地域内自給自足権 (圏) の確立こそ重要であることが
提唱…。FECとは、Foods (食糧)・Energy (エネルギー)・
Care (人間関係=医療や教育等)」
『●『浪費なき成長』読了』
『●『不安社会を生きる』読了(1/2)』
『●『不安社会を生きる』読了(2/2)』
『●『新版 悪夢のサイクル/ネオリベラリズム循環』読了(1/4)』
『●『新版 悪夢のサイクル/ネオリベラリズム循環』読了(2/4)』
『●『新版 悪夢のサイクル/ネオリベラリズム循環』読了(3/4)』
『●『新版 悪夢のサイクル/ネオリベラリズム循環』読了(4/4)』
『●原発絶対断固反対!』
『●FECにつながる「地給率」』
『●SLAPPと祝島』
『●TPP批判: 内橋克人さん』
『●まさに、FEC自給圏を目指せ』
『●内橋克人さんインタビュー:
〝貧困マジョリティー〟の形成と『FEC自給圏』への志向』
『●衆院選の惨敗と参院選という正念場:
FEC自給圏・「浪費なき成長」と「暗闇の思想」』
『●原子力ムラに対して、開き直ろう!:
こういう挑発や脅し、騙しに乗ってはならない』
『●居直ろう!: 〈毒食わば皿まで〉?
「一度認めた以上、どこまでも認めるという論理の一貫性」?』
『●電源構成(エネルギーミックス)案という貧相な「未来図」:
泥棒やその子分に縄をなわせる愚』
「ニッポンにとって、デンマークはとても参考になると思うのですが?
内橋克人さんのFEC自給圏の確立を」
『●「原子力の平和利用」という核発電への幻想…「原発は『プルトニウム
をつくる装置』」(内橋克人さん)にこだわる周回遅れのニッポン』
『●「始まりの地、福島から日本を変える」:
シェーナウ電力、会津電力、飯舘電力…内橋克人さんのFEC』
『● FEC自給圏(内橋克人さん)…《地域の中で隣人同士が見守り合い、
支え合いながら、病気を予防し、重症化を防ぎ、健康寿命を延ばす》』