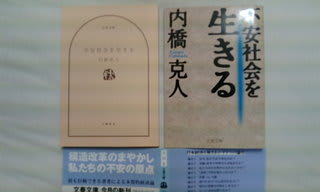
 【内橋克人著、『不安社会を生きる』】
【内橋克人著、『不安社会を生きる』】「日本には個人貯蓄が一千二百兆円もある・・・豊かな貯蓄を持っている国は日本以外にはない」という幻想、「個人の貯蓄の大きさを指摘する議論ほど、無意味なものはない」(p.107)。約半分は「個人事業者の事業用資金」、残り大半は約十数%の富裕層の貯蓄であり、「平均像としての貯蓄額は二百万円から四百万円の範囲に集中」。「リタイアした人びと・・・貯蓄総額の五〇パーセント以上を保有・・・当然ながら、その貯蓄は老後のための蓄えであり容易に消費に回されるものではない」。「消費の中核を担う二五歳から四五歳までの世帯では、貯蓄より借金の方が大きくなっている。/要するに、個人も借金漬けなのであり、高い貯蓄額の数字だけをもって日本人は豊かであるというのは幻想に近い。」
「景気が回復するとは・・・国民一人ひとり、勤労者一人ひとりが自分の立場から見て、自分の働きにふさわしい報酬を得ることができるということではないだろうか」(p.109)。この不景気の世だからこそ、かみしめたい言葉。
「小泉政権のすすめる不良債権処理策の実質が、企業の債務を国に移し、時を狙って、今度は、国の債務を一人ひとりの生活者の家計へと移し・・・」(p.177)。「「自己責任」は企業ではなく、もっぱら個人に押しつけられている。・・・/・・・従業員は・・・レイオフや解雇の対象となることを覚悟しなければならず・・・。/・・・しかし、「規制緩和は若干の痛みをともなう」とうたっているのだ・・・。/「若干の痛み」とは何を指しているのだろうか。/・・・九百三十四万人の失業者! 千六十四万人の新規雇用? いったいどのような根拠あっての数字だったのであろうか。そして、これが「若干の痛み」であろうか。/この驚くべき「非現実性」・・・/経団連・・・まさに生活者には「自己責任」を求め、自らはその埒外に立つという習性に発しているのではあるまいか」(pp.194-197)。
再販制度(p.154)。「教育の機会均等」にならぶ「情報の機会均等」に貢献。
「従来、国際通貨基金(IMF)、世界銀行は人道主義的支援が大きな精神的バックボーンだった。・・・アジアを救済するのあたり、支援と引き換えに市場化を要求するように変わってきた。・・・/・・・MAI(多国間投資協定)もアメリカの覇権を打ち立てようとする強い意志のシンボルだった」(p.217)。
「・・・イスラムの金融機関は利子、利息の概念そのものを禁じている。・・・利が利を生むマネー資本主義に対するアンチテーゼがイスラムにはある。/・・・とってかわるのではなく、市場経済をより健全なものにする上で価値の高い対抗思潮だと思います。」(p.218)。自給自足圏の中でも安定した経済成長は可能かとの問いに、「ほどほどの成長は可能です。それを実践しているモデルは世界にたくさんあります。『浪費なき成長』です」(p.221)。いわゆるFEC。「BSE問題の発端、肉骨粉に関しても飼料穀物の輸入自由化にさかのぼる長い歴史検証をスキップすることはできない」(p.226)















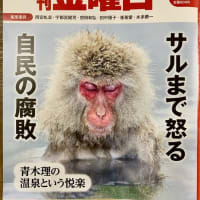







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます